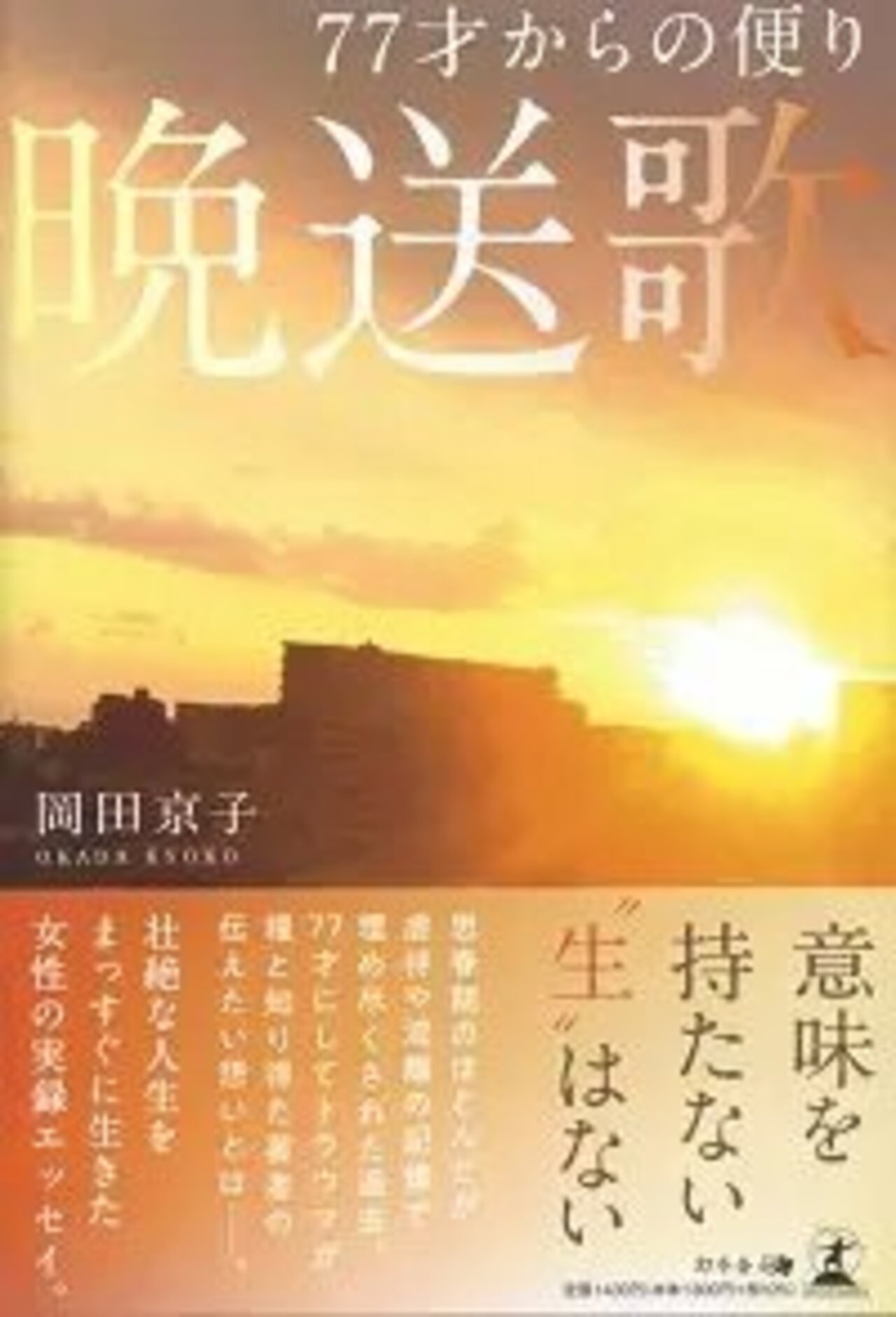或る夜、父がソーッと引き戸を開けソーッと階段を上がって来、シーッと口元に人差し指をあてて私の枕元に竹の皮に包まれたものを置いていった。再びソーッと階段を下りソーッと引き戸を開け今度は〝ただいま〟といつもと同じ様に帰り、信子の寝ている部屋に入るのだった。
私は父の秘密の所作がなんとなく理解でき、その夜のうちに全てたいらげた。残った包装紙は小さくしトイレに落とした。父は私のことで信子に気を使い何も云えずにいたと思う、その頃の父の影はとてもとても薄かった。
或る夜夢を見る、私はその頃から起きていても寝ていても夢の中に生きて、あるいは想像の世界の中にいた。或る夜の夢は知る由も無かった我が身の真実、今思えば天国の入り口まで行けたのかと信じられる程の風景だった。辺り一面果てしなく咲く清涼な白い花、その花々の中で佇むのは父と13才くらい、10才くらいの二人の少女、その10才の少女は私だと思った。
その時の夢は何十年も後に意味を持っていた。三人は一つの墓の前に立ち静かに見つめていた。空は青く白い雲が浮かぶ、そして知る由もない曲「白い花の咲く頃」今になってもあり得ないと思う、でも流れていた。隣の部屋のラジオからか、でもなぜその曲だけが聞こえ夢は鮮明だったのか。
私はその頃から何か予知する能力を与えられた様に思う。神はなぜ「流れ子」に人並みの生き方の代わりを授けたのか。それは今も嬉しくは無い、平凡な人生で有ってほしかった……路傍の雑草でも小さな花を咲かせるのに。
暗闇の中、信子は赤いセーターを切り刻んでいる、糸を引きちぎり形を成さぬ程切り刻む。いつも閉めている襖を大きく開けて暗闇の中、人なのか鬼なのか、最後まで私に見届けさせた。私は思った、母が私の為に編んだ私に着せる為のセーターなのだと。私の心まで切り刻むつもりなのだと。父が買ってくれたのかも知れぬが。