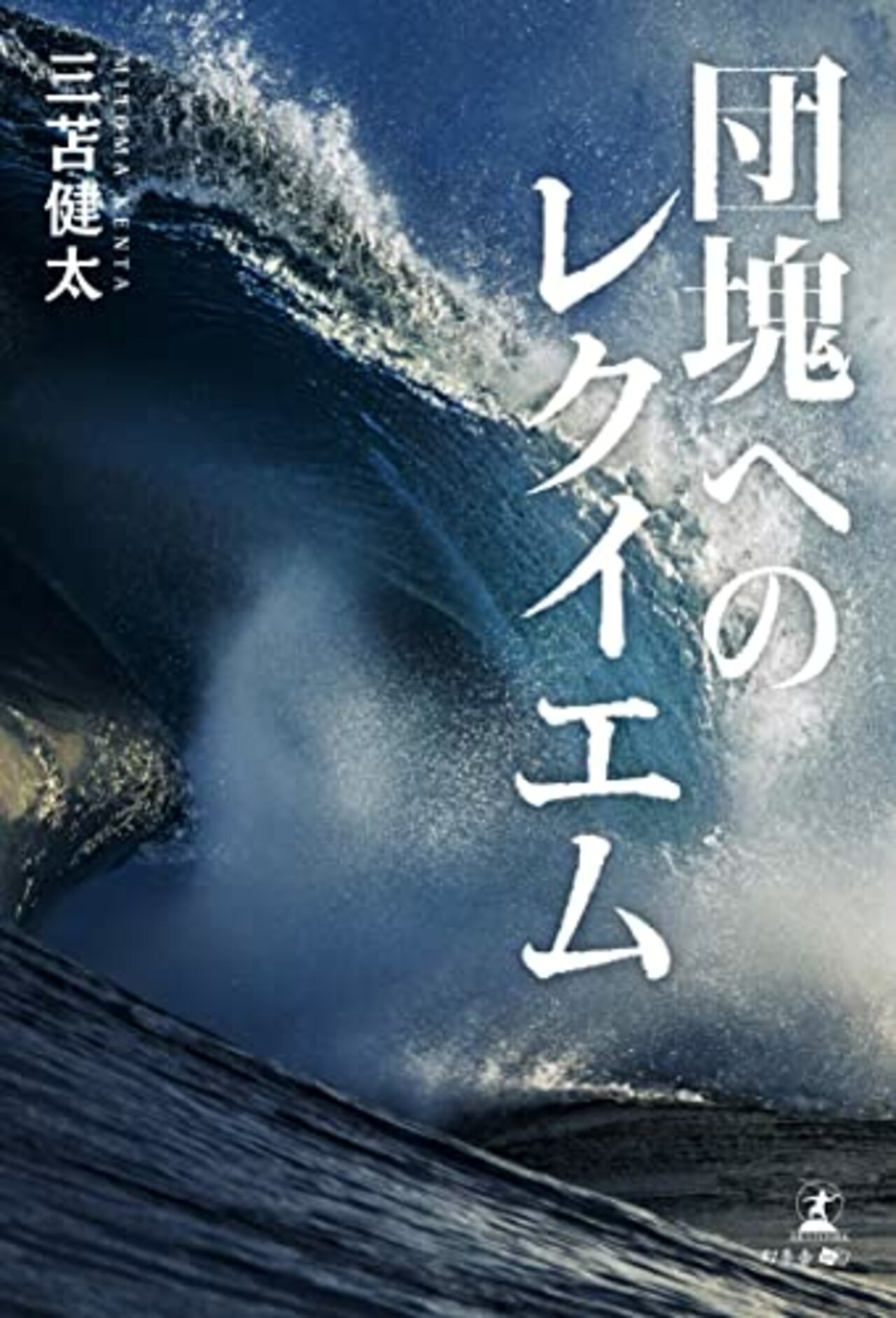2
やまびこ53号は福島駅に定刻に到着した。東京と山形の往復で幾度となく通った駅だが、ホームに立つのは今日が初めてだった。西の遠方には、晩秋の晴れわたった空に吾妻連峰がくっきりとした稜線を描いている。中央には連峰を代表する吾妻小富士がヒョットコの口のような山頂を空に突き出している。
左沢は駅前でタクシーを拾い、福島県警本部に向かった。県警本部の外来窓口で来意を告げると、四階の応接室らしきところに案内された。そこは部屋の片隅をロッカーで囲んで、古びたソファを置いただけのスペースだった。もちろんドアもない。
しばらくして中背で痩身の老刑事が、お待たせして申しわけない、と恐縮しながらやってきた。その胡麻塩頭の老刑事は、警部補の多門恒三と名乗り、聞かれもしないのに、あと半年あまりで定年になると申し添えた。強い東北なまりだったが山形で四年を過ごした左沢に聞き取れない言葉はなかった。ただ、強いなまりは初対面の人に示す多門一流の韜晦のようで、左沢との交流の深まりとともに、なまりも次第に軽微になっていく。
「アテラザワさんとは懐かしい名前だばい。アテラザワと読める人は少ないだっぺ」
多門は左沢の名刺をしみじみと見ながら、故郷の旧友にでも出会ったような目をして訊いてきた。左沢は、ただ「ええ」、とだけ答えた。多門が言うとおり、左沢をアテラザワと初めから読んでくれる人は少ない。
昔はその都度、サザワではなくアテラザワです、と正しい読み方を教えていたものだが、最近では面倒になり、敢えて訂正することは少なくなった。だから、今まで出会った人のうちで左沢をサザワと思い込んでいる人がかなりいるはずだ。
「んだねぇ、普通サザワとかヒダリザワだのしか読めねでば。私は寒河江さ出身でね、左沢は隣の町だかんね。やっぱ、左沢さんもいなかは山形だっぺ」
左沢は父親が天童の出身だとだけ答え、周平の自殺の状況を知りたいと、早く本題に入るよう婉曲に促した。
多門は、そんな左沢に好意を持ったらしく、目を細めながら朴訥とした口調で周平が発見されたときの様子を話し始めた。