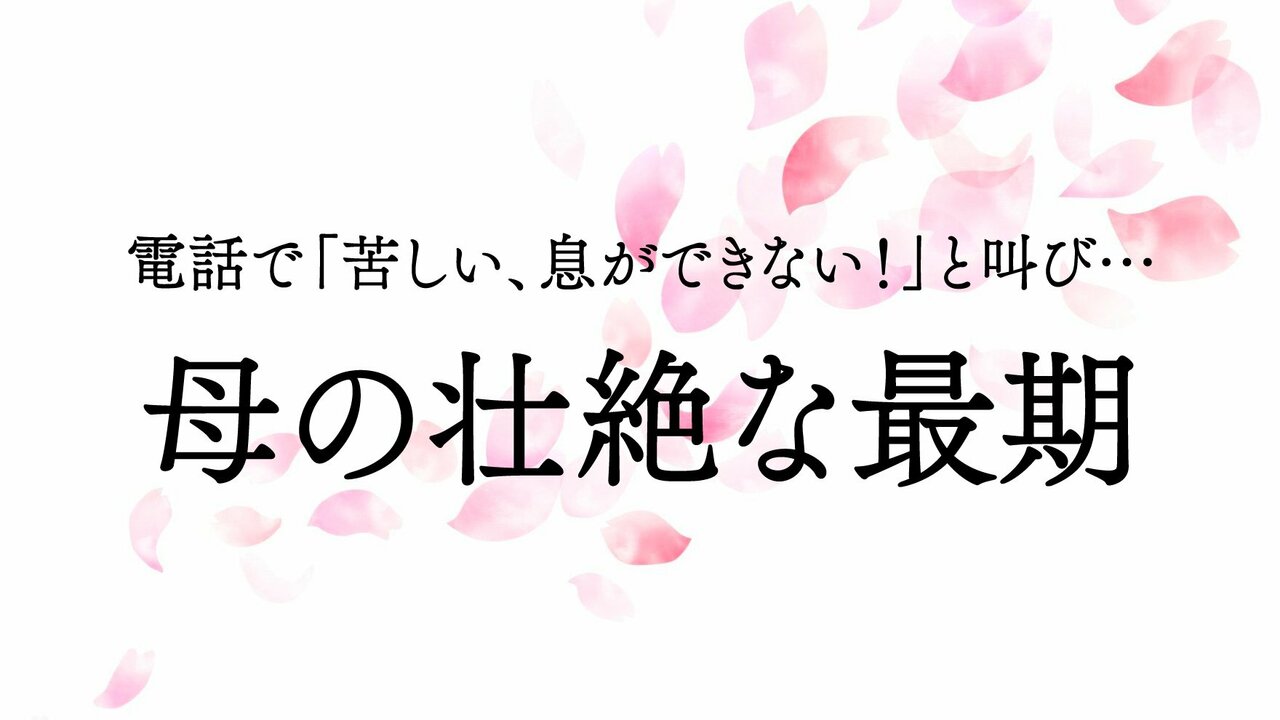残酷な運命
私は足取り軽く去っていく彼女の後ろに、もう一人の女性の影を見ていた。この年恰好の似通った二人の女性は一時期ベッドを並べていた。そして一人は幸せをつかみ、一人はこの世にいない。運命と言えば運命なのだろうが、なんと残酷なことであろうか。
私は、今はこの世にいない女性の顔とレントゲン写真を思い出していた。
いつもと変わらぬ朝だった。午前8時20分、私は白衣に着替えている最中であり、隣の部屋では老医師が煙草を吸い、時折音を立ててお茶をすすっていた。
結核病院には昭和の色がこびりついている。
突然、電話が鳴りマイクを通して院長の声が響いた。
「誰かNという女性の患者を知っているか?」
「ええ、知っています。この間まで結核病棟に入院していて、先日外来に来ましたが」
色白の痩せた顔が目に浮かび、いったい何事だろうかと私は思った。
「Nが自宅で死んだと警察から電話が入っているから代わってくれ」
自分は関係ないと言わんばかりに院長は早口で言った。
「えっ、警察から?」
その瞬間、私は自殺だと思った。電話の相手が変わった。私は受話器をとった。
「主治医の先生ですか。警察の者です。Nさんが昨夜亡くなられまして、以前先生の病院に入院されていたということでお電話させていただいております。入院時の詳しい事情を知りたいのですが」
「大体の経過でよろしいでしょうか?」
「いえ、できるだけ正確な経過をお聞かせ願いたいのですが」
警察官の口調は事務的で、多くの事件の中の一つを一連の手続きで片付けていくような雰囲気だった。
「では、カルテを見ながらお答えしたいと思いますので、折り返しお電話させていただきます」
私は一度電話を切ることにしたが、最後に一番気になっていることを尋ねた。
「ところで、どうして亡くなられたのでしょうか?」
「血を吐いて、えーと喀血だそうです。救急病院に搬送されましたが、だめだったということです」
自殺でなくて正直私はほっとした。受け持ち患者が自殺すると直接の原因が自分にはなくとも主治医は打ちのめされる。