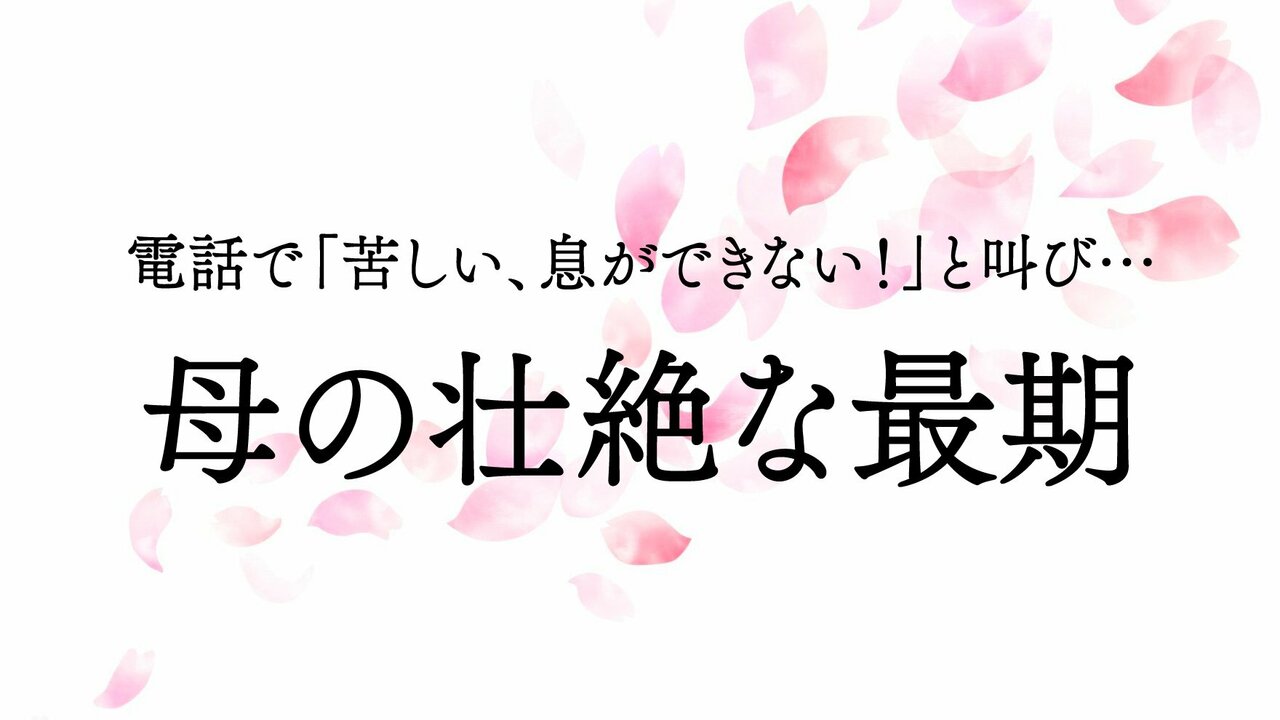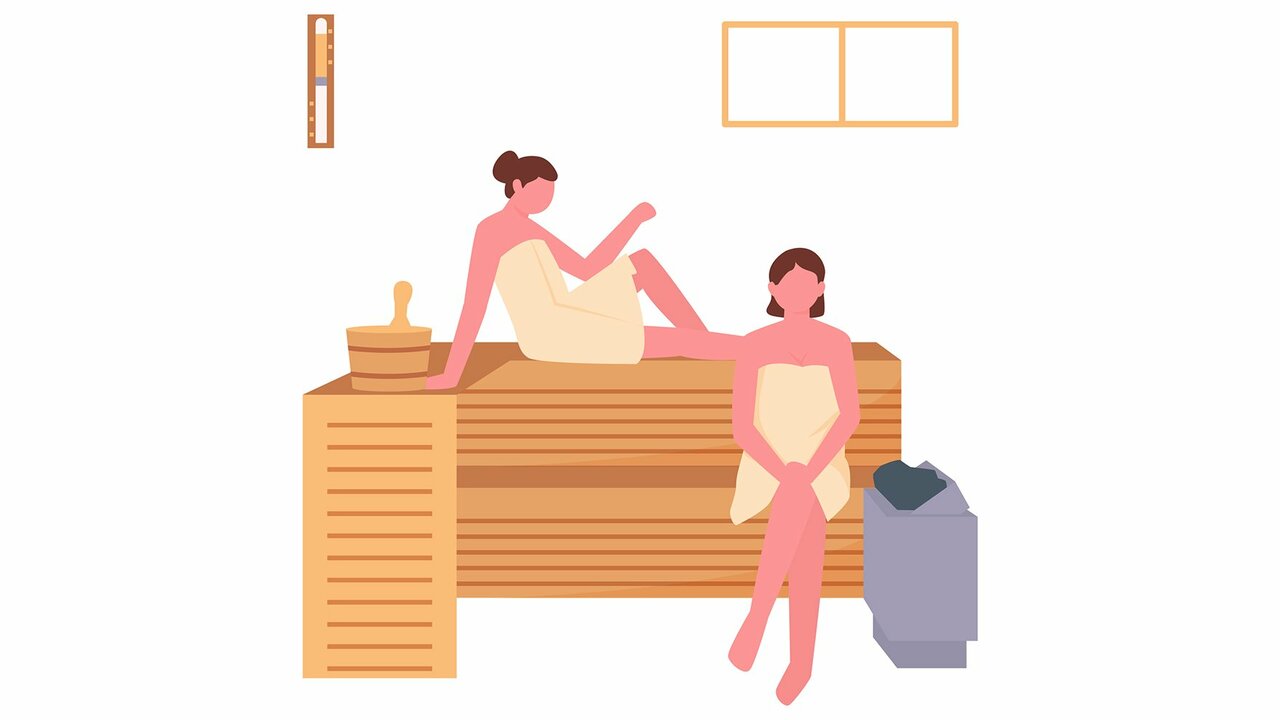【前回の記事を読む】一見“ヤンキー”風だが…結核の彼女を支える男の深い愛情
私は悪魔の手先?
事務所に連絡してカルテが届くのを待つ間、私は彼女のことを思い出していた。
胸部レントゲン写真では右肺に大きな空洞があり、約1年間の入院中に数回の喀血があった。喀血の量は少ないこともあったが、受けた膿盆の底が見えなくなるほど出ることも多かった。血圧が下がるほどの喀血があったあと、私は彼女と母親に告げた。
「今回はこれで止まりましたが、だんだん出血量が多くなっていて、次が心配です。おそらく空洞の中で血管が露出していると思います。薬で菌を殺すことはできますが、出血を抑えることはできません」
心配そうに母親は頷く素振りを見せたが、彼女は表情を変えなかった。
「何か方法はありますか?」
母親が尋ねた。
「足の付け根から管を入れて血管造影をして出血している血管を突き止め、それを塞いでしまう方法と、出血している空洞ごと肺を切除するか肋骨を切除して空洞を押し潰す方法が考えられます」
「とんでもない、血管を詰めたり肺を取るなんて、いったいどういうことよ。考える気にもならない」
私が話し終える前に、彼女は強い口調で提案を一蹴した。目は怒りに燃え、白い顔が赤く染まり、息遣いも荒くなっていた。これ以上興奮させるとまた喀血が始まってしまう。
「今すぐとは言いませんが、喀血のコントロールがつかなかったら、そのような選択肢があるという話です」
「つけてみせます。喀血しなくなればいいのでしょう」
彼女が語気鋭く言った。喀血は目に見えるが肺の変化はレントゲン写真を通してしかわからない「間接的な現実」であり、血痰や喀血が主人公の死を意味するのは古い映画の世界だけ、という認識なのだろう。これまで病気とは無縁に生きてきた彼女にとって結核にかかったことは悪夢、結核病棟は突然迷い込んだ異次元のようなものであり、手術などとんでもないことで、それを口にする私は悪魔の手先と感じたに違いない。