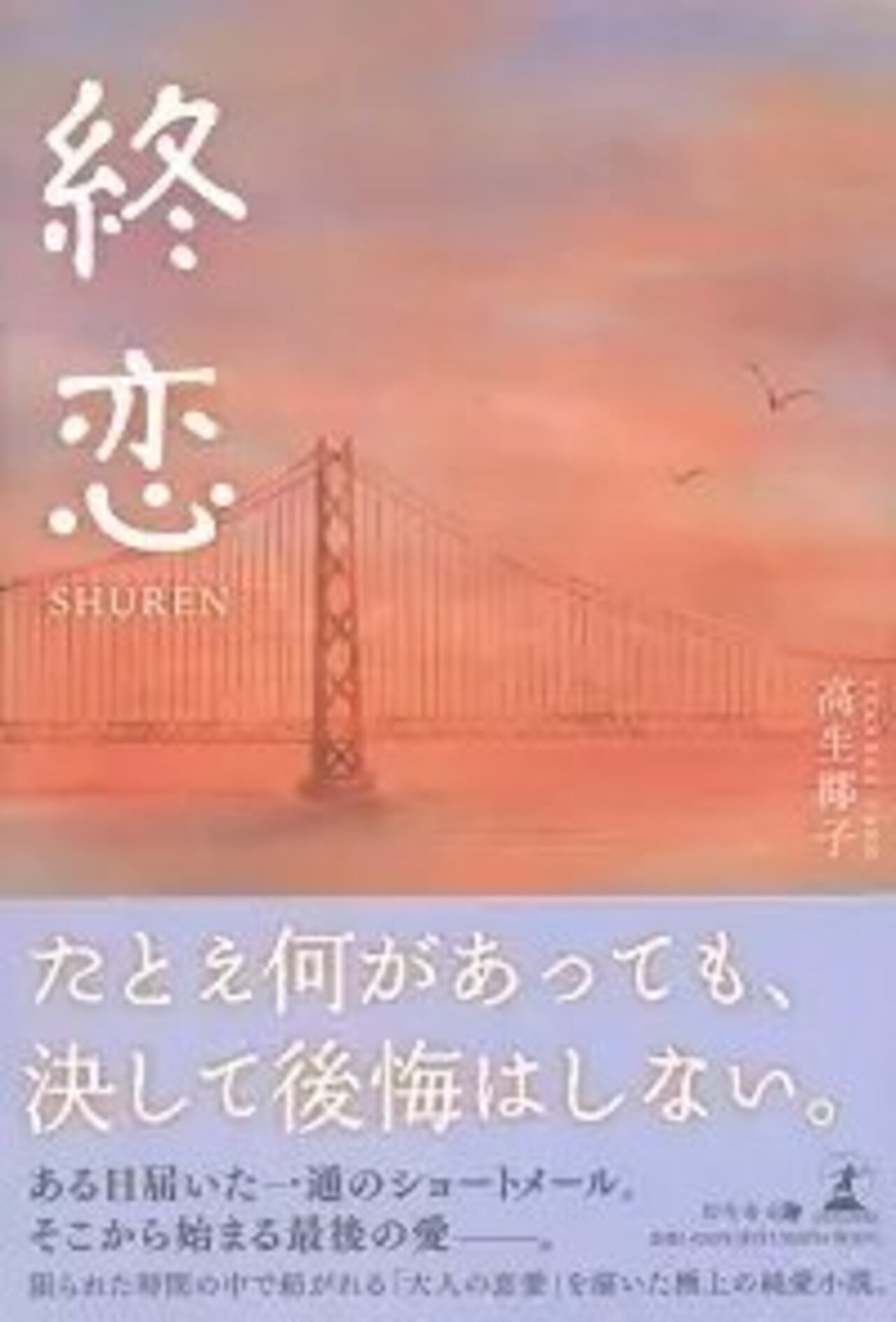男は女とSEXするまでが優しいというが、まさにこの頃までが彼の私に対しての優しさの絶頂期だった。目的を達成するともう用なしという訳ではなかったが、旅行から帰ってきた彼は少し大人になっていた。
それは彼が大学に入ってから顕著になったが、大学という所を知らない私は単に勉強が忙しいのだろうと思っていた。
私が18歳の夏休みに二人で旅行をした。九州に行くことになったが、出発は二人別々のコースにした。あくまで一人旅という親向けの名目だった。
私は南九州へ行き、彼は北九州を旅行した。当時は寝台列車が全盛期の時代で、宿泊は列車を宿代わりにした。最後に長崎で合流し、長崎市内を一緒に観光した。
秋には彼の大学の学園祭に行った。広いキャンパス、化粧をした女子大生が眩しい。お金持ちのお坊ちゃん、お嬢ちゃんが行く大学ということもあり、ほとんどの学生が自家用車で通学していた。
彼の家もお金持ちだった。今考えてみれば、私のような貧乏人の娘とよく付き合ってくれたものだ。
学園祭は煌びやかすぎて、私には場違いな場所だと感じた。田舎娘みたいな高校生を連れて彼は恥ずかしいだろうなと気が咎めた。
その冬のクリスマス、彼は傍にいなかった。学園祭の後、アルバイトの帰りに彼に電話をしたら、こう言われた。
「大学での生活はことりの知らない世界や、お前、ディスコに行ったことあるか、俺は高校生のお前とは違うねん。……俺、好きな女が出来た。こんなに好きになることはもうないと思う。お前とは会われへん」
地下鉄に乗った途端、涙が溢れてきた。泣いているのが周りの乗客に気づかれないように太子橋今市駅までずっと下を向いて座っていたのを覚えている。
悲しい記憶が蘇った。私は24歳の時に捨てられたのではなかったのだ。18歳の冬に最初の破局があったのだ。