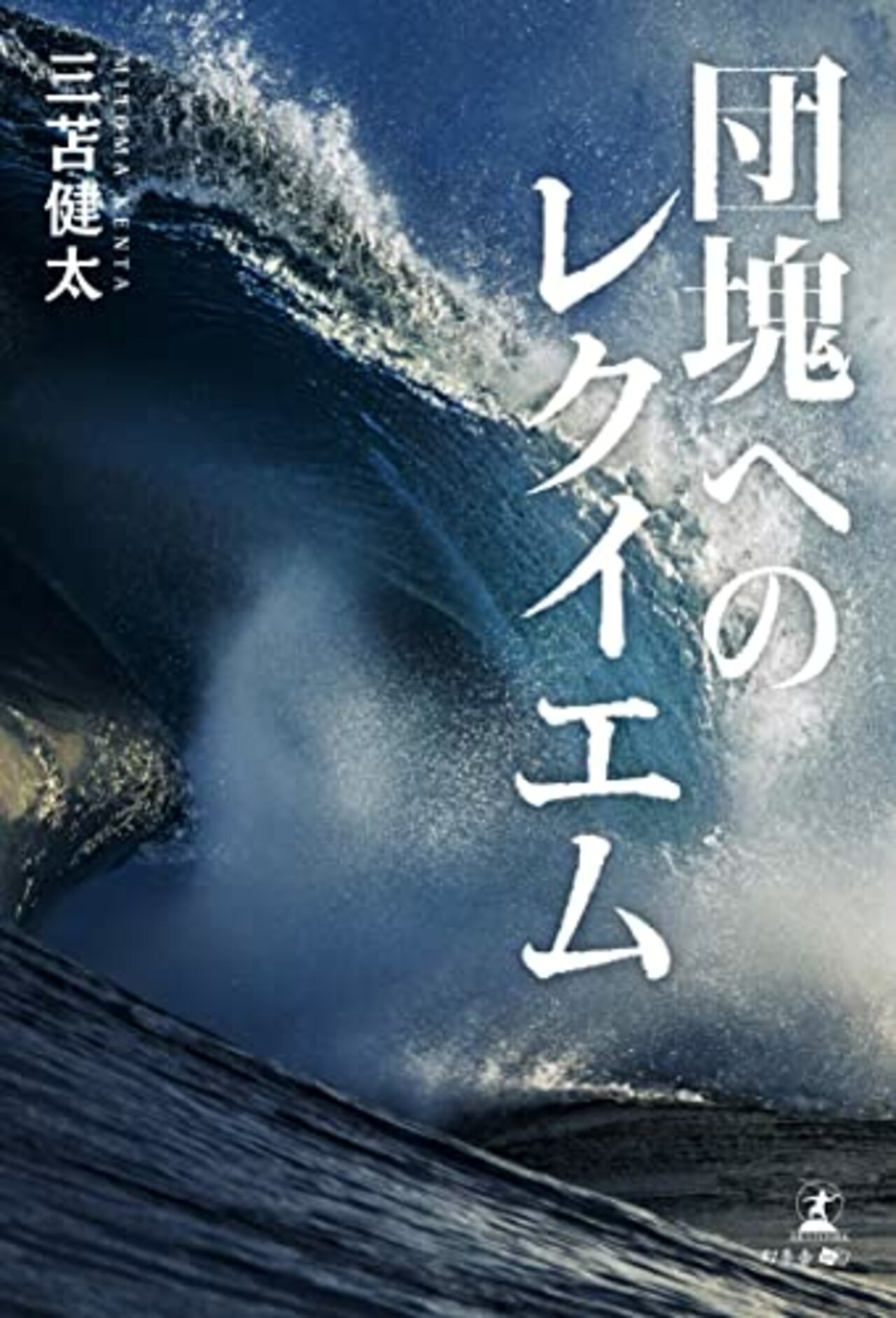「学級委員は気づかなかったと言っているが、左沢くんがいじめに気づいたのなら、なぜ先生に連絡しなかったんだ。いじめを見つけたら先生に連絡するようにと、全校朝礼でいつも言っているはずだがね」、と言いながら校長も左沢を睨みつけてきた。隣を見ると教頭も睨んでいた。
「それに、左沢くんは水沼真一くんの親友じゃないか」
校長の、親友という言葉が胸に刺さった。
(親友ならなぜ助けなかった)
左沢には言外にこう聞こえた。それはもっとも恐れていた言葉だった。昨日、佑太から詰め寄られても口籠るよりほかなかったのは、この言葉を佑太から聞くのが怖かったからだ。左沢は三人の刺すような視線を受けながら、ただ俯き続けた。
(真一を見殺しにした俺は、あのふたり組と同罪ではないか)
翌日、左沢は学校を休んだ。風邪でも腹痛でもない。学校に行こうという気力がまったくわかなかったのだ。その日は終日ベッドの中にいた。翌々日も、その次の日も、自分の部屋に閉じこもったままで一日を過ごした。
四日目の夕方、担任が家庭訪問をしてきた。しかし、左沢は担任に会う気がしなかった。顔を見るのも嫌で、再三の母親の催促にもかかわらず、部屋に閉じこもった。
担任は、「親友を亡くしたショックからでしょうから、本人がその気になるまでそっとしておいてください」、と左沢の部屋にもとどく大きな声で言って帰っていった。
結局、左沢は二学期が終わるまで登校することはなかった。その間、心配した父親は学校側と相談して、名目を病気療養にして、左沢を山形の中学校に転校させることにした。
中学校は父親の母校、下宿先は父親の実家だった。父親から初めてこの話を聞いたとき、左沢はにべもなく拒んだ。しかし、かといって今の学校に復学する気にもなれず、結局は両親の説得に負けて、この話を呑んだのだった。
こうして、左沢は山形県天童市の中学校に転校し、高校を卒業するまでの四年間をここで過ごした。