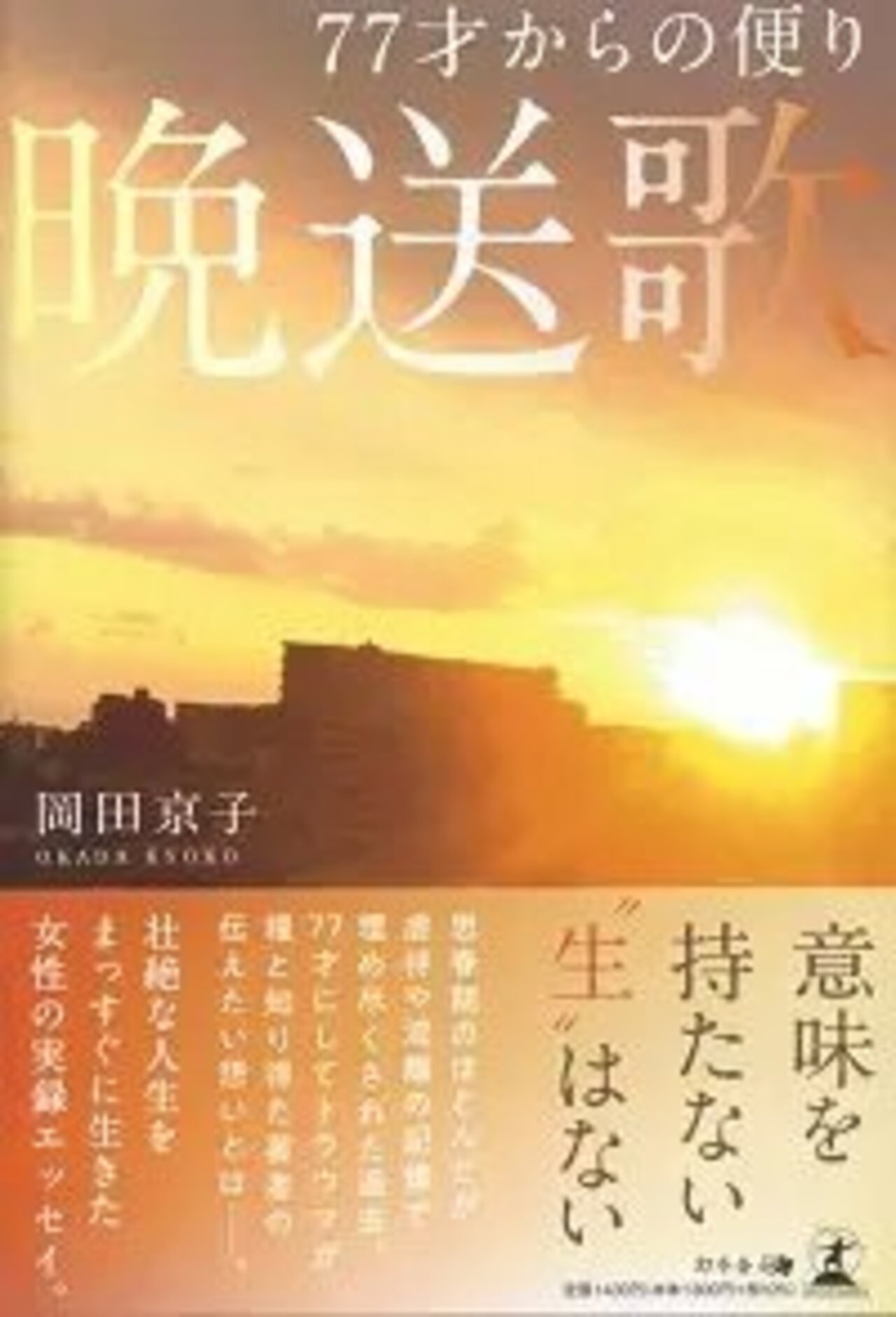第一章 父と信じて、母と信じて。
仕事を終え父が帰って来る。その頃で云うゆうに6尺は有ろうかという決して2枚目とは云えずとも辺りをはらう堂々たる男ぶりだ。その後をいつものごとく3、4人の若い衆がゾロゾロ。彼は大工の棟梁、その彼の様子は男として脂がのり、自信に溢れ、今思うと敗戦後のあらぶれた時代の曙をになう市井の人々の一人で有ったろう。
その頃としては広い方であろう部屋をL字型で囲った土間に入ると途端
“おい美夜子帰ったぞ”
“美夜子どこに隠れた”
その日その日云うことは変わっても仕草はいつも同じ、部屋に上がりドンとあぐらをかき職人のはくニッカポッカと云うズボンの真ん中をドンと叩くのだ。軽くほこりが立つその真ん中に私は飛び込む様にはまり込む。
父はほとんどいつも同じセリフ、“美夜子は今日もエエ子にしてたか”
と部屋中に響き渡る声で云い私の頭をクチャクチャになるほど撫で回す。そして決まって五円玉を出して、
“ホレ、アンドーナツ買こうてこい”
と抱きかかえる様に送り出す。そんな日々の中に何故か母の姿や声は無く憶えもない、3才の頃で有ったろうか。
私は父が仕事に出ている日中のほとんどは、隣の飲み屋と云っても今で云えばちょっとしたミニクラブの様さまを呈した店を経営する姉妹の家に、夕刻店をオープンする頃まで入りびたっていた。誰かは知れず聞き覚えたのは、二人は元タカラジェンヌでその頃流行った天然痘にかかりどちらが後か先か整った顔には俗にいうアバタが残されていた。
何かと不自由な中でも二人は身綺麗に過ごし、時があれば身をやつし長く伸ばした髪は下に新聞紙を広げ私には定かでは無いが30分はブラッシングをするのだ、その頃には未だ無い整髪料の代わりに。
襟足から梳きだす長い髪は幾度も幾度も梳き流され、雪の様にフケは新聞紙の上に積もりだし、4才の私はポカーンと口を開け時と共に艶を増す様を最後まで見届ける。たぶん口の中にもフケをいただきながら。
彼女達は何故か私をいとわずよく映画に連れ出してくれ、洋画、邦画とわず手をつなぎ引っ張り出してくれた。私が夢を見て生きてこれた神の使いの様な姉妹だった。
或る時、父は私に着物を着せて(多分七五三の為に準備してくれたのか)二人で出かけた。電車を乗り継ぎ着いた所で、階段を5、6段上がって行くとお座敷風の小部屋が並んでいる。一室の障子を開けるとそこには今も憶えている肌の色こそ黒いがキリッとした女前と云える様な人がコタツに入って居て、私に笑いかけ手招きしている。その場面の憶えは薄いが何回か同じことが繰り返される。
そんな或る日、父、母の大喧嘩、父は私には見せまいと外に出そうとするが私には見えてしまった。