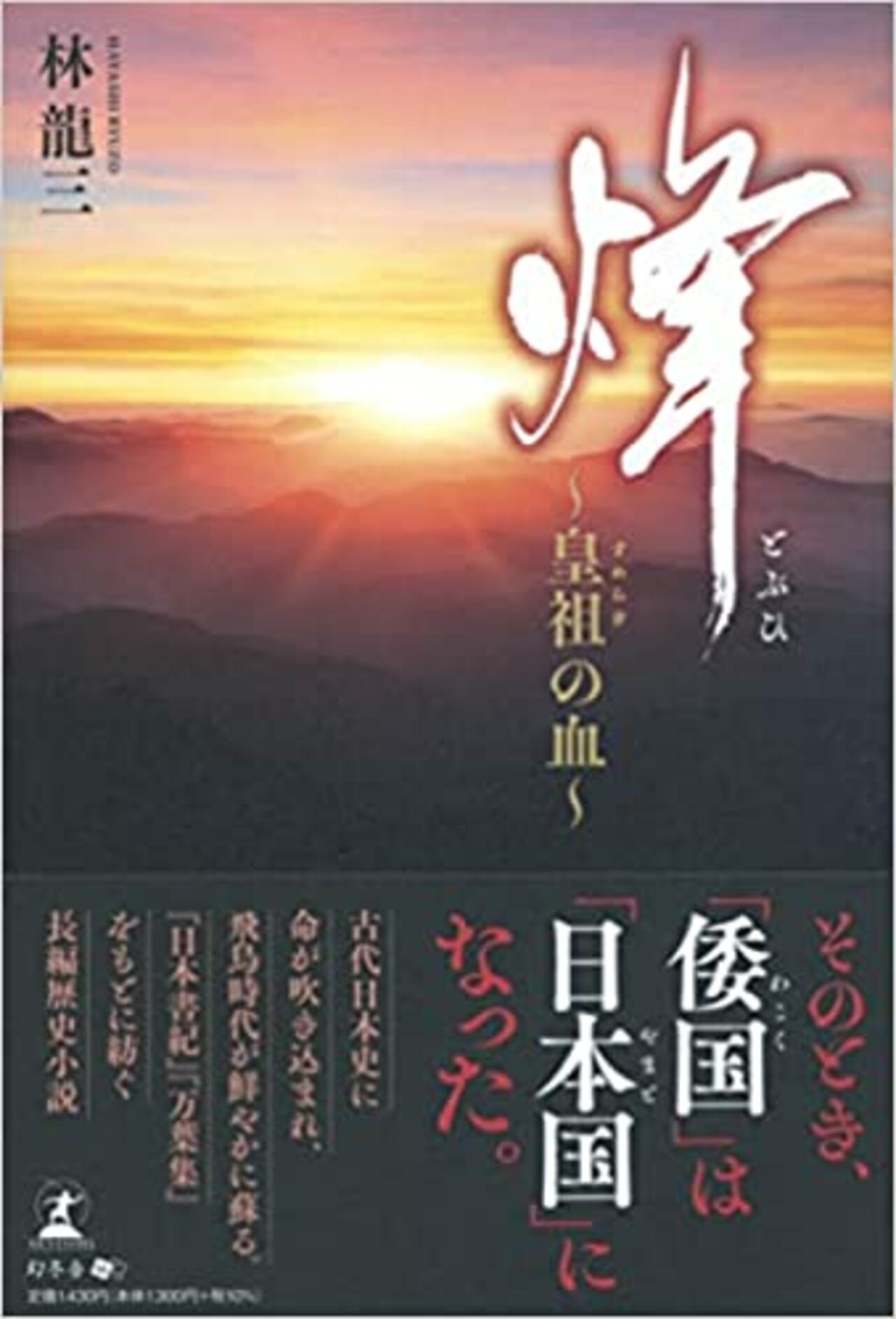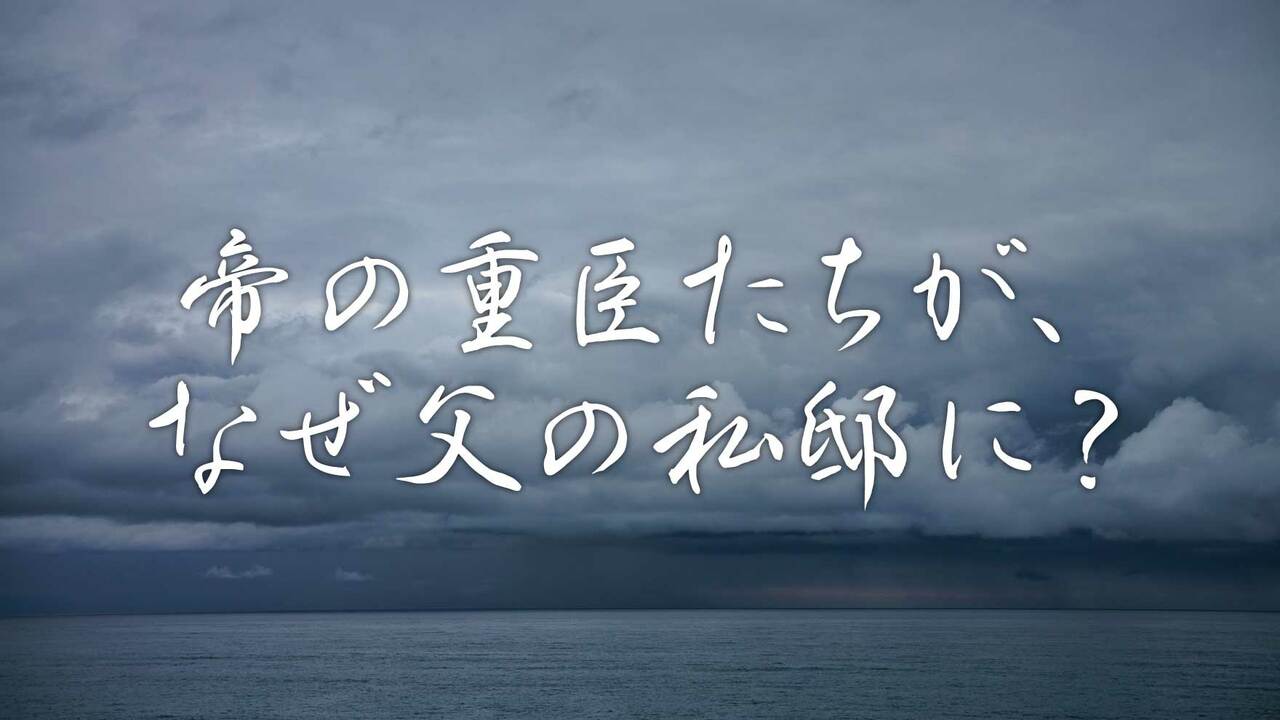石川麻呂はその声に怯んだように入鹿の方を見た。いや、正確には入鹿の背後に迫った二人の刺客を見た。その視線に気付いた入鹿は振り向きざまに立ち上がり、二人の剣から逃れた。しかしこの二人を頼りなしとみた中大兄王子が取り上げていた入鹿の剣を抜いて躍り出た。
「やあ!」と言うかけ声と共に、入鹿の頭に剣を振り下ろした。入鹿はとっさに牙笏を構えたが受けきれず冠が飛び、血しぶきが散った。更に肩を斬りつけると、今度は子麻呂が入鹿の足を斬った。沓が脱げて入鹿は御座の下に転げ落ちた。列席の一同も大いに驚いて立ち騒ぐ。
「こ、これは大王の御前である。我に何の罪があると言うのか。わ、訳を申せ」と、額から血を流しながら入鹿が叫んだ。
御簾の内の大王も突然の変事に驚いて中大兄に問うた。
「王子よ、これは一体何事か」
中大兄は一旦入鹿の剣を置いて平伏し、「入鹿は王子たちを皆滅ぼして大王を脅かし、自らをもって大王に代わらんと欲しております。入鹿をもって大王に成せましょうか」と言った。
入鹿はそれを聞いて、何と愚かなと思った。
「我はその如き罪を識らず……」
裂けた袍からどくどくと血が滴っていたが、これだけは言わねばと、残る力を振り絞って大王の前に平伏した。口が僅かに開いたが、もはや声にはならなかった。我は臣としてこの国と大王を第一に支えてきたものを……。視界が闇に閉ざされた。
大王が殿舎の中に駆け入るのを見届けて、子麻呂と網田は入鹿に止めを刺し、首を挙げた。
この惨劇を目の当たりにして最も慄いたのは古人大兄王子であったろう。取り乱して中大兄に詰め寄ろうとしたところを隣に座っていた軽王子に、「落ち着きなされよ」と、たしなめられた。軽王子も知っていたのだと古人大兄もわかった。そういえば阿倍内麻呂を始め、列席の重臣たちの中にもこの騒ぎにまったく動ぜず、泰然としていた者が何人もいた。
このあと、間違いなく蝦夷も殺される。いや、もう既に討手が回っているかもしれぬ。そうなれば後ろ盾を失った自分はどうなるのか。大王の座どころか命さえも危うい。
この場で斬られるかもしれぬと怖れた古人大兄は軽王子が止めるのも聞かず門に向かって駆け出した。雨が降り始めていた。やっとたどり着いた通門は閉じられており、武装した兵に遮られた。どこからか乱闘の叫び声が聞こえた。おそらく入鹿の近侍たちも一人残らず討ち取られているのであろう。
「王子はお通し申せ」
中臣鎌子の声である。振り返ると胸元に返り血を浴びた鎌子が立っていた。古人大兄は自邸に逃げ帰り、固く門を閉ざした。