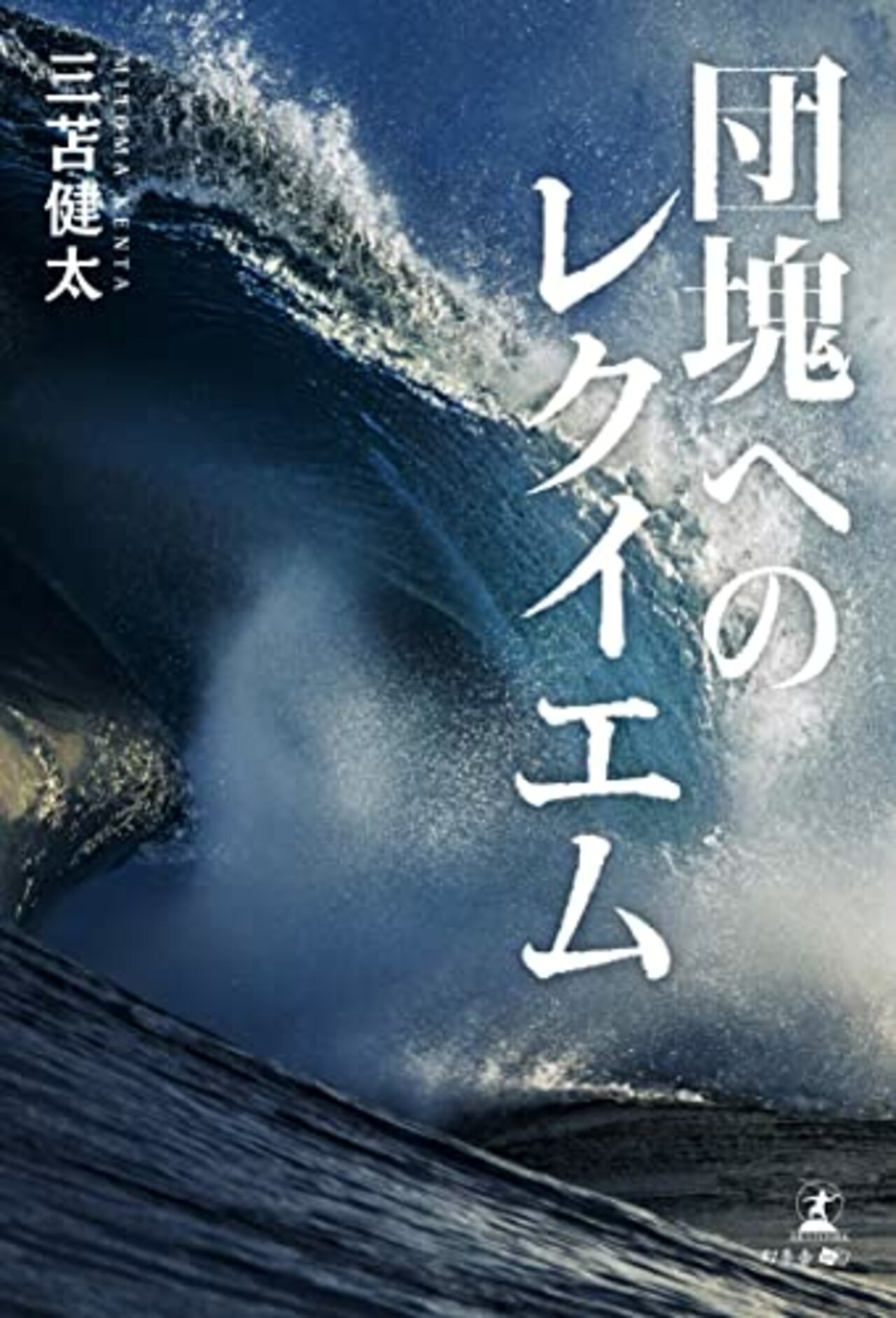同じ世代の親たちが一時期に転入してくれば、子どもたちの世代はさらに凝集したものになる。いわゆる団塊ジュニアと呼ばれる世代で、アパートひとつの棟に同学年の子どもが三人も四人もいるありさまだった。左沢の棟にも秋元佑太と水沼真一という同学年の男の子がいた。
同じ棟に居住するというだけで、子ども心には同族的仲間意識が芽生えるようで、小学生時代の左沢は、いつも佑太と真一の三人で日が暮れるまで遊んだ。その頃から流行りだしたテレビゲーム、公園でのキャッチボールにサッカー、後背地に広がる山林の探検、ときには電車に乗って渋谷や銀座にも出かけた。
リーダー格は佑太だった。その日の遊びも、行く先も、それぞれの役割も、佑太が提案し、左沢と真一はそれに異を唱えることはなかった。佑太は三人のなかでいちばん体が大きかったが、ふたりが彼に一目置いたのはそのせいだけではない。佑太はめっぽう喧嘩が強かった。
団地にはいくつものグループができていた。友好的なグループ、反目するグループなど、グループ同士の関係はさまざまだった。団地には公園や球技場などの共用の広場がいくつか設けられていたが、この広場の取り合いが喧嘩のほとんどの原因になった。反目するグループとぶつかれば間違いなく口論になった。ときとして、罵り合いになり、取っ組み合いに発展した。口論に取っ組み合い、佑太はふたつとも強かった。
「広場はみんなのものだ。みんなで使うのが当たり前じゃないか」
佑太はつねに正論を吐いた。反論できない相手は罵声を返すより他なかった。彼は罵声には罵声を返した。
「ざけんなよ、このアホ」。眉を吊り上げ目の玉をひんむいて怒鳴る彼の罵声は大きく、相手を怯ませるに十分で、諍いのほとんどはここで終わった。ときとして取っ組み合いに発展しても、相手を柔道の腰車か出足払いで地面に転がし臀部に蹴りを入れれば、たいがいの子は戦意を失くした。
中学生になると、運動が得意な佑太はサッカー部に入部し、左沢と真一は学習塾に通いだし、三人一緒に過ごす時間は少なくなった。
左沢の子ども時代は、このように何の変哲もないありふれたものだった。あのおぞましい事件が起きるまでは……。
左沢は首を振り大きく息を吸った。電車は多摩川の鉄橋に差しかかっていた。強い朝の光を浴びて水面がまぶしく照り、河川敷の草木にはまだ秋の気配は微塵もない。記録ずくめの酷暑だった二〇一〇年の夏の余勢がまだ残っている。
電車は信号待ちを繰り返しながら調布駅に入構した。どっと通勤客が乗り込んできて、車両はすぐにお決まりのすし詰め状態になった。発車すると、慣性で入り口近くの人の塊が中央に向かって押し込まれてくる。この力には抗えない。左沢は、吊り革から手が離れそうになり、慌てて握り直した。