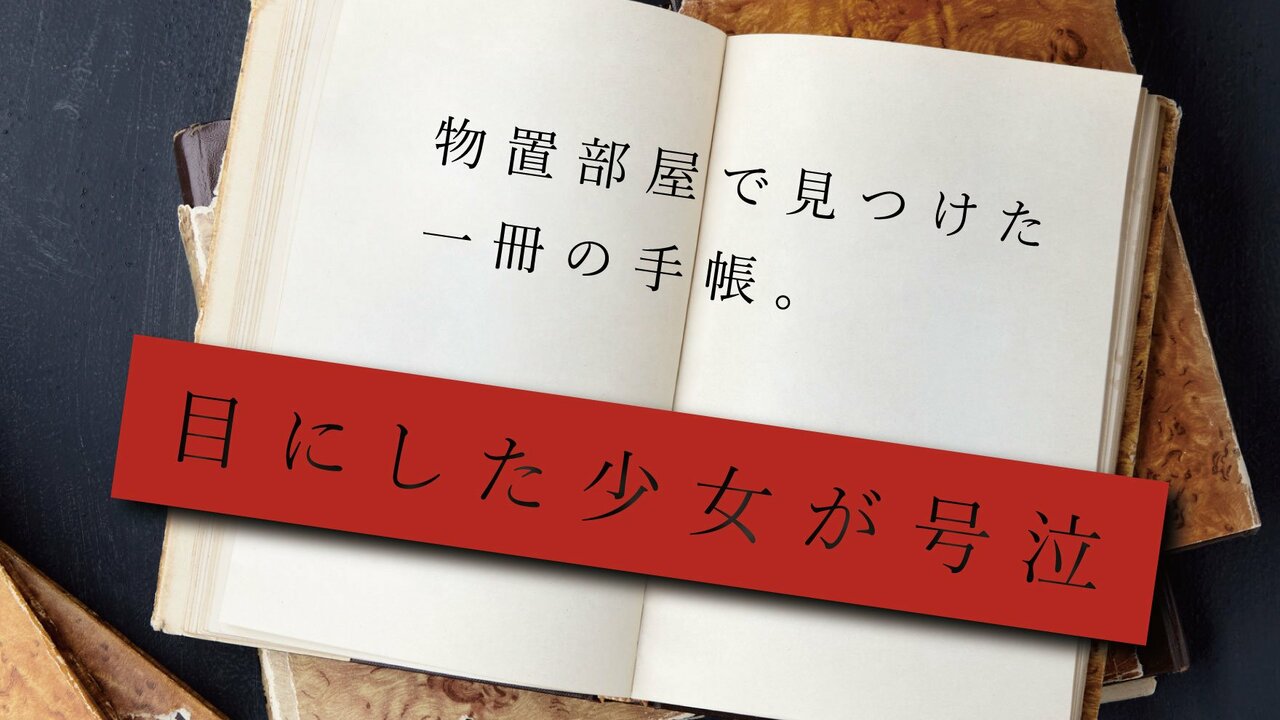ハッと安堵の顔を作って立ち上がった瞬間、松の木の太い枝がゴツンッと私の脳天を強打した。
「いったーい!」
よろけながら、私の視界がとらえたのは、フラフラと蛇行するお父さんの単車だった。私は頭の痛みを忘れて、ドキンッと心臓を鳴らせた。そして、ありったけの大声でお母さんを呼んだ。
「お母さーん、早く来てー! お父さんが、なんかへーん! 酔っぱろうとるみたい!」
私のただならぬ呼びかけに、お母さんに加えて、おばあちゃんも急ぎ足で出てきた。皆が見守る中、単車がヨタヨタと家の前の坂を登りきって止まった。ヘルメットを外したお父さんの顔面を見て、その場にいた誰もが顔を歪めた。まるで乱打戦を戦い切ったボクサーのように、頬も額も瞼も鼻も、顔中が真っ赤に染まり、パンパンに腫れ上がっていたのだ。
話を聞くと、ヘルメットに取り付けたネットと首の間にできた僅かな隙間から、何匹ものアシナガバチが侵入してきて、命がけでお父さんの顔面に針を突き刺してきた、ということだった。私はお父さんの顔面を見るのがおっかなくて、顔を背けた。
「幸久、今すぐ病院行きなはい!」
「幸久さん、救急車呼んだ方がええんやない?」
おばあちゃんもお母さんも強く病院に行くように勧めたが、お父さんは缶ビールを片手に、
「酒が一番の薬やけん。これ以上効く薬はないんやけん」
と言って聞かなかった。プッシューッと缶の蓋が勢いよく開かれる音と、ゴクゴクとビールが体内に流し込まれる音が聞こえてきた。
これだけボコボコに蜂に刺されても命に別条はなかったが、それ以来、お父さんの頬や額、瞼や鼻までもが、ボヨンと腫れて膨らんだままになったのだった。
どれだけ飲んでも酒があるうちはよかった。お父さんは、愉快になり、饒舌になり、自分で言ったことにガッハッハッと大声を上げて笑った。家に友人や親戚を招いて飲んでいる時には、その愉快ぶり、饒舌ぶりに拍車がかかった。お父さんの発した一言でその場の一同がドッと笑い、築五十年の木造家屋が、亀裂が入らないかと心配になるくらいミシッと揺れた。
そのおかげで、お父さんには飲み友達が大勢いたが、その中でも特に仲がよかったのが、鱒下のおっちゃんだった。二人で浴びるように酒を飲んでは、二人でデロンデロンの上機嫌になり、そんな二人の笑い声は、やまびこ山にも轟くほどの大音量で、明け方まで響き続けていた。