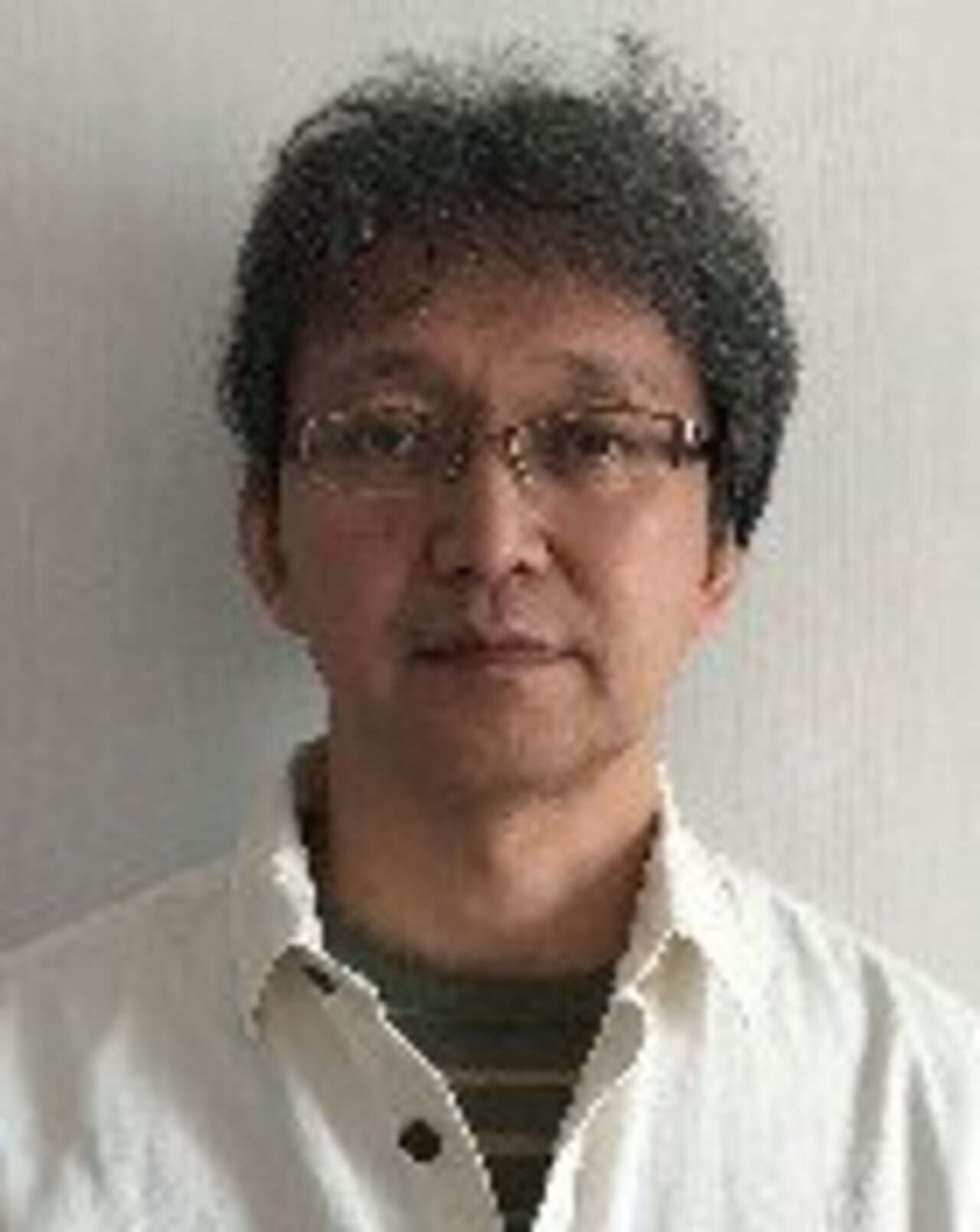ただ、「この分量で本当に九十分繫ぐことができるのだろうか」。そう思ったちょうどそのタイミングだった。
「私がバーチャル聴講者になってあげようか」
和枝が申し出てくれたのだ。実際にやってみるとボロボロだった。原稿は頭に入っていたので、廉はメモを一切見ずに喋っているのだが、それにもかかわらず、和枝からするとほぼ棒読みしているように聞こえた。そこからの「書き言葉の世界」を「話し言葉の世界」に変換させる作業は甘くはなかった。
「面白いエピソードがいっぱいあるのに……。もったいないよ、その話し方じゃ。内容はいいんだけど原稿そのものが硬いのね。それを『そのまんま暗記してお伝えしてます』っていう感じがありありなのよ」
「じゃあ、どうすりゃいいんだよ」
「ほらすぐに怒らない。新聞講座を受けたいっていう人たちだから、町内会報とか地域の情報誌とかを実際に作っていて、新聞に詳しい人が多いかもしれないよね。だけど私みたいに予備知識の無い人だって半分くらいはいるわよ、きっと。そしたらどちらのタイプの人たちにも関心を持ってもらえるように話さなくちゃ。『きょうの回はハズレだったね』って彼女たちが帰るようなことになったら、廉がかわいそうだもん」
そんな風になだめながら、廉の語りの難解さや不自然さを、ワンセンテンスずつほぐしていった。
遥のピアノの師である白銀彩先生からベルギーのチョコレートメーカーのアイスセットが届いた。箱を開けた和枝が突然泣き崩れた。
「平林先生へ応援団より」という手紙がアイスの上に載っていたのだった。先生同士でつくる連弾研究会のメンバーからのメッセージを、白銀先生が寄せ書きのレターにしてくれていた。和枝も名を連ねる会だった。
「アイスクリーム」。
何と幸せな響きだろう。和枝の病が分かってからは口にしていなかった。コンビニにでも立ち寄ればいつだって買える身近な幸せ。でも目に留まらなくなった。食べたいという感覚も抜け落ちていた。
きっかけは何でもいい。この非常事態の中でも以前の生活感の片鱗を取り戻すことができる、すがれるような解決策がほしい。そんなものはあるわけがないが、そう思い続けて廉は日々を過ごしている。でも和枝はこのごろよく言う。
「なるようにしかならないんだよ。なるようにしかね」
決して悲観しているのではない。和枝はとにかくしっかり生きているのだ。和枝、二クール目の治療に向け八月二十四日に再入院した。