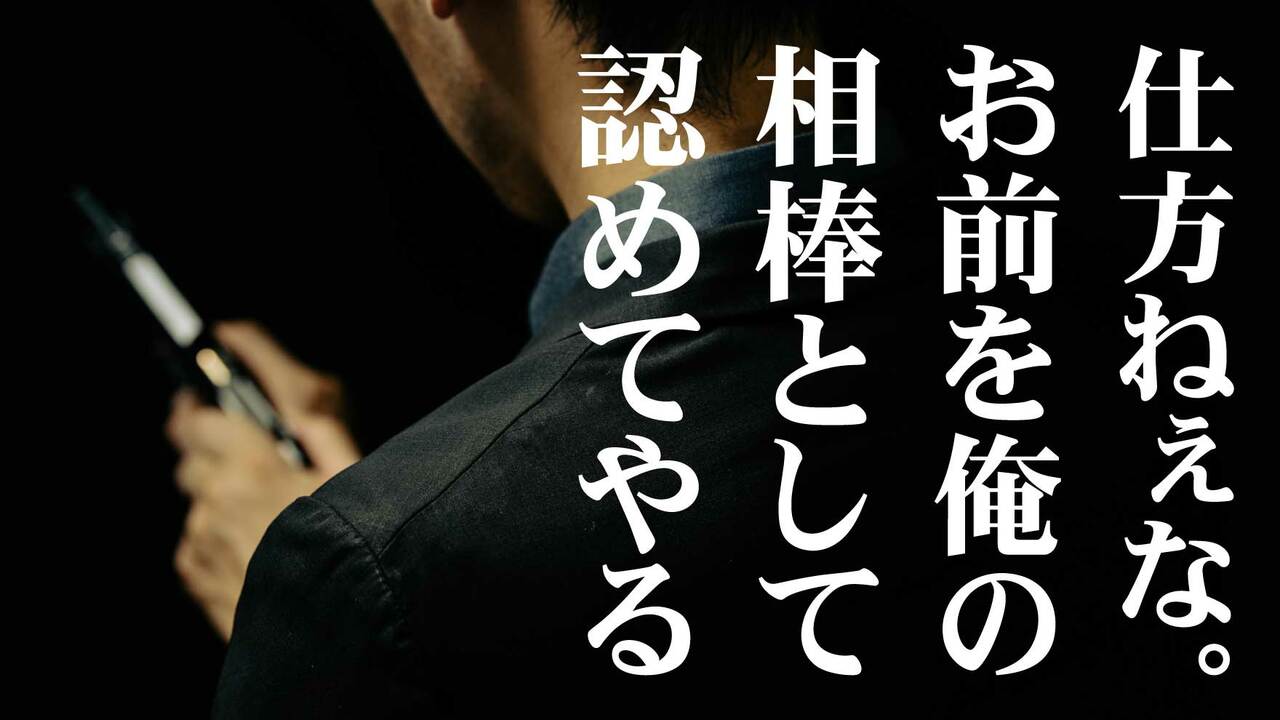【前回の記事を読む】弟を殺された少女。死神の悲痛の声を聞き、何も言えなくなった
第二章 恭子
庭に出てからも、彼女はしばらくバッタを見つめていた。
私が捕まえなければ、このバッタはまだ生きていたのかもしれない。
草むらで、楽しく飛び跳ねていたかもしれない。
次第に罪悪感に襲われ、目頭が熱くなる。
少女は片手で目を覆い、声を上げて泣き出した。
「おやおや、どうしたね。恭子」
縁側から、祖母が声をかけてきた。庭に降り、少女の元へと近付く。
「バッタさんが……、ヒッ、あたし、ヒッ、あたしバッタさんを殺しちゃった……ヒッ……」
彼女は嗚咽しながら言い、動かなくなったバッタを乗せた掌を差し出す。
祖母は小さな掌に乗ったバッタを見つめ、
「おやまぁ……」
と、呟いた。
祖母は恭子の前に来てしゃがみ、掌を恭子の頭に乗せ、まだ嗚咽している孫の頭を優しく擦る。
「恭子……」
頭を擦りながら、優しい声を掛ける。
「命というんはなぁ……限りがあるんじゃあ……。この世の全ての生き物には『命』というもんが宿っとる……。命とは魂じゃあ。身体から魂が抜けてしまうと、生き物はなぁ……死んでしまうんじゃ……。悲しいが、それがその生き物の寿命というもんじゃあ……。いつ寿命が来るかは、神様しか分からん。そのバッタも寿命を迎えたんじゃ……。しかし『人』はその『命』を奪う力を持っている事を忘れちゃならんぞ、恭子……」
祖母の優しい言葉を聞きながらも、嗚咽は止まらなかった。バッタの魂を奪ったのはやっぱり自分ではないのかという疑念が拭いきれなかったからだ。
祖母はそんな恭子が泣き止むまで、頭を撫で続けていた。