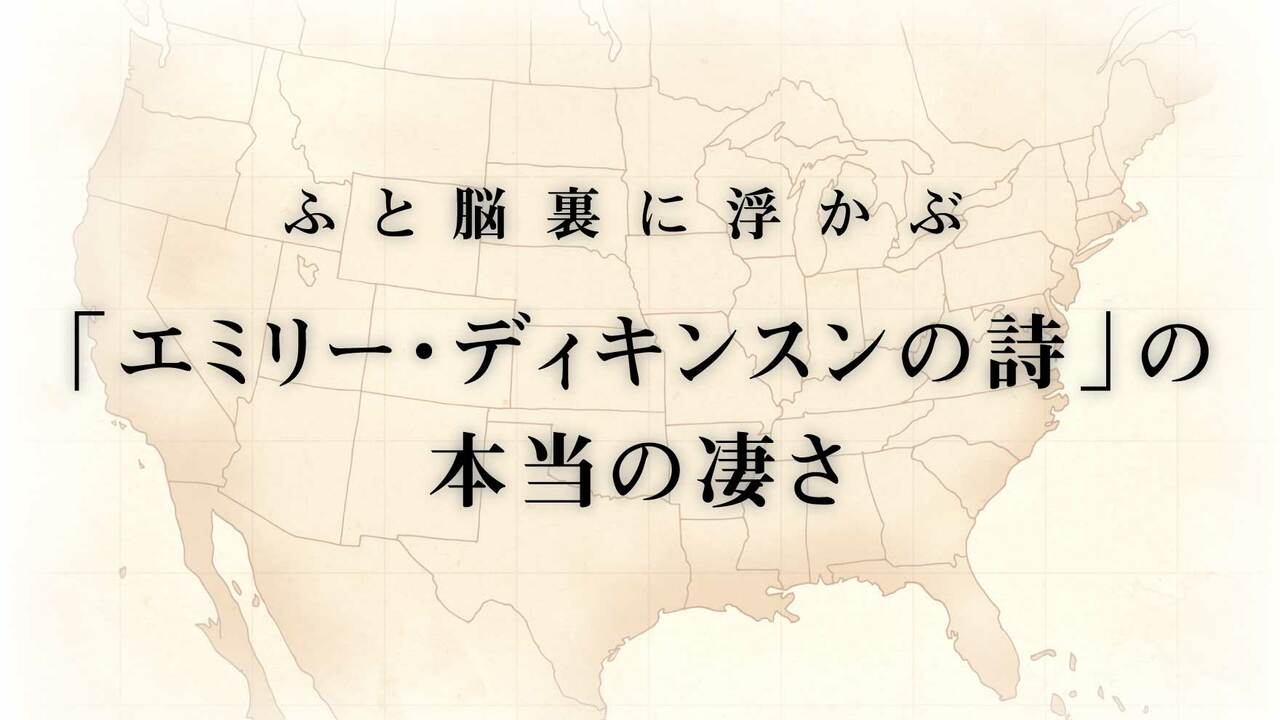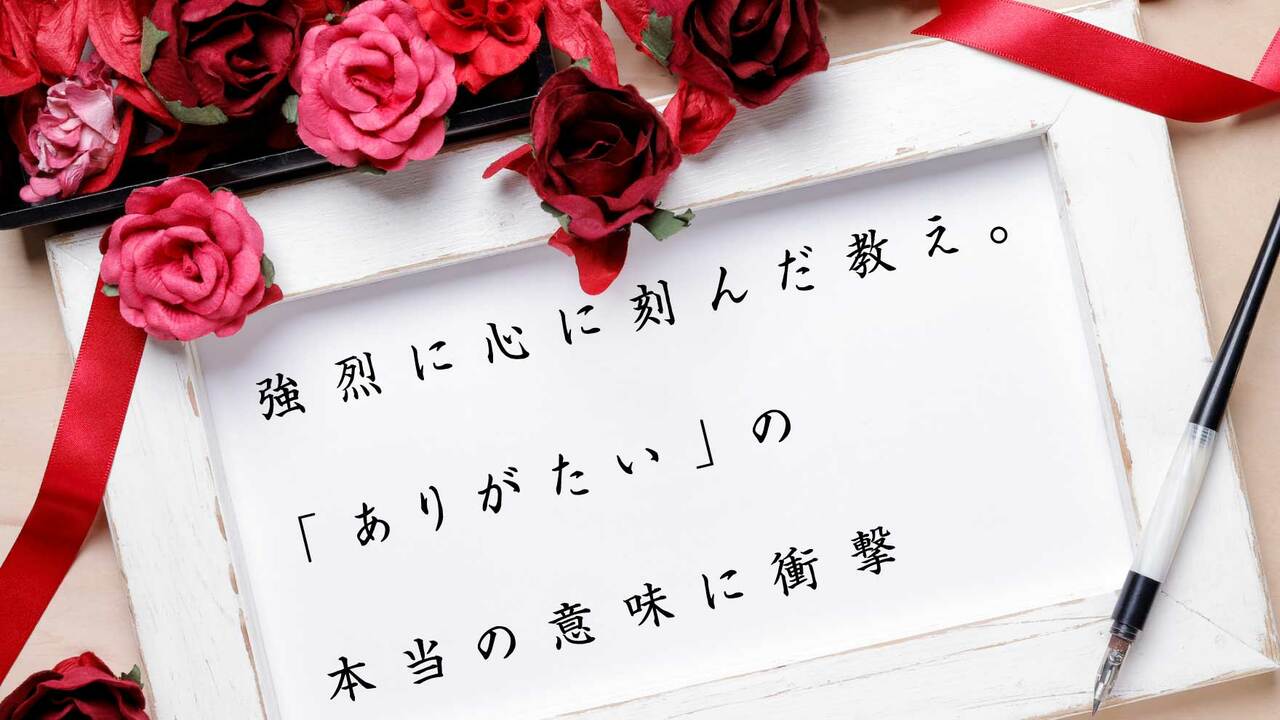まだ老木の花もあるのだけれど……
ところで世阿弥は「老木の花」ということも言っている。そして『老女もの』と呼ばれる演目を能の至高のものとしている。とすれば「時分の花」を思うにはもう遅すぎるけれど、まだ「老木の花」を求めていく道は残されているかもしれないと、かすかに希望をつなげたのだが……世阿弥はそうは甘くない。じつは老木に花が咲くということは、二十代三十代、それぞれの年代に確実に花が咲いていなければならないと言っているのだという。そうでなければ老木に花は残っていないということだと教えられた。世阿弥という人はずいぶんと冷徹な鋭い人らしい。少なくとも甘くはない、としか思えない。
さて私の場合「老木の花」が残るかどうかは大問題だ。二十代三十代に花が咲いていたかどうかも定かではないのだ。それなのに、そこに「老木の花」が残っているかどうか、またそこに私の「まことの花」が咲いているかどうか、この先もじつに険しい道が待っている。
毬の中での生成
この「毬の中での生成」という言葉はエミリー・ディキンスン(一八三〇~一八八六年)の詩の一節である。
格別詩が好きということはないのだが、ときどき、ふと脳裏に浮かぶことのある詩は幾篇かある。このエミリー・ディキンスンの詩もその一つだ。どういうときに思い出すのか考えたことはなかったのだが、今回「時分の花まことの花」を書いているうちに、そうだ、エミリー・ディキンスンが言っているのは「時分の花まことの花」と同じような感覚だと感じた。そういえば私がこの詩を思い出すときも、もしかして「魂の成熟」というようなことを考えているときなのかもしれないと思った。
短い詩なのだが、全部はこうである。
熟することにも二通りあって、一つは目にみえます
天がその力を蓄えさせ
やがてビロードの柔らかさの賜物が
地上へと薫りだかに落ちるのです
もうひとつはずっと質素です
毬の中での生成─
はるか先 十月の大気に包まれ
霜のもつ歯だけが暴く成熟です
中学や高校生のころは私も詩や短歌が好きだった。幾篇も好きな詩を暗誦したりした時期もあった。だが次第に詩のもつ繊細さや鋭く感覚的なところが自分には向いていないと思うようになった。私の本性はもっと粗野で繊細さに欠ける、だからもっと強く、たくましいものが好き、と感じるようになって、次第に詩から離れていった。卒論も小説を選んだ。だが詩が嫌いなわけではないのだろうと思う。
とくにエミリー・ディキンスンの愛読者というわけでもないのだが、たまたま手にした彼女の詩集のなかで見つけたこの詩だけが何故だか心に残り、何かの折にふっと蘇ってくる、というだけなのだ。第一、エミリー・ディキンスンは文学史上では有名な詩人だが、一般的な意味では格別人口に膾炙している詩人とは言えない。