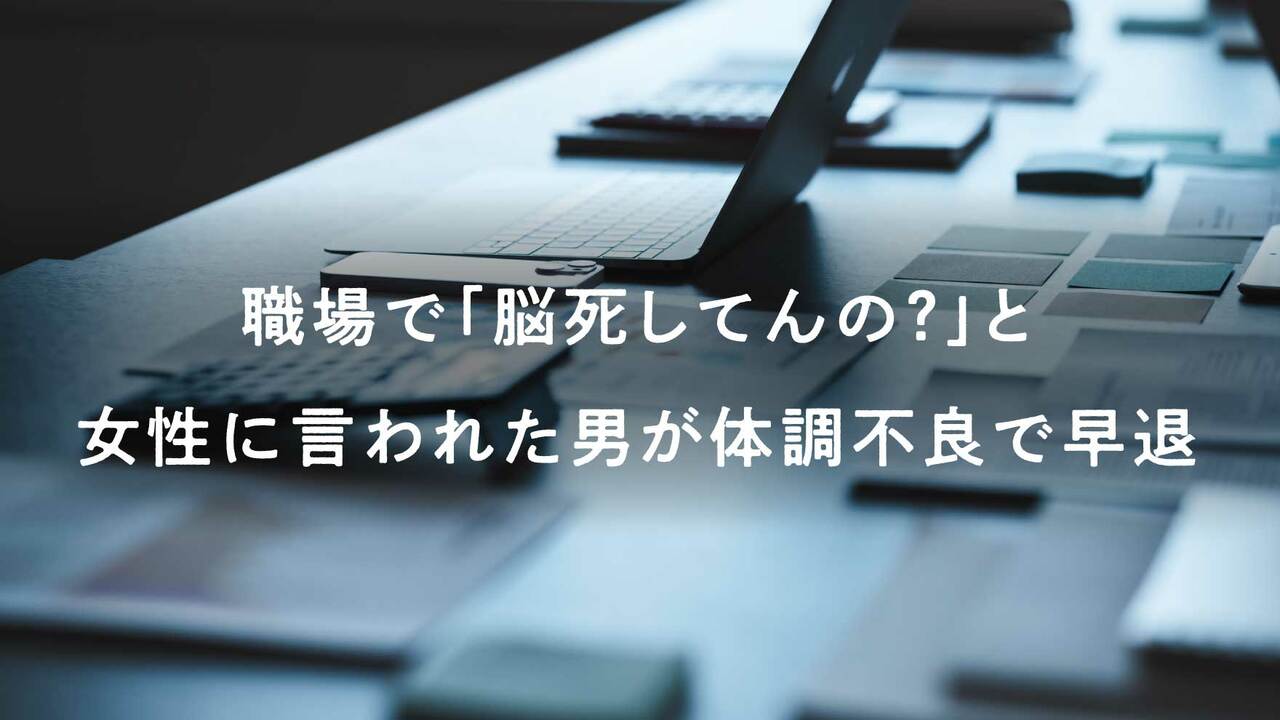お絵描きが好きな私は祖父が飼っているトイプードルのチェリーをダイニングテーブルに座らせて何時間も描写し続ける。祖父母や両親に絵が上手だと褒められるのが心地良く、同じ絵を繰り返し描き、チェリーはその間じっと動かない利口な犬だった。
絵を描くだけでなく漫画を読むのも好きで、月刊少女マンガ誌を三冊ほど購読し続けている。お気に入りのマンガの連載が終わる頃になると、友達とのお別れが来たかのように寂しく感じた。この瞬間が一番キライでどうにか払拭しようと思いついたのが、自分が漫画家になるという選択であった。
「自分で物語を描けば、主人公の言動すべてが自分の意志のまま操れる。永遠にストーリーを書き続ければ誰ともお別れはこないし寂しくもならない。よし、漫画を描こう!」
それからというもの裏紙を使っては漫画を描いた。来る日も来る日も部屋に籠って足の踏み場が無くなるほど、原稿用紙やスクリーントーンの切れ端を部屋中いっぱいに巻き散らしていた。たまに母が私の部屋を綺麗に掃除すると、Gペンや丸ペンの置き場所が分からなくなり文句を言った。
ご飯も食べずに制作に没頭する様子を見ていた父は、自分自身がいわゆる「お固い職業」についていたため、芸術方面に興味を持っている娘のことを大変喜び、漫画家になる夢を応援してくれた。
父は古本屋であだち充、北条司、大和和紀、和田慎二など一昔前の漫画を買って来てくれるので、制作の合間にそれを読んだ。私のお気に入りはキャッツアイとスケバン刑事。そのせいか悪い敵から家族の身を守る設定の空想で遊ぶのが好きな、正義感の強い女の子に育った。
一度だけ漫画を描いて応募してみたことがあったが受賞することはなく、端っこの応募者欄に小さく自分のペンネームが載っているのを呆然と眺めた。
ストーリーを練り、トーンを貼り、毎晩遅くまで頑張ったにもかかわらず期待していた結果が得られなかった。それまで応援し続けてくれた両親のことを思うと、途端に恥ずかしくなる。蝋燭の火がしゅんと消えるように、胸の中にあった情熱も意欲も静かに消滅した。それ以降、漫画を描くことはなくなった。