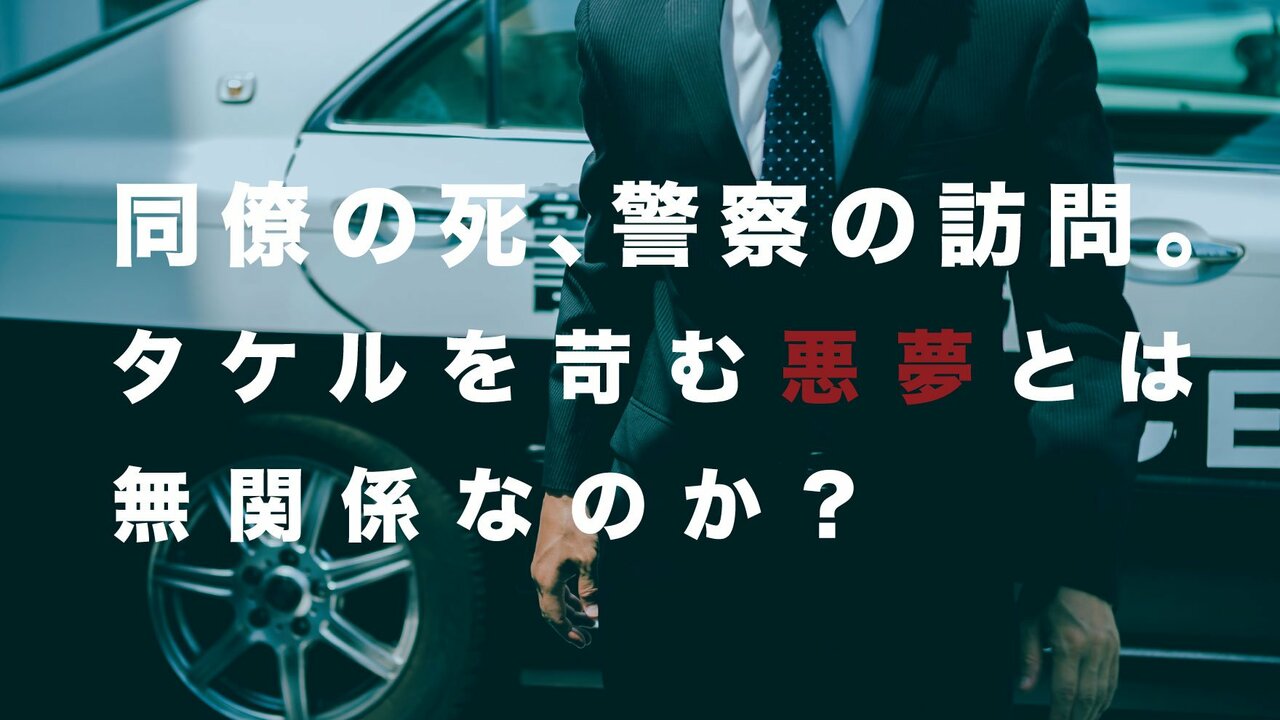双頭の鷲は啼いたか
タケルは仕事場にいた。なんとなく自分をごまかして今まで来たけれど、事故と今の自分の精神状態の因果関係を早く明確にしたかった。大事なことから目をそらしてはいけない。それがどんなに辛い現実だったとしても。本当の自分を取り戻せるのならば。
タケルは表面上は取り繕って日々を過ごしていたが、内面はかなり追い詰められてしんどかった。生徒たちが来るにはまだ時間があった。タケルは母親に電話した。幸い仕事中ではなかったようだった。
「母さん、仕事中にごめん。今いいかな?」
久しぶりに聞く母の声だった。
「休憩中よ、どうしたの」
「最近頭痛や不眠できついんだ、毎日」
「いつから?」
厳しい口調に変わった。
「ここ三週間ほど」
悪夢の事はさすがに電話で言える内容ではない。
「もっと早く言いなさい。辛かったでしょう? ちゃんと食べてないんじゃない。行こうか、そちらへ。事故の後遺症かな。今頃?」
母はあの事故以来、タケルの郷里・神戸から長い休みが取れるとやって来た。
「だろうか」
「すぐに、病院に行きなさい。鴻池第一病院よ。事故の相手はその病院の病院長の息子だから、全額負担の申し出があったわ。事務長の人から名刺もらってあるから、電話をしておくわ」
看護師の母親は厳しい人だった。が、その判断は的確でいつも迅速だった。
「高次脳機能障害だろうか。些細なことでイライラしたり、キレたりするんだ」
「時間が過ぎてから出てくるから、そうかもしれないわね」
母は大きなため息をついた。タケルも沈黙し、一言絞り出した。やはり悪夢の事は言えない。
「この辛い毎日がもう、限界なんだ」
「早く受診しなさい。一緒に行こうか?」
「子供じゃないから、大丈夫」
「じゃあ、気を付けて。結果を知らせて」
母は沈んだ声で言った。
電話を切ったタケルはフロアの電気を点けた。掃除を始めると秋元さんが出社した。相変わらず元気がない。辞めるのではないかと心配していた。
「おはようございます、元気だして」
「頭では分かっているのですが、なんだか怖くて」
秋元さんの目は虚ろで、いつものはつらつとした感じは消えていた。
「うん、そうですね。僕だってカラ元気だから」
タケルは個人的に問題を抱えていたので、心の中ではざわつきは大きいと思った。わざと繕う笑顔さえ今のタケルにはきつかった。なんで、自分だけがと。
彼女は気持ちを取り直そうと、書類を整理し始めた。事務職が一人減ったので仕事は山のようにあった。二人では電話も取り切れなかった。三人いた時もこんな感じではあったが。
それでも授業の時間はあっという間に過ぎた。もう夜の九時が過ぎて生徒はいなくなった。
「お疲れさま、君たちももう遅いので帰りなさい。明日に回して」
タケルはまだ残っている男性の講師達に声をかけた。
「チーフ、あと二枚だけ報告書、書かせてください。来週まで来ないので」
指導報告書を書いている男子大学生が二人ほどいた。彼らは三回生でベテラン講師だが、就活で三月からいなくなる。就職が希望のところに決まればいいなとタケルは優しい気持ちになった。自分のような思いをしてほしくないと思ったからだ。でも彼らは指導力があったのでいなくなると厳しいし、親しかったので寂しくなる。