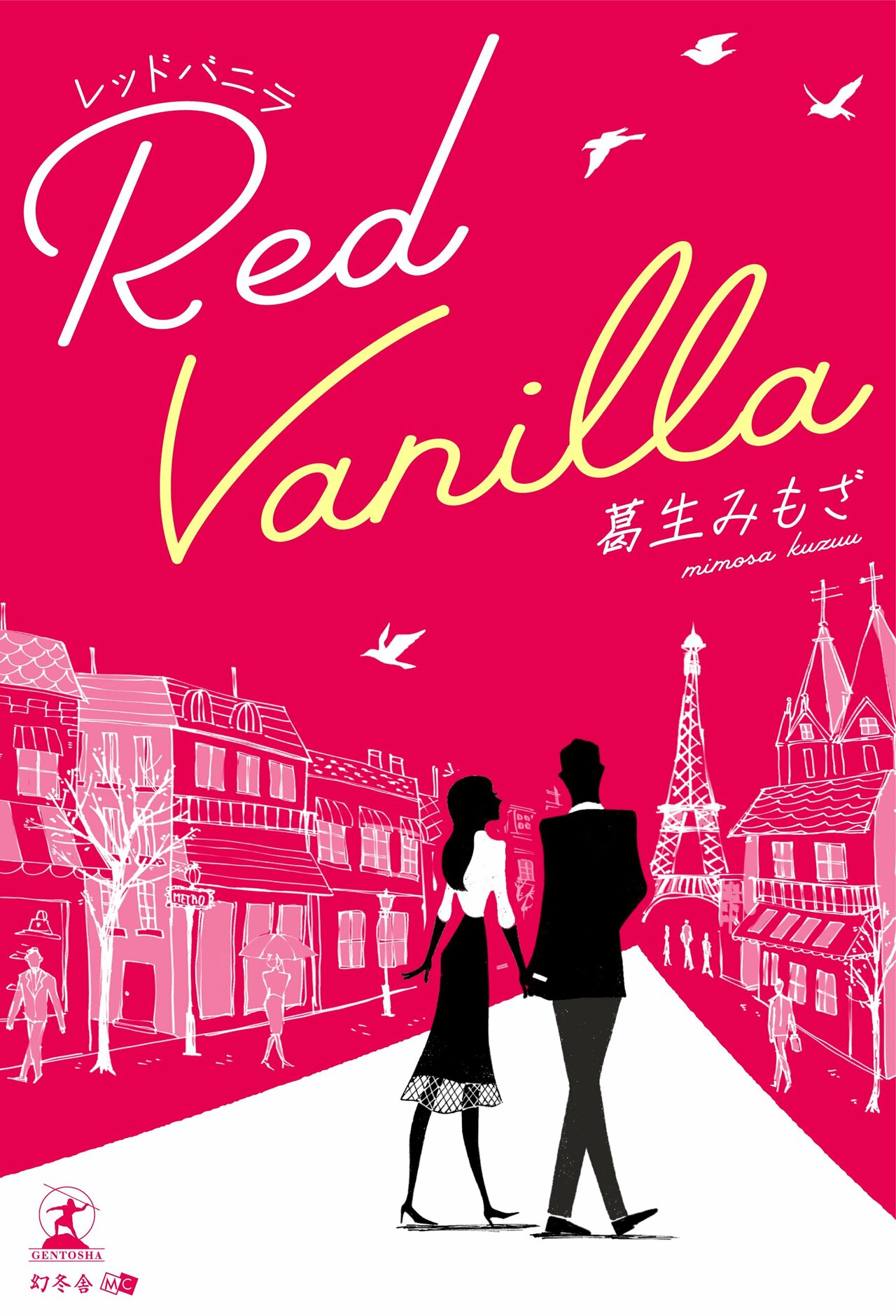しかし、約束はしたものの結局は行かなかった。ストラスブールではぐれたボーイフレンドが無事にホテルに戻ってきてくれたのだった。
しかも私に置き去りにされたと思い込んだ彼は機嫌が悪かった。私は東駅で一時間以上待っていたこと、とても心配したことなどを説明し、彼の誤解を解くために一生懸命話すと同時に彼の言い分も聞かなければならず、そんな時間を費やしているうちにムッシュとの約束の時間は過ぎてしまった。
お互いの話を理解し合って、冷静になった彼は疲れたらしくベッドに入った。時計の針は午後十一時四十分を指している。ムッシュが待っているかもしれない。幸いレストランはすぐ近くだ。せめて行かれなくなったことだけでもムッシュに伝えてこようと、部屋を出るために私は小さな嘘をとっさについた。
「フロントが心配しているかもしれないから、ちょっと一階に行ってくるわ。あなたが無事に帰ってきたって伝えてくる。私はフロントでTGVが何時までか聞いたりして迷惑をかけたのよ」
「俺が帰ってきたとき、えりかが帰っているかどうかフロントに聞いたから。大丈夫だよ」
いつものことながら機転の利く彼の返事がちくりと胸を刺したけれど、すでに私はルームキーを持ちながら、部屋の扉を開けて片足は廊下の絨毯を踏んでいた。急いでいけば三分くらいでレストランまで行けるわ。私は走ってヌフ橋の角を曲がったものの、そこで立ちすくんでしまった。昼間ならまもなく見える彼の店も、夜の闇で遙か遠くに感じる。思ったより、距離はあるのかもしれなかった。
しかも彼の店の手前あたりで、ほの暗い舗道の両側にGパン姿の黒人男性が二、三人ずつ立ち話をしながらこちらのほうを見ている。さっきは見かけなかった風景だ。おまけに、夏の終わりで私は短めの白いスカートをはいていて、その男たちの前を通ってレストランまで行く勇気はとてもなかった。
これ以上はどうしようもない。私はあきらめてすぐにホテルに引き返した。アパートメントホテルの前のセーヌ川は優しく夜を流れてゆく。ムッシュとの約束破りが気になったけれど、それは致し方ないことだった。