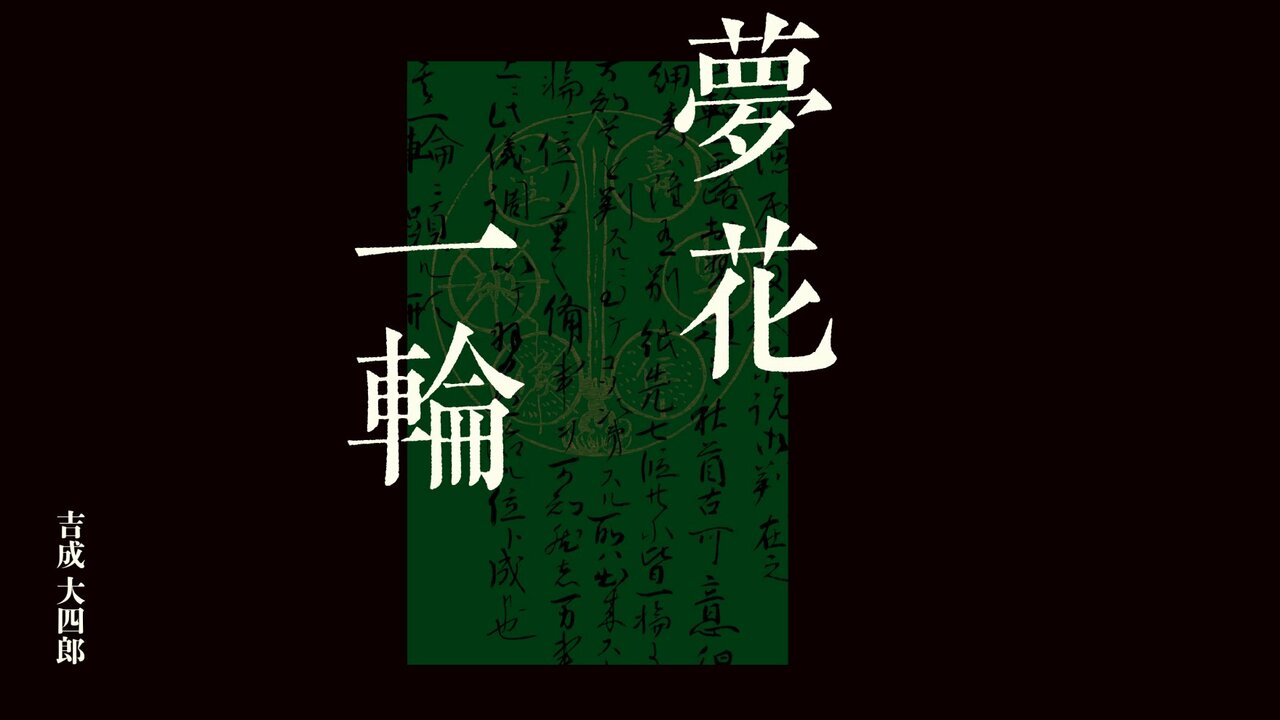第二章
一
「世阿弥様がご出家か、それは祝着申し上げる」
元能の話を聞いて氏信(うじのぶ)は顔をほころばせ、祝いの言葉を述べた。七郎と弥三郎はすでに元服し、それぞれ元能、氏信と名を改めている。
応永二十九年、齢六十を数えた年、世阿弥は出家し観世大夫の座を元雅に譲った。
世阿弥という名乗りは、芸能者に多くある擬似的な法名というべきもので、それまでは俗体であったのを改めて得度(とくど)したのであり、世間の呼び名は変わらず世阿弥のままである。
新しく観世大夫となった十郎元雅は、能芸の道に優れた天分を表し、ことに能作においては数少ないながら目を瞠(みは)るような新作をすでに生み出している。次代の観世大夫として何ら不足はないのだが、一つだけ引っかかるのは三郎元重の存在であった。
元々、世阿弥にはなかなか子が生まれず、半ば諦めをつけるような形で弟四郎の長子を養子にもらい受けたものである。
世阿弥自身の名であった三郎を名乗らせたのも、末は大夫を継がせるという意図のもとになされたことであった。それからほどなくして実の子である十郎が生まれたのは皮肉なことというしかない。
元重もまた才に溢れた者であった。能を作ることはないものの、技の切れは元雅以上、ことに優れているのはその統率力である。
能は為手(して)だけがいくら頑張っても良いものにはならない。脇の大夫、地謡じうたい、囃子や間(あい)の狂言まで、舞台に立つ者が一心に力を合わせて初めて花を咲かせることができるものなのだ。
元雅にその力が足りないということはない。舞台の隅々にまで気を配り、それぞれの役の力を引き出すことのできる、大夫としての立派な力を持っていた。
ただそれ以上に元重はその強い意志で一座の全員をぐいぐい引っ張っていく力があり、それは衆目の一致するところであった。一座の統率者としては、あるいは元重の方が上なのではないか、はっきりと口に出す者はいなかったが、そんな空気が潜んでいることは否定できない事実であった。
とはいえ、世阿弥が定めた以上、それに異を唱える者はいない。元重も不満一つ漏らさず元雅の下につくことを受け入れていた。
しかし、元重に野心がなかったわけではないし、それがすっかり消えたのでもなかった。