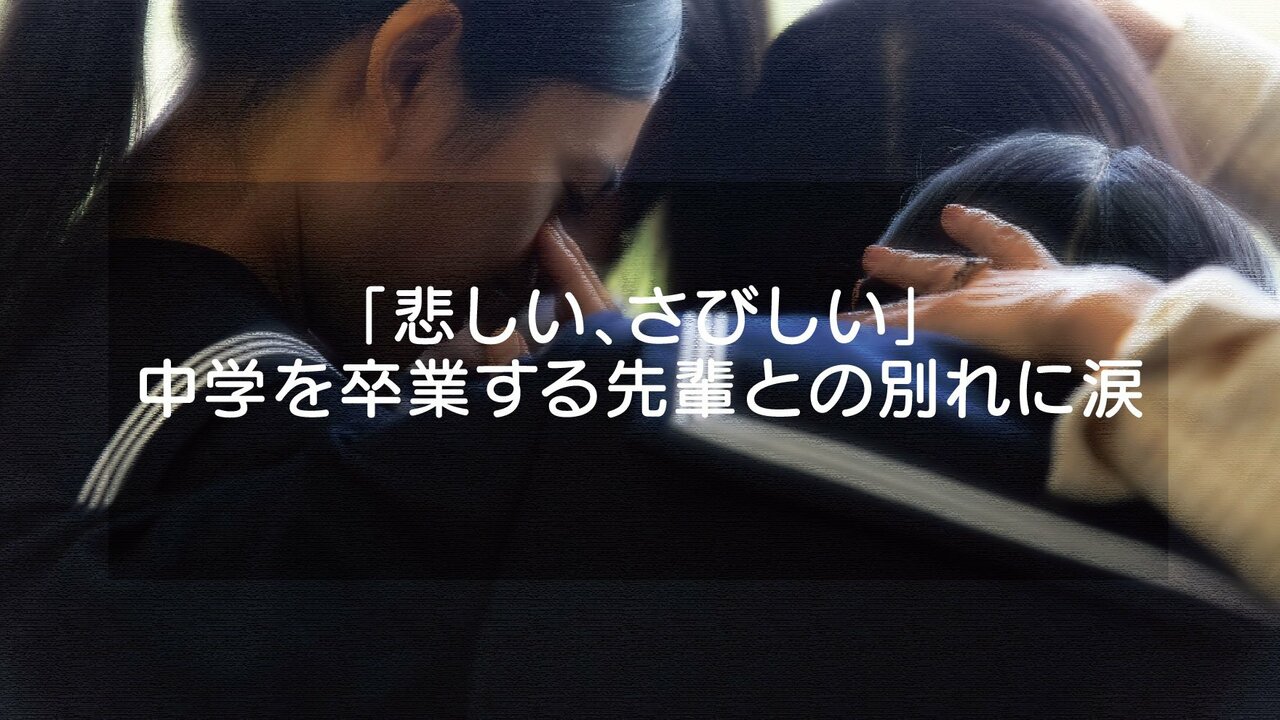どう受け答えをしたらいいかわからず、おずおずとうなずきを返すだけのわたし。
「1-Cの本多(ほんだ)さん、だっけ」
「そ、そうです」
涼しげなショートカットのうなじに手をやりながら、野長瀬さんは
「ふうん」
と言った。人なつこそうな目が、好奇心でいっぱいのネコみたいにきゅっと細くなる。
ちなみに、ソフトボール部期待のホープでもあるらしい野長瀬さんは、わたしよりも頭半分くらい背が高い。自然とわたしが彼女を見あげるかたちになる。
「べつに詮索とかそういうんじゃないんだけどさ、きみって天坂さんの友だちなわけ?」
そこだけは迷いなく
「はい」
と答えると、野長瀬さんは、へえ、と感心するようにあらためてわたしを見た。
「あの……ミュ……彼女、もしかして病気とか……」
「んー、どうかな。先生は、特にそういうこと言ってないね、今のところ。仲のいい人なら聞いてるかもしれないけど。あ、それってきみじゃんか」
野長瀬さんは、なぜか、とっておきのジョークを口にした人のように笑いだした。
「ま、きみが知らないとなると、たぶん、だれもわからないよ。今度出てきたら、それこそ首に鈴でもつけておいたほうがいいんじゃないかな」
「それは……」
やれるものなら、やってみたいです。実際わたしは、こういうときにミュウと連絡を取りあう方法をなにひとつもっていない。
いくら言っても、ミュウはケータイを持ってくれない。一週間音信不通でも、ひたすらやきもきしているだけ。
考えてみると、ずいぶん情けない友だちだった。