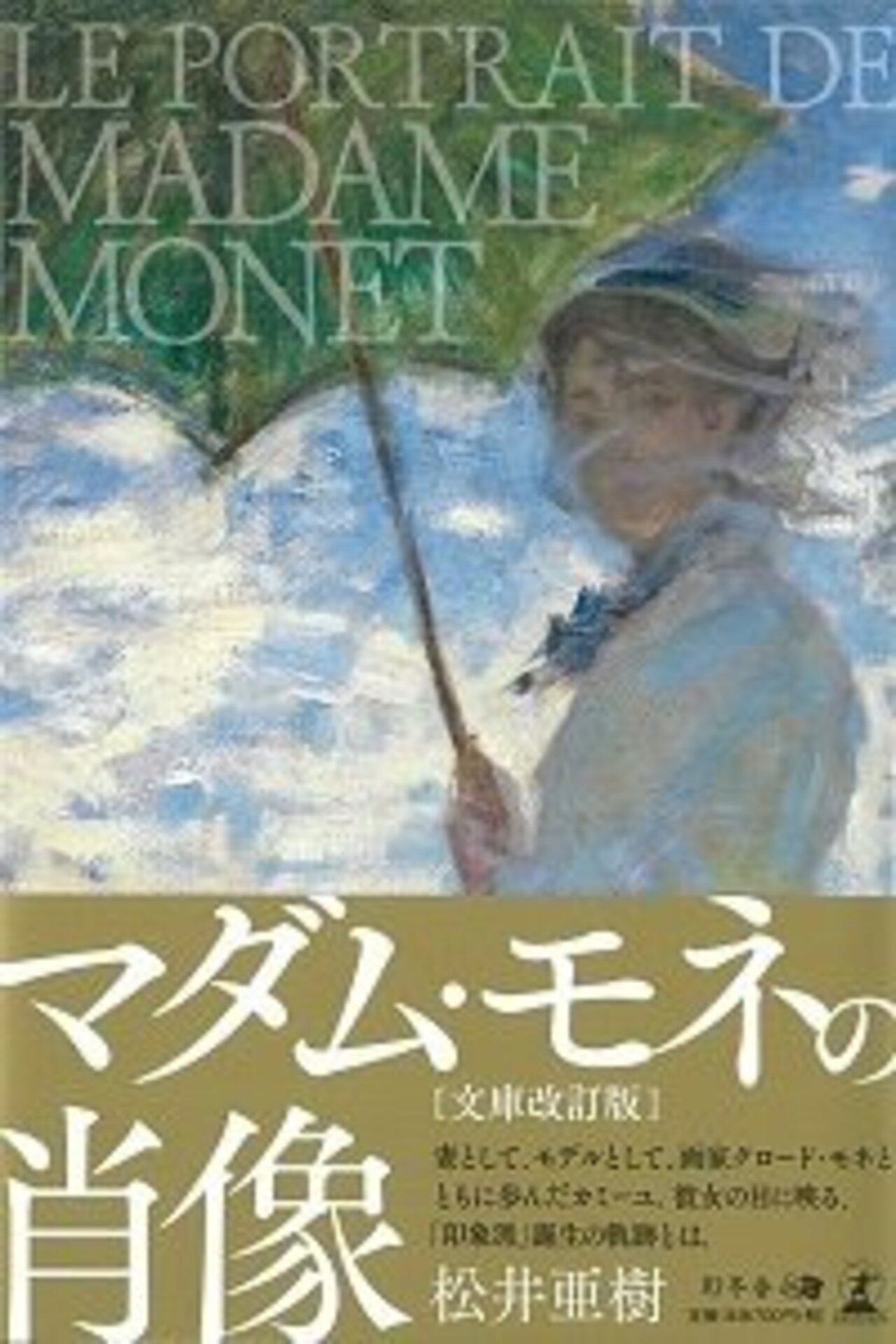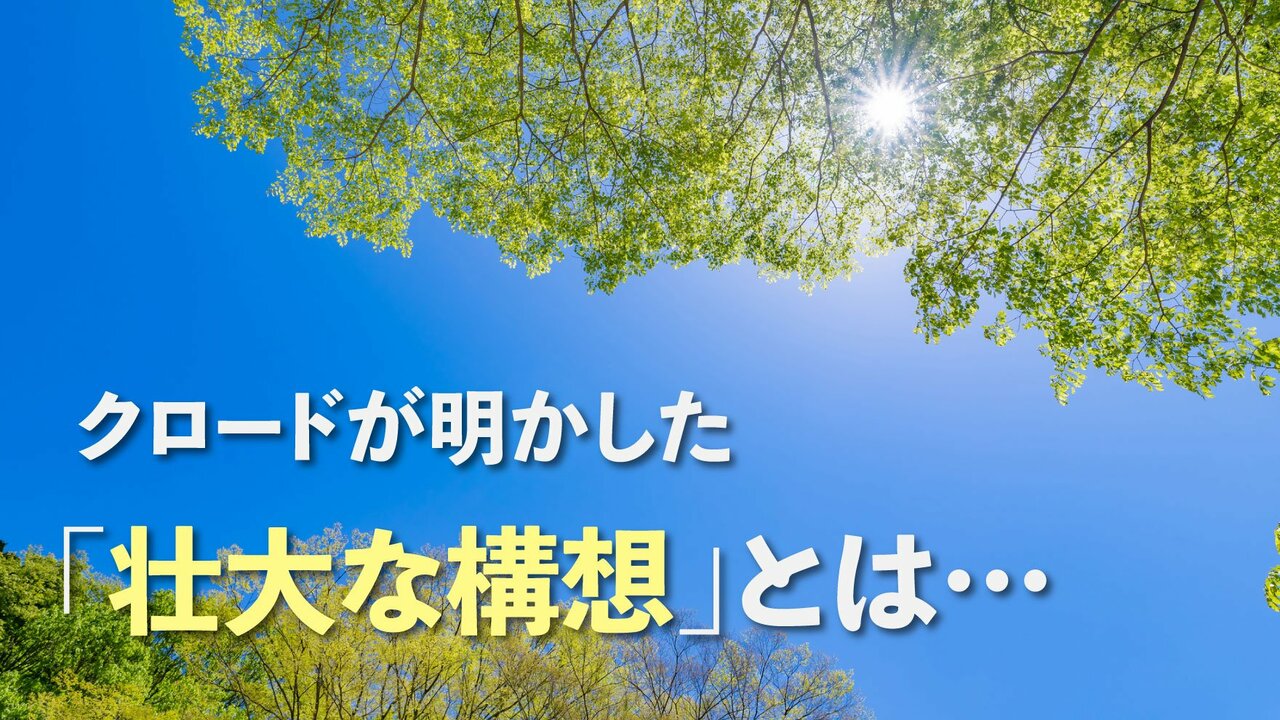ムッシュー・モネは、少し言いにくそうに尋ねる。
「……君は、あのときの弁償をさせられるのかい? それはいくらだろう?」
「あ」
そうだったのか。たった今まで、ムッシュー・モネが「私が払います」と店主に詰め寄ったことを忘れていた。あのときはうれしかったけれど、ただあの場の状況に憤ったあまりの言葉だと深く受け止めはしなかった。でも、彼は覚えていてくれたのだ。
モデル料としてカミーユにお金を支払うことで、間接的に弁償しようと考えてくれたのだろう。たまたま入った店でひどく叱られている小娘に同情し、店主に憤慨し、怒りに任せて気まぐれに口にしただけの言葉だと思っていたのに、あのときのカミーユはその言葉だけでも十分に救われ感謝したのに、彼は今まで覚えていてくれた。
もしかしたらあの日、再会を待ちわびていたのは私だけじゃなかったのかしら。そんな期待がどうしようもなく膨らんで、それを二人に気取られそうで、カミーユは慌てて頭を下げた。
「ありがとうございます」
下げたところで涙がこぼれ出そうになったので、また慌てて言葉を継いだ。
「覚えていてくださったなんて。……ありがとうございます」
目頭に溜まった涙をそっとぬぐうと説明した。
「あのときのあの生地は、結局、汚れたところを除いて、襟や見返しなど細かいパーツに使い回せるので、それほどの損失にはならないようなんです。店頭の台も床も少し削ってワックスを掛けたらもとに戻りました。次回のお給金は減額すると言われましたけど、実は私、まだお針子見習いで、お給金自体少ないから減額といってもたいした額ではないんです」
ムッシュー・モネは優しい顔で聞いていた。弁償額自体が少なかったことは喜んでくれているらしい。
「だけど君、あの店主はずいぶんひどいじゃないか? 店を辞めたら君は困るのかい? その代わりになるほどはモデル料を払えないとは思うんだが……」
カミーユは首を振った。
「ああ見えて悪い人ではないんです。ちょっとケチで、すぐ癇癪を起こしますけど。私は、店ではまだ縫製を任せてはもらえませんし、家計の足しになるほどのお給金を頂けるわけでもありません。私が辞めたところで、どなたにもご迷惑はお掛けしないでしょう。ただ私、仕事は嫌いじゃないんです。誰かの役に立つのはうれしいし、自分で稼ぐって楽しい、……自由ってこういうことなのかなって」
しゃべり過ぎたと思った。うっかり、修業を積んで最先端のドレスを縫ってみたい、などと夢まで語るところだった。もしかしてムッシュー・モネをがっかりさせてしまっただろうか。モデル探しに苦労していたとはいえ、私のためも思って提案してくれたのに。カミーユは、彼の次の言葉を待たずに尋ねた。