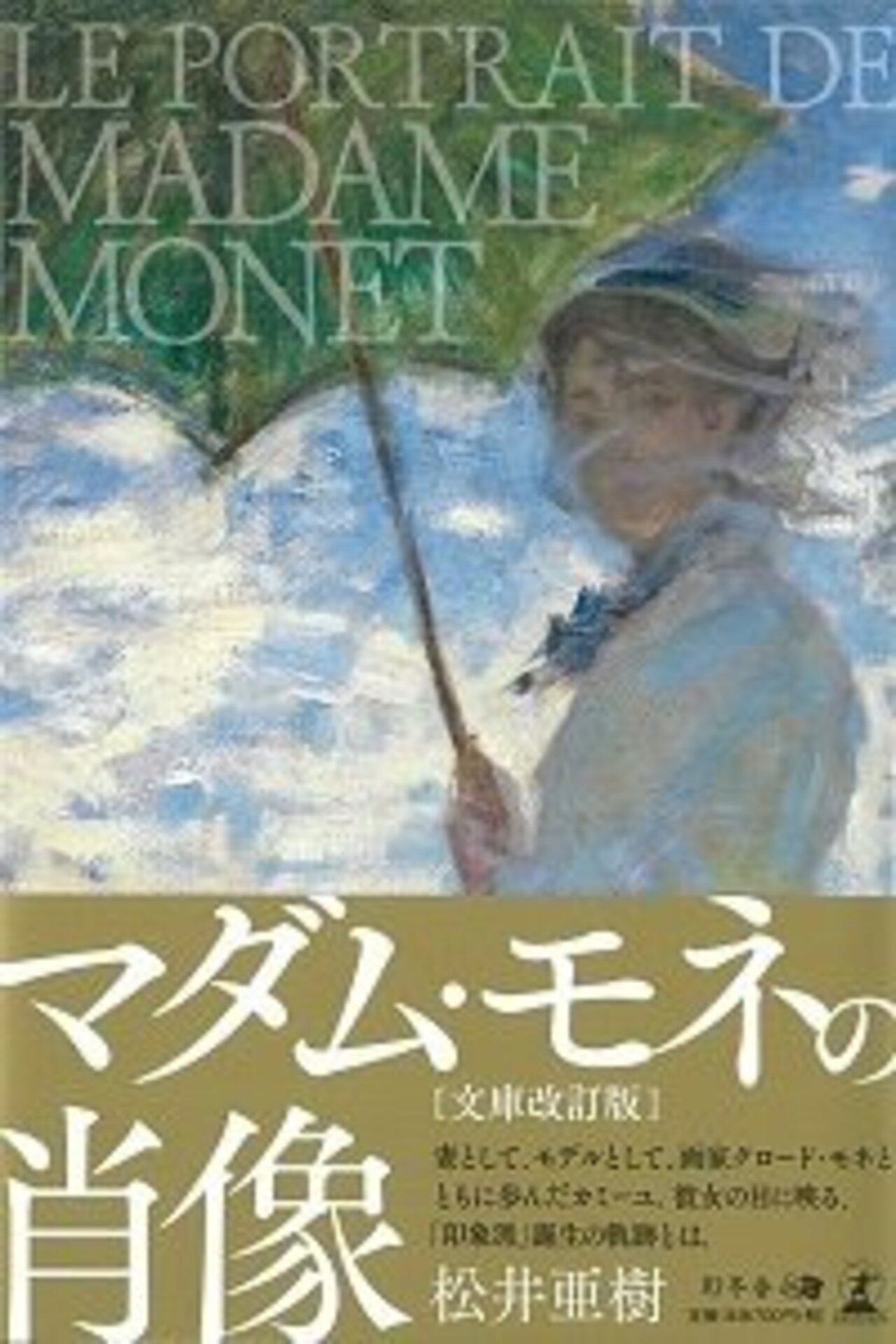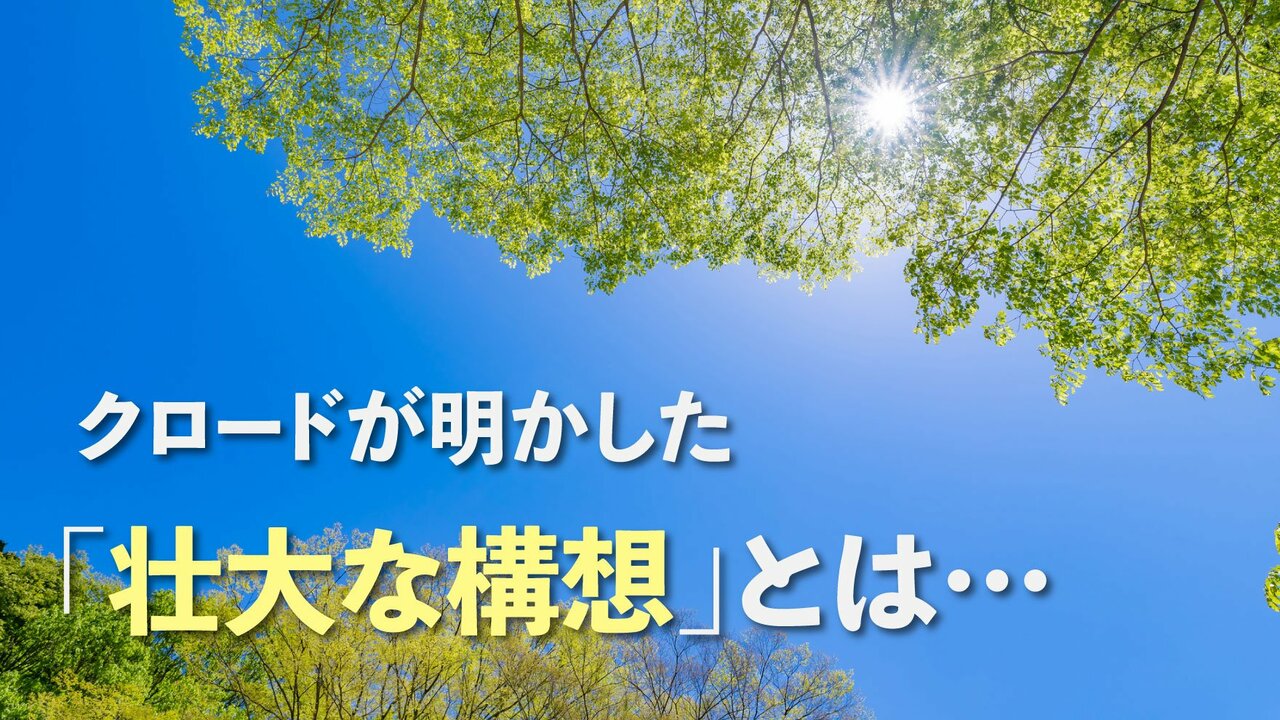カミーユは二年前、急速に工業化するリヨンでの農業に見切りを付け、新しい職を求めて移住する両親に付いてパリに出てきたばかりだ。リヨンでは、できたばかりの公立女子小学校に通わせてもらった。
家庭教師に学ぶ良家の子女のようにギリシャ語やらラテン語やらは知らないが、母国語の読み書きにはさして不自由しないし、お金の計算だってできる。慣れない工場勤めを始めた父を少しでも助けたくて、この夏からテーラーでお針子見習いとして働いている。もともと手先は器用な質だったが、きちんと学んでもっと上手に洋服が縫えるようになったら、将来結婚してもお母さんになっても、きっと役に立つ。
とは言っても、店ではまだあまり生地に触らせてもらえない。掃除や雑用が多く、手が空いたときに印付けや仕付けを頼まれるくらいだ。
一八五八年、世界初のオートクチュール・ドレスメゾン「ウォルト・エ・ボベルグ」がパリに開店した。一八六五年のこのころには、そのイギリス人店主シャルル・ウォルトは、ナポレオン三世の皇后ウジェニーをはじめ名だたる貴婦人たちを顧客とし、店はたいそう繁盛しているという。
大きな舞踏会が催される晩などは、ウォルトに着付けを指南してもらおうと押し掛ける馬車の列で店の前は大渋滞するらしい。何でもウォルトは、マヌカンたちに自作のドレスを着せてファッションショーとかいうものを催し、自分のデザインを売り込むのだという。
これまではテーラーもドレスメゾンも、客の注文通りに服を作るのが当たり前だったから、「ウォルト・エ・ボベルグ」は実に画期的なのだ。余程自分のデザインに自信とこだわりがあるのだろう。
皇后様さえ気に入ってお求めになるというドレスは一体どんなものだろう。胸元のレースは、どれほど繊細なものだろう。例えば花柄なら、きっと気高いバラが匂い立つようなドレスなのだろう。カミーユは、わずかに目にしたことのあるファッション誌のイラストをうっとり思い浮かべた。
私も腕を磨いたら、いつかそんな店で、社交界を彩る華やかなドレスを毎日眺めながら仕事ができるだろうか。そんな想像をしているうちにポン・ヌフを渡り終えていた。
店主がメモした紙切れには「フェルスタンベール街六番地」と書かれている。まだパリの地理に明るくないカミーユにとって、初めて訪れる場所だ。ポン・ヌフを渡ったところで右に折れ、二ブロック目を左に曲がる。しばらくまっすぐ……、それから何度か角を曲がり……、ここがフェルスタンベール街。
きっと、こんなお使いでもなければ入り込むことはなかっただろう小さな通りだ。まっすぐ進むと、途中で通りは方形に膨らみ、その中央に小さな緑地帯があった。すっかり葉を落としたマロニエが数本植わっていて、ガス灯の足元に二人掛けのベンチが置かれている。