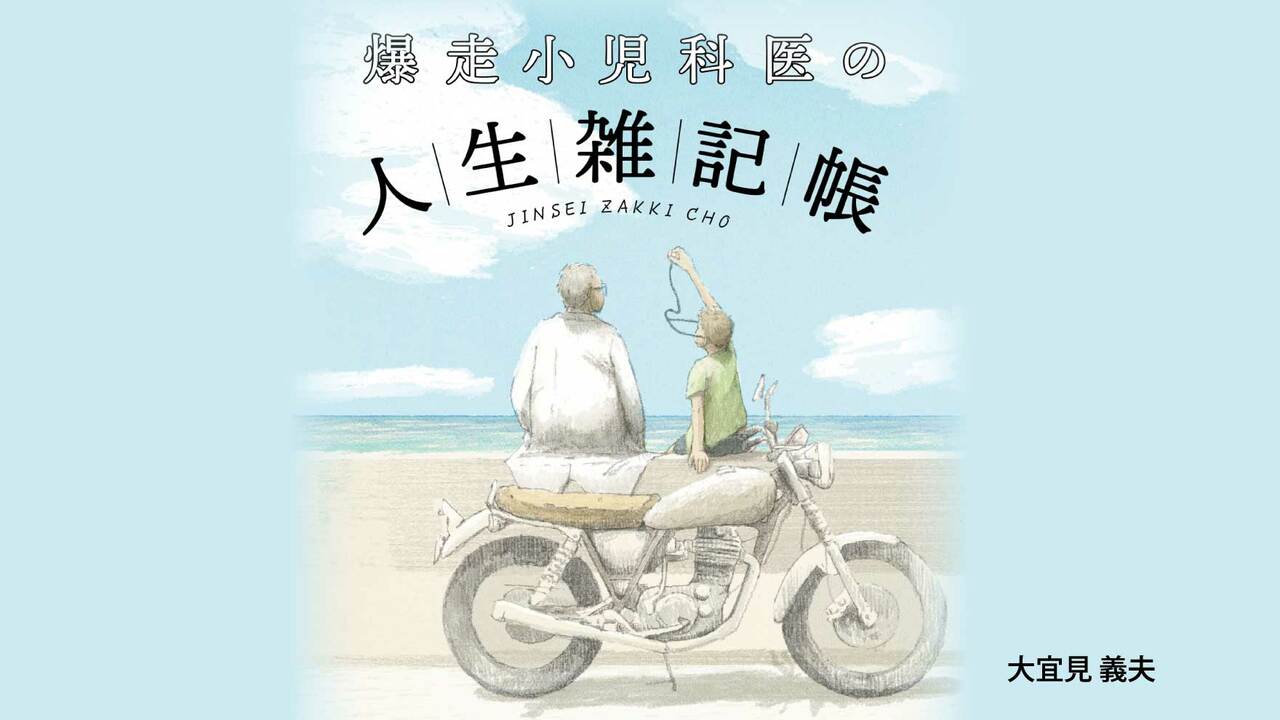無給医時代
過日の全国紙(読売新聞2019.6.29)に「大学病院無給医…研修名目『白い巨塔』の悪弊」という記事が大きく掲載されていた。
無給医局員……。
五十年以上も前に私も無給医時代を経験した。インターン研修を終え、医師免許証をもらって二年目の春、北大医学部小児科学教室に入局した。新米医師として先輩から診療の基本を学ぶためである。
入局すると早速、大学病院に入院中の患者さんをあてがわれ、先輩医師とタッグを組んで臨床研修に励んだ。無給医の身分ゆえに生活費は週一回、地方の公立病院や炭鉱病院へ出張診療を行い、その謝金でまかなっていた。何かの都合で出張診療ができないと途端に生活に窮した。
当時、結婚したばかりで、ないないづくしの生活を強いられ、妻の貯金もあっという間に使い果たした。家具の代わりに妻の実家から送られたリンゴの空き箱を利用し食器棚、衣類ケース、食卓、書棚の代用とした。
長女が生まれると、ベビー服を買う余裕もなく妻はもっぱら手縫いで間に合わせていた。
ある日、妻から医局に
「今、おうちにお金が二十円しか残っていない……」
との電話が入り、慌てて医局から一万円を借りて駆け参じたこともあった。電車賃を節約し病院とアパートとの間の二kmの道を毎日駆け足で通った。
カバンが買えず書籍や資料を風呂敷に包んで抱え、オーバーコートを翻しながら走ったので朝は決まって犬に吠えられた。小雪ちらつく夜半、風呂敷包みを抱え走っていると、うしろからついてきたパトカーの職務質問を受けた。
「どこへ行くの」
「家に帰る……」
「なぜ、走っているの?」
「急ぐから……」
「職業は?」
「医者……」
「どこで働いているの」
「北大病院……」
「生年月日は」
と聞くので和暦で答えると、すかさず
「西暦では何年?」
とたたみかけてきた。ウソを見抜く尋問手法のようだった。当時私は、気分一新をはかり丸坊主にしていた。丸刈りの男が深夜、風呂敷包みを抱えて走っているものだから怪しむのもムリはなかった。
結局、運転免許証を見せることでケリがついた。