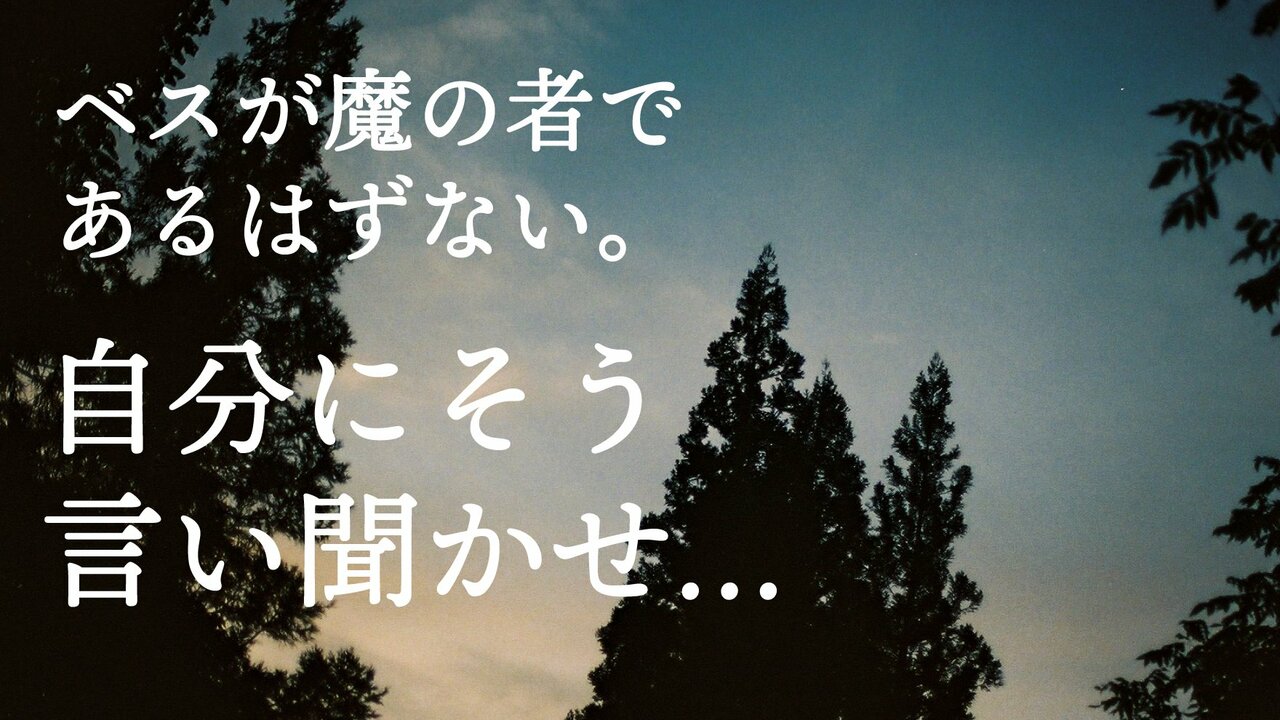ディアナベスと名乗ったその少女は、ゆっくりとたき火に近づき、ラウルのいる方へ歩いてきた。
「火に当たってもいいですか? 寒いんです。」
少女はラウルの返事を待たず、たき火の前に腰を下ろした。確かに体は冷え切っているようで、いくらか水をかぶったように全身が濡れている。ラウルは急いで立ち上がり、そばにつないである馬の背中の麻袋から、自分のマントを取り出した。
「私のもので良ければお使いになって下さい。」
言いながら、ディアナベスの肩を包み込むようにマントをかけた。
「お優しいこと。お言葉に甘えてお借りします。」
彼女の震えはすぐには止まらなかったが、たき火の温かさとマントのおかげで、半時間も経った頃には、青白い顔にいくらか赤みが差してきた。
二人はウッドベル港での火事のこと、どうやって難を逃れたか、一緒に同行していた者と混乱の中、はぐれ、ここまでたどり着いた経緯などを話し合った。
ディアナベスは侍女長と、宿泊していた館を逃れたが、途中足に怪我を負った侍女長を運ぶ男手を探しに、炎に包まれていく街をさまよううち見知らぬ郊外へひとり出てしまっていた。
しばらく二人はそれぞれに今日の出来事を思い返し、沈黙が訪れた。騎士団の仲間たちはどうなったんだろう。ルカは、マーセルやエリアスは。選りすぐりの騎士たちだ、無事であることは間違いない。やはり今夜はどこかで暖をとっているのだろう。
ルカの馬は疲れ知らずだ。ひょっとしたら近隣の城まで飛ばしている最中かもしれないぞ。
「ラウルは何歳になられるの?」
突然の問いにラウルは思わず、ディアナベスを見た。左右の大きさの違う目、大きすぎる額、主張の強すぎる鼻、そばかすだらけの肌。
しかしその深い緑色の瞳は、何か抗いがたい知性の高さをたたえ、全体としての雰囲気は高貴な王族の品格にあふれていた。