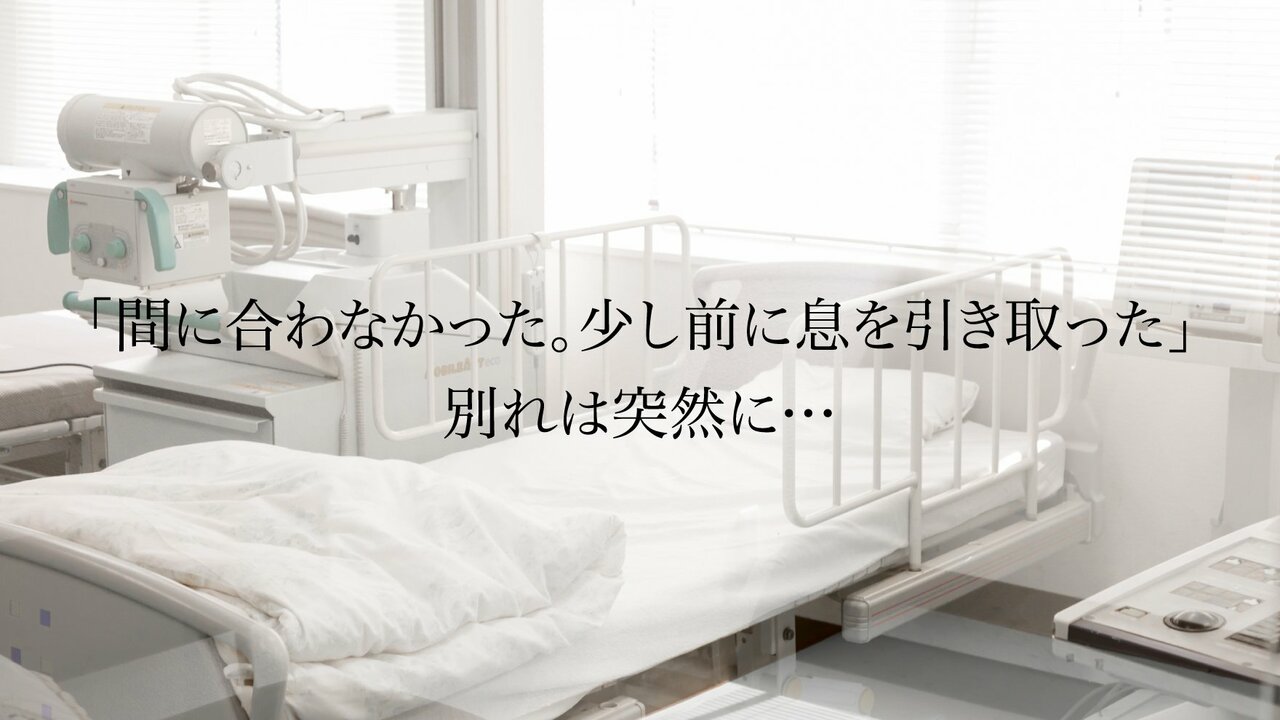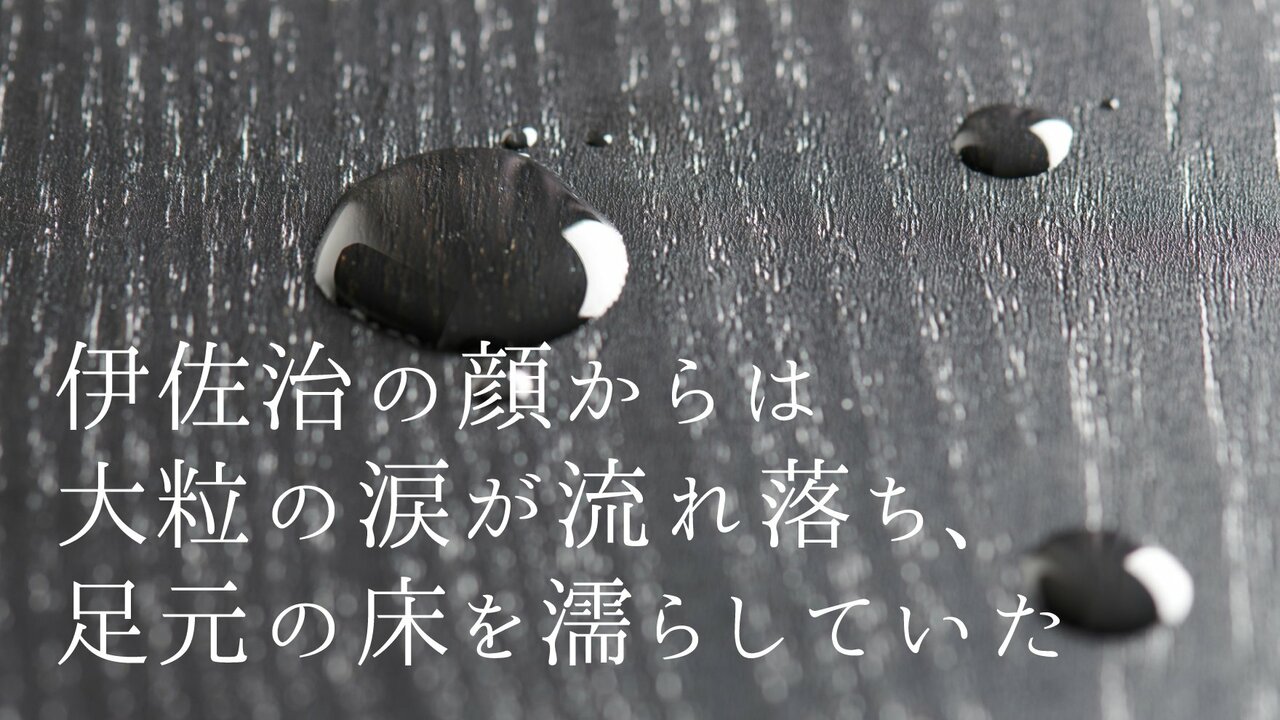【関連記事】「出て行け=行かないで」では、数式が成立しない。
別れは突然に
武蔵野の台地に広がる茶畑には、ヒバリがホバリングをしながら、鳴き声を響かせていた。
空を見上げ新鮮な空気を胸いっぱいに吸い込むと、桃子は「よし」と、自分に気合を入れ始発駅へと向かった。改札口を抜け、階段を上ったホームはすでに通勤客で溢れていた。
ドアーが開くと同時に桃子は自分の意志とは関係なく、中へ中へと押し込まれた。やっとのことで自分の居場所を見つけると、ため息をつきながら下方に目を落とし、通勤地獄の洗礼を受けていた。
幸い急行だったので、この先停車する駅は限られていたが、どの駅にも乗客が溢れていた。もう人が乗れる隙間はないと思われたが、不思議と、どうにかなるものだなと感心し、クスッと頬が緩んだ。
自由に手足を動かすことができない桃子は無駄な抵抗をあきらめ、身を電車と乗客の揺れに委ねることにした。長い地獄のような時間から解放され、目指す駅の改札口を抜けたところでバッグからスマホを取り出した。
大学卒業後、大手広告代理店に勤務していた桃子は、この日、取引先に呼ばれデザインのプランを説明することになっていた。地図アプリを開き訪問先を確認している時、突然、着信を知らせる「安室保奈美」の曲が流れてきた。
桃子のお気に入りの曲だった。
「お父さん、どうしたの」
短い沈黙に桃子は胸騒ぎを覚えた。
「潤子が入院した。担当医の話だと危ないかもしれないって。至急、帰って来て欲しい」
と、父の途切れ途切れに話す声が耳に残った。
潤子は伊佐治の妻であり桃子の母の名だった。
「毎日忙しそうで大変ね。無理して体を壊さないよう気を付けるのよ」
と、笑顔で送り出してくれた母が入院したなんて、すぐには信じられなかった。
母は生まれつき体が丈夫な方ではなかったので、激しい運動は避け散歩やラジオ体操程度の軽い運動を日課にし、体調管理には充分すぎるほど気を付けていた。なんで……。
頭の中が混乱している桃子は気を取り直し、勤務先の上司に電話を入れた。事情を説明し、取引先のお客様のところには代わりの者に行って貰うよう上司にお願いすると、はやる気持ちを抑えタクシー乗り場に向かって走り出した。
桃子は病室の前で一瞬立ち止まったが、意を決し静かにドアノブを回した。シングルベッドにはすでに息を引き取った母の姿があった。桃子と目を合わせた伊佐治は、
「間に合わなかった。少し前に息を引き取った」
と、話すのがやっとだった。
「なにがあったの」
と聞く桃子に、
「潤子が朝食の後片付けを済ませ、洗濯物を干そうと竿に手を掛けた時だった。その場に崩れるように倒れた。抱き上げソファーに横にさせるとすぐに救急車を呼んだ」
力のない声で話を続けた。