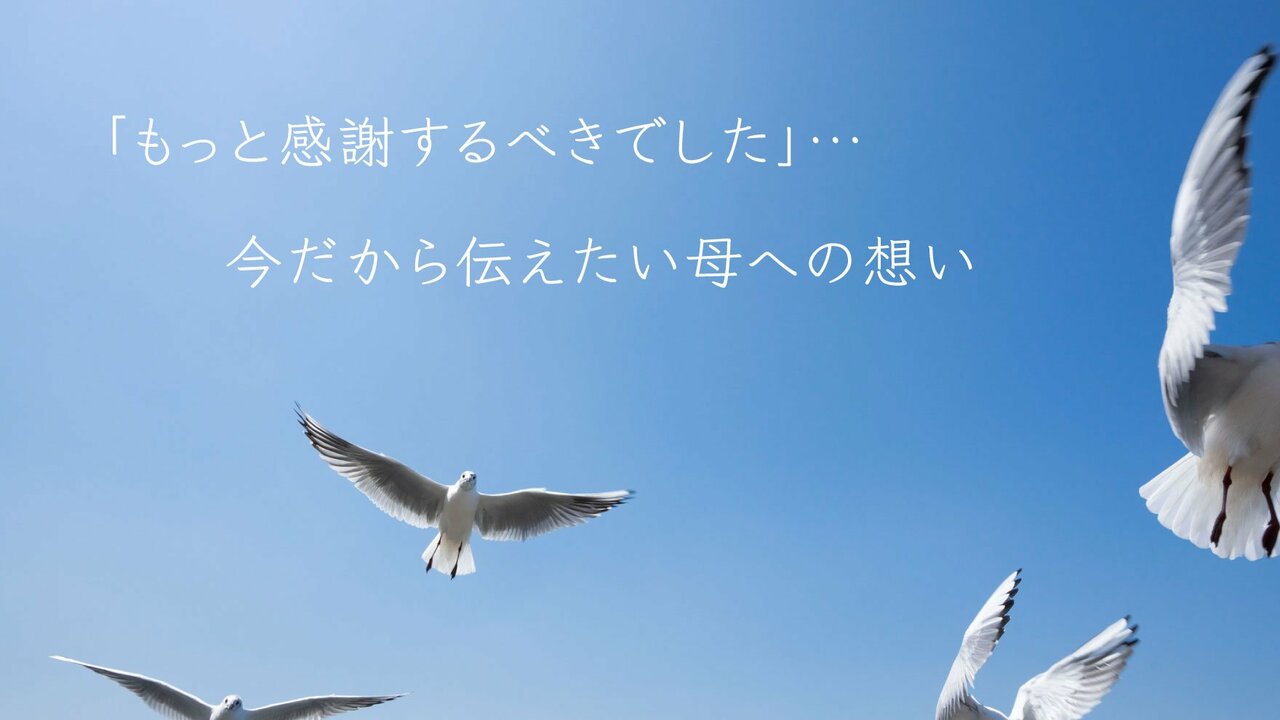高校時代、卒業したら『美術の大学に進学』の道は選びませんでしたが、大学入学後は、1年生で国体800m走で3位、日本インカレで2位、そして大学2年生と3年生で日本インカレ優勝を手にできたのです。
大学卒業後には女子高校の体育教師になったため、『美術への思い』はますます遠のいていくのでした。体育教師になって3年目。同期が担任に任命される中で、私だけ名前が呼ばれませんでした。
私に対しての「教師としてはまだまだです」という評価と感じ、挫折感と劣等感に包まれる日々でした。
「私は認めてもらっていない」という思いから、授業がない時間の職員室で、すっかり遠のいていた絵を描くようになりました。白いスケッチブックに頭に浮かんだ世界を描く時間が、私を無心にしてくれるのでした。
太く柔らかで濃いBの鉛筆、薄くて硬いHの鉛筆を使い分けながら、海から飛び出した魚が突然、女性に変化し、女性の手からまた魚が泳ぎだす。授業が空いた時間は、瞑想をするように鉛筆画を描いて、それをためていました。
ある日、私の絵を見ていた隣の先生に声を掛けられました。「今度、趣味でやっている彫金の個展を画廊喫茶でやるの。一緒にどうですか?」定年直前の世界史の先生でした。
「やります。でも、作品数が少ないので、これから家でも何枚か描きますので、一緒にやらせてください、よろしくお願いします!!」
と胸を躍らせました。個展が迫ったある日のこと、電車のドア横に寄りかかりながら作品を描いていると、絵の上に名刺を差し出してくる人がいました。
見上げると、スーツ姿の男性でした。
「突然に失礼しました、私は〇〇出版社の者です。実はお願いがあります。ホテル・ニュージャパン火災で九死に一生を得た方を記事にしておりまして、その方の体験を絵で説明していただけないかと思い、声を掛けさせていただきました」
電車でスカウトする人なんて、いるか?――と用心していると、降りる駅が偶然一緒でした。
「原稿がここにあります。これを読んでいただいて、燃え盛る炎の中、シーツを使ってどうやって窓の外に逃げることができたか、一週間でこのサイズに描いていただけないでしょうか? 資料はここに入っています」
と渡され、それを引き受けることにしました。