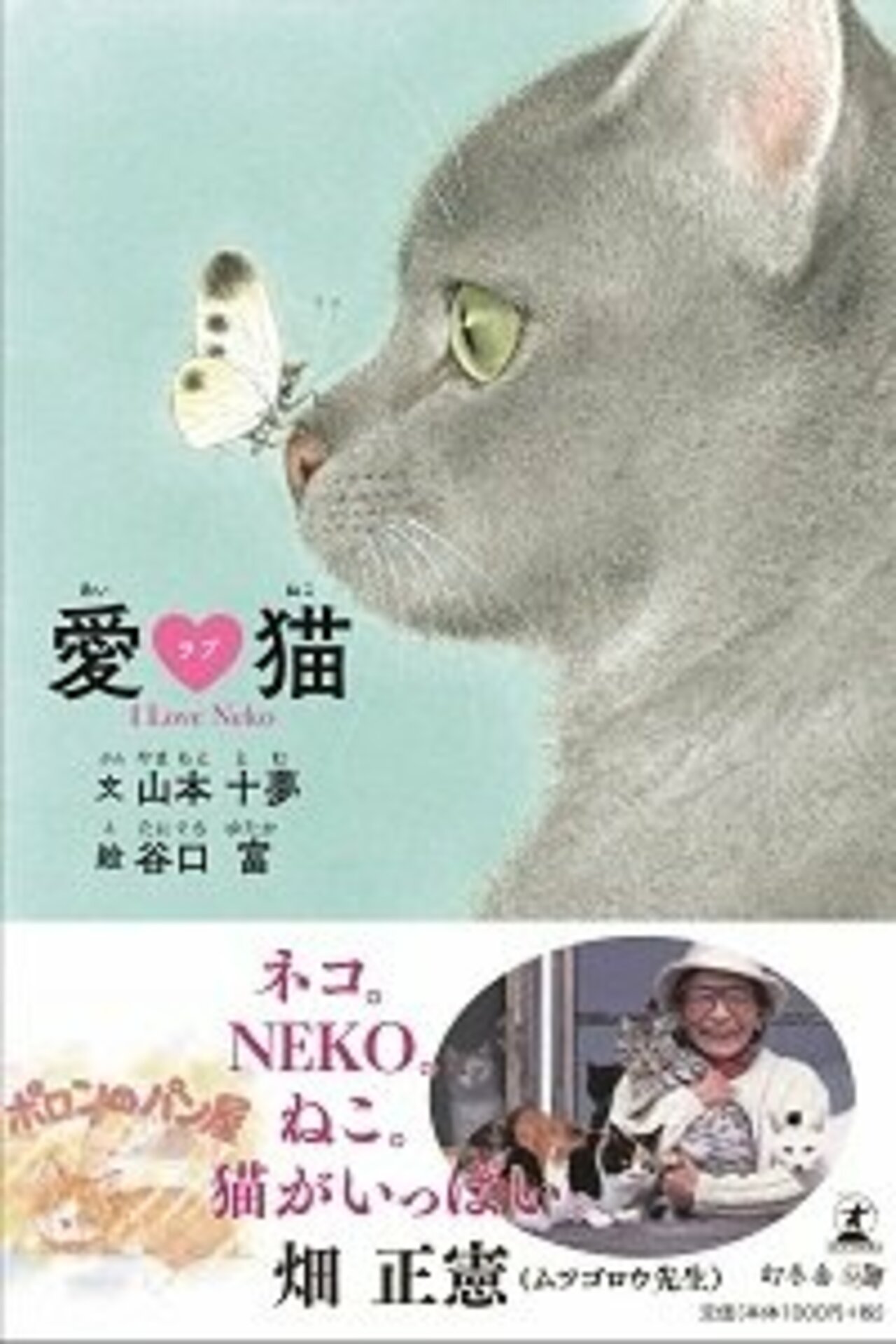猫のミミ
「おいぼれのじいさんには、お金やら、物やら、なーんもいらん。楽しい思い出は心の中にたくさん残っておるからのう。今は一日じゅうミミと、こうしておるだけで幸せなんじゃ」
そう言って、えんがわで一緒にひなたぼっこをしながら、まったりとした日々を重ねていったんじゃ。それから1年後じゃった。
“会うは別れのはじめ”とはよく言うたもんじゃ。イチョウがこがね色にそまって落ちはじめるころ、ミミの食欲が、ふたたび落ちてしもうたんじゃ。
「また猫風邪か」病院へ連れていって診てもらうと、老衰と言われた。ミミの好きなかつお節やのりもやったんじゃが、もうあまり食が進まなかったらしい。
一日のほとんどを、ミミ専用の座布団で寝るようになった。抱きあげるたびに、あれほど重かった体重が、スカスカに軽くなっていった。
そして、こな雪が庭じゅうに舞い散る寒い朝じゃった。ミミは布団の中のおじいさんの足もとで、小さな声でミャーミャー鳴きだしたそうじゃ。おじいさんは、いとおしくなってミミを抱きあげた。するとな、おじいさんの腕を、ゆっくり、ゆっくり、なめだしたんじゃ。ざらっ、ざらっと。