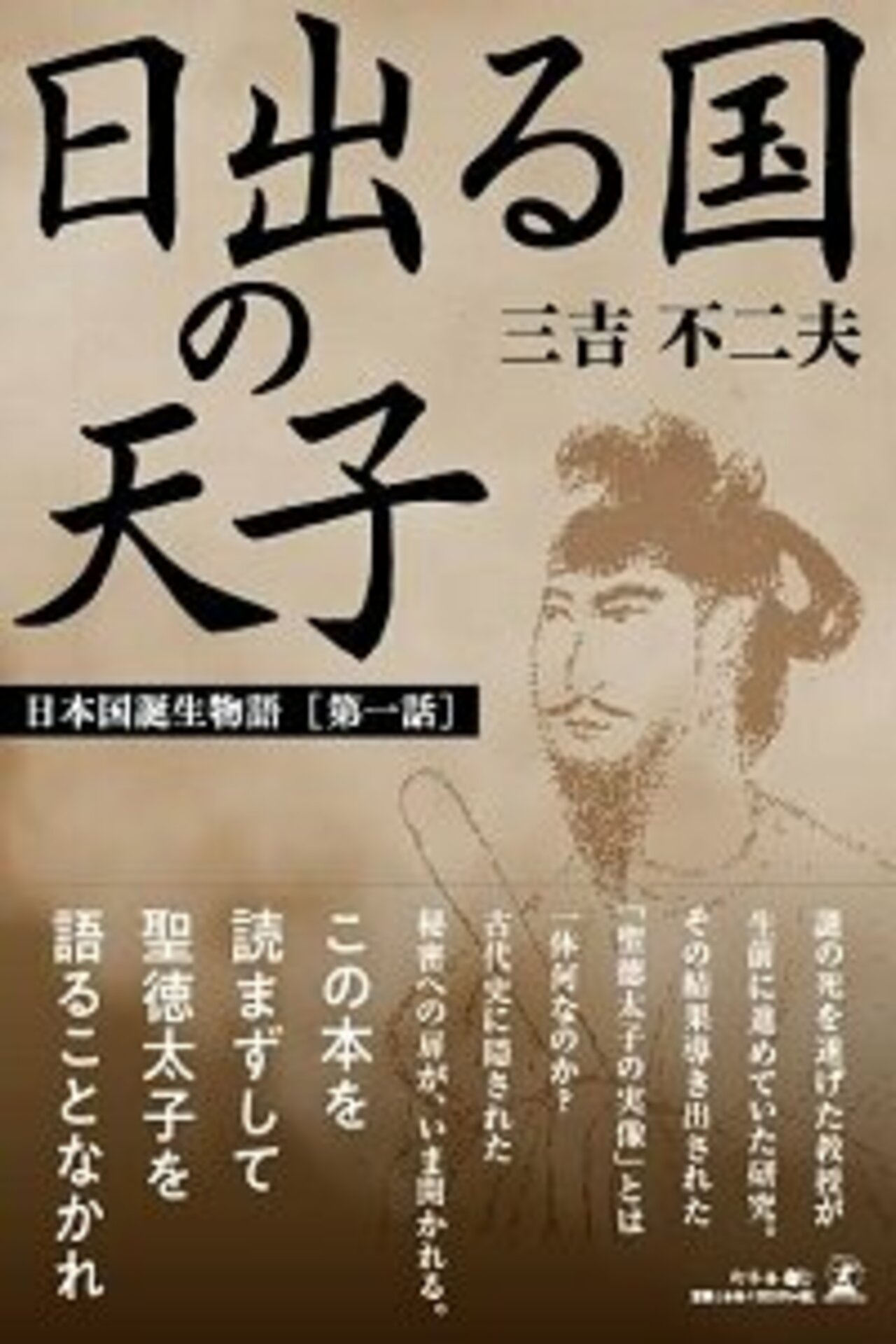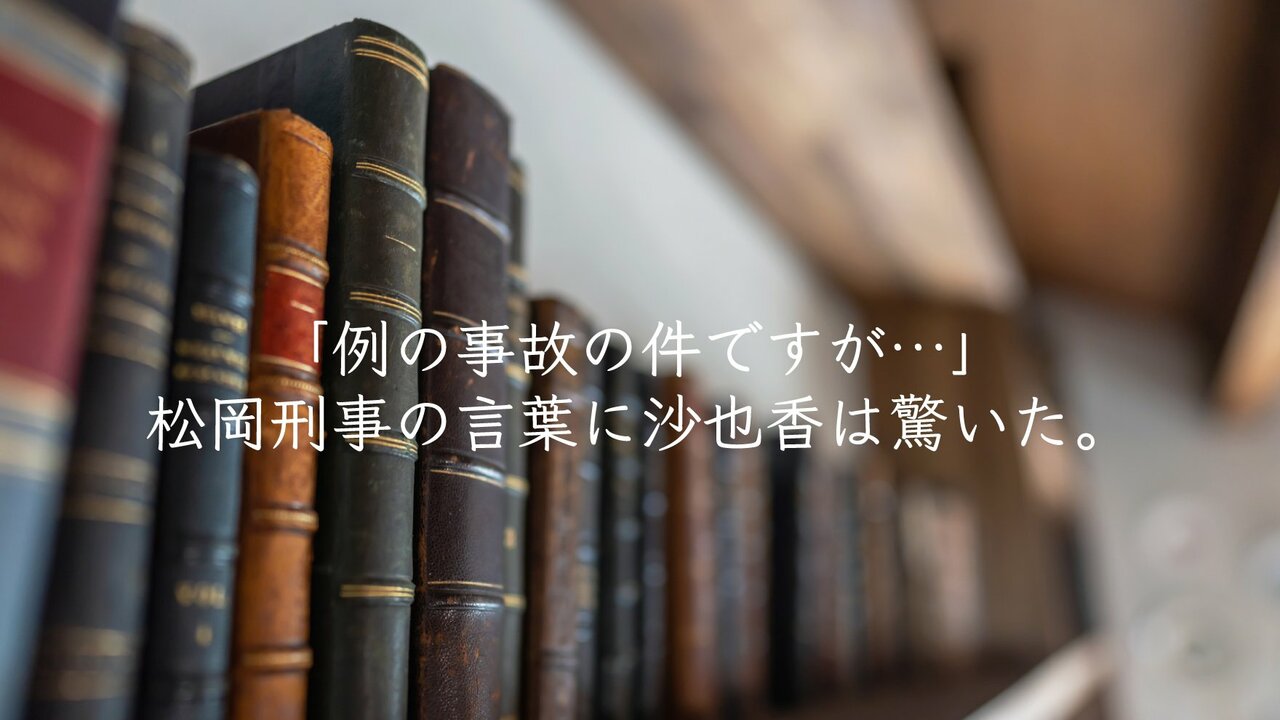手掛かりは少しずつ、しかし確実に増えていく
「なにか、役に立ちそうなことが書いてありました?」夫人がにこっと笑って聞いた。
「ええ、つい夢中になって読んでいました。あの…わたし、どのくらいの時間読んでいました?」沙也香は少し照れながら聞いた。
なにかに熱中すると時間を忘れてしまう。
「そうですね、三十分くらいかしら。ずいぶん熱心に読んでおられましたね」
「そうですか…」三十分ならまあいいか、と少しほっとする。するといま気づいた疑問が頭をもたげてきた。「このノートですけど、最後のところが何ページか、ちぎれてなくなっているんです。これは高槻先生がされたんでしょうか」そういってノートを見せた。
「いいえ、主人はそんなことはしないと思います。このノートは、特に大事にしていたものの一つですから…」夫人はノートを見つめながら不思議そうにつぶやいた。
「では誰がこんなことをしたんでしょう」沙也香も少し考えていたが、ふと思いついて聞いた。「このノートは、こちらの大学の研究室に置いてあったものですか」
「いいえ。そのノートは、東京のW大に置いてあった荷物の中にありました。たぶん向こうでも書き続けていたんだと思います」
「ではいったい誰が…」沙也香はつぶやき、ひょっとして冷却水を抜いた犯人がやったことでは─ といいかけて、あわてて口を閉じた。うかつな想像を口にすべきではない。
「じゃあ最近のものを五冊ほどお借りさせていただきます。大変参考になりそうなので」「わかりました。では、ノートはほかのものと一緒に宅配便で送りましょう」
「いいえ、これは持って帰ります。すぐ読んでみたいことがたくさん書いてありますから」「そうですか。ではそうなさってください」
沙也香たちは、送ってもらう資料をもう一度確認し、高槻家を辞した。