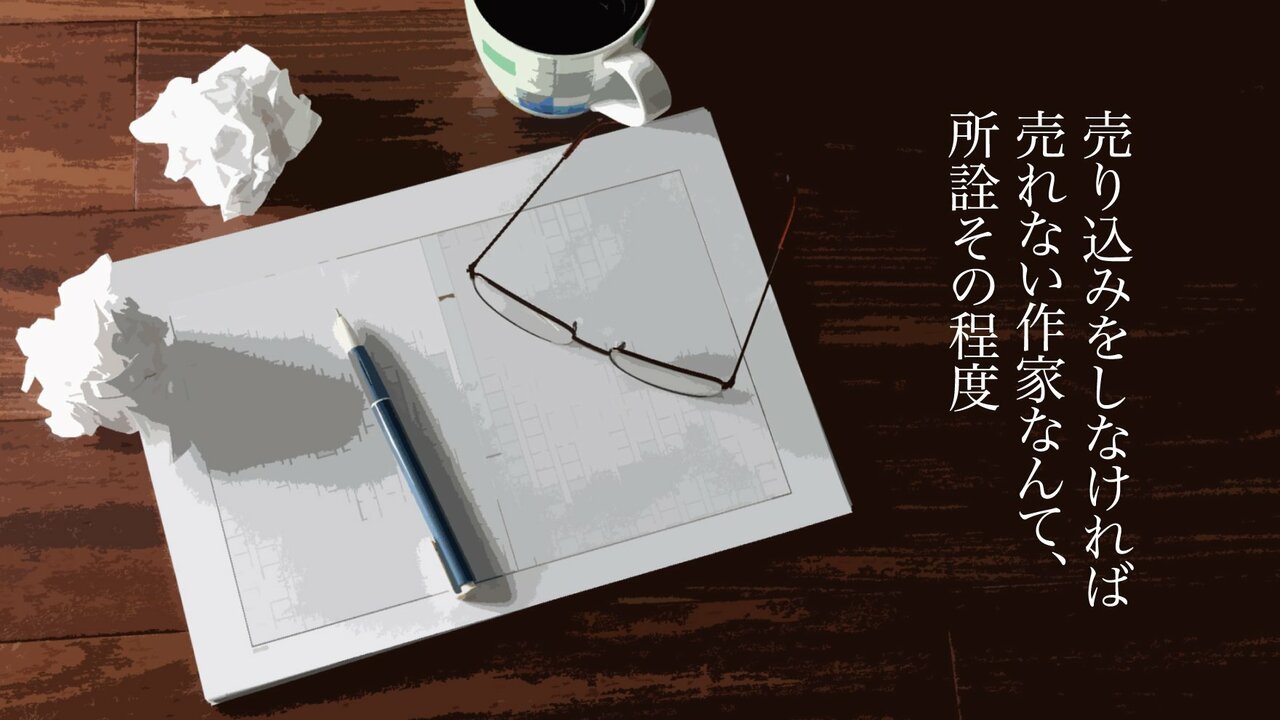ライジング・スター
会場は、銀座のはずれにある瀟洒(しょうしゃ)なホテルで、ハイエンドクラスではないがそれなりの格式を醸(かも)し出している。いずれにしても、今の自分にはまったくそぐわない場所だ。気乗りのしない足取りでロビーに入ると、一目で文壇あるいは出版関係者と分かる姿がそこかしこで目に入り、とたんに気後れが生じた。
やはりやめよう、と踵(きびす)を返したとき、「芹生くん」と馴染みのある声で呼び止められた。振り向くと田村理津子だった。彼女とは文芸サークルでいっしょだったが、俺が大学を中退してからは会っていない。
「あっ、リコ。やあ、久しぶり」、突然の再会にどう振舞っていいのか戸惑った。
「久しぶりね。元気だった?」
サークル時代から際立っていた理知的な美しさは少しも変わっていない。いやむしろ、時が若さにありがちな過剰な自己主張を削り取り、滑らかな魅力を醸し出している。すらりと伸びた白い手足が眩しい。
「あなたが大学を辞めて以来ね」
「そうだね。七年ぶりになるか。話には聞いているけどTV局に勤めているのだって?」
「ええ。コスモTVの、今は企画にいるの。でも将来的には翻訳の仕事がしたくて、時々翻訳の仕事をフリーランスとして請け負ったりしている」
「ふーん、翻訳か。君はトリリンガルだからな。たしか英語と仏語だね」
サークルで文学論議を交わしたときには、相手を論破する論理性と勝ち気な一面を見せた。父親の仕事の関係で海外生活が長かったにもかかわらず、帰国子女にありがちな、会話の中でやたらと英語をまき散らすこともなく、自然な日本語を話す。文章力も相当なレベルだ。家庭での日本語教育が完璧だったのだろう。理津子自身も、母親に奨められて日本の古典をよく読んでいたと話していた。
「ところで沙希ちゃんはお元気?」
沙希は俺の妻だ。大学の後輩で在学中につきあい、いわゆるできちゃった結婚で今に至る。かなり裕福な家庭に育ち、情けない話だが、沙希の実家の援助がなければ生活は成り立たない。
「ああ変わらないよ。子育てでますます忙しくしている」
「すごいわね。あの若さで尊敬するよ。時代に迎合せずに良妻賢母を担うのも一つの考えよね」
「そのぶん亭主には甲斐性がないからね」
俺は自虐的な笑いを浮かべた。
「何を言ってるの。彼女は才能も含めてあなたのすべてに惚れたのよ。今の暮らしはきっと幸せだと思うわ」
「だといいけどね」
「わたしが保証する。それはそうと会場は七階よ。そろそろ行きましょ」
一度は帰りかけたが、理津子に促(うなが)されて会場へ向かった。
「こんな華やかな場所はどうも苦手だ。リコは仕事柄慣れているだろうけど」
「まあね。でもTV局も最近は経費削減で派手なパーティーも自粛モードよ」
「いったいどう振舞えばいいのか分からない」
「気にし過ぎね。誰も芹生くんのことは眼中にないわよ。あ、ごめん。でも招待だから勝手に料理とお酒を楽しめばいいの。それに、作家を目指しているのだったら出版関係者に顔を売るチャンスじゃない」
「う、うん」