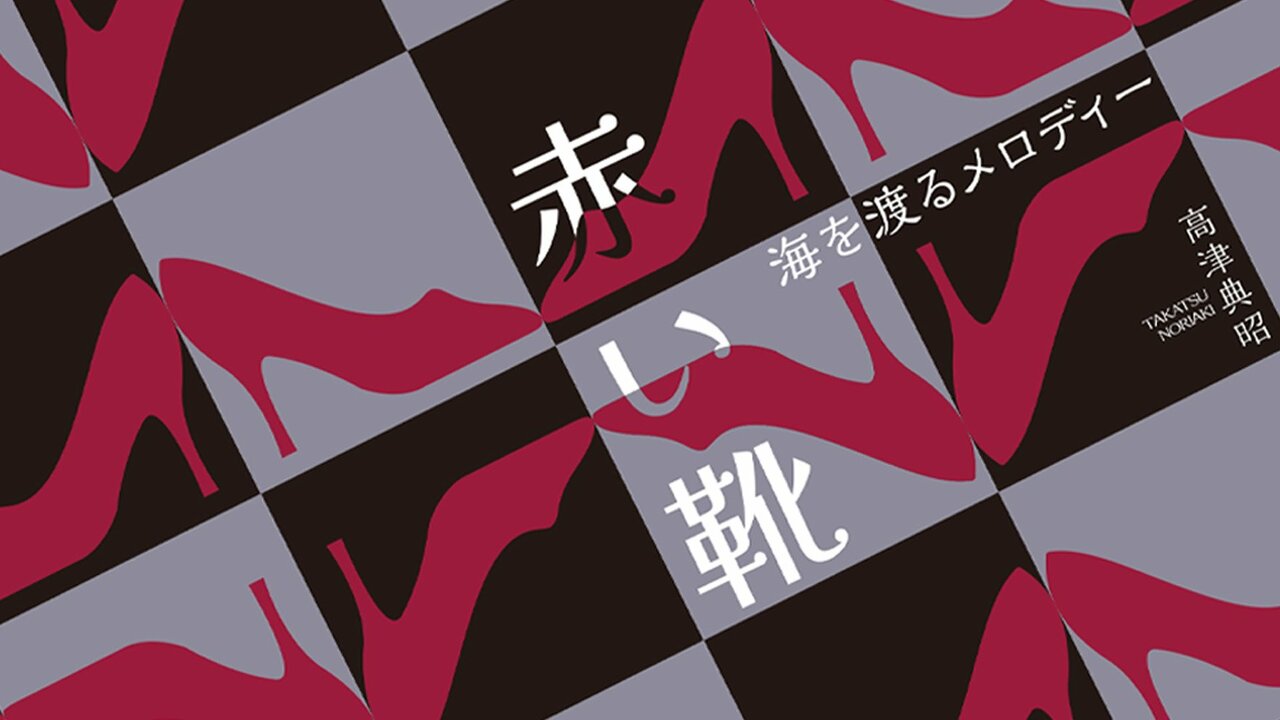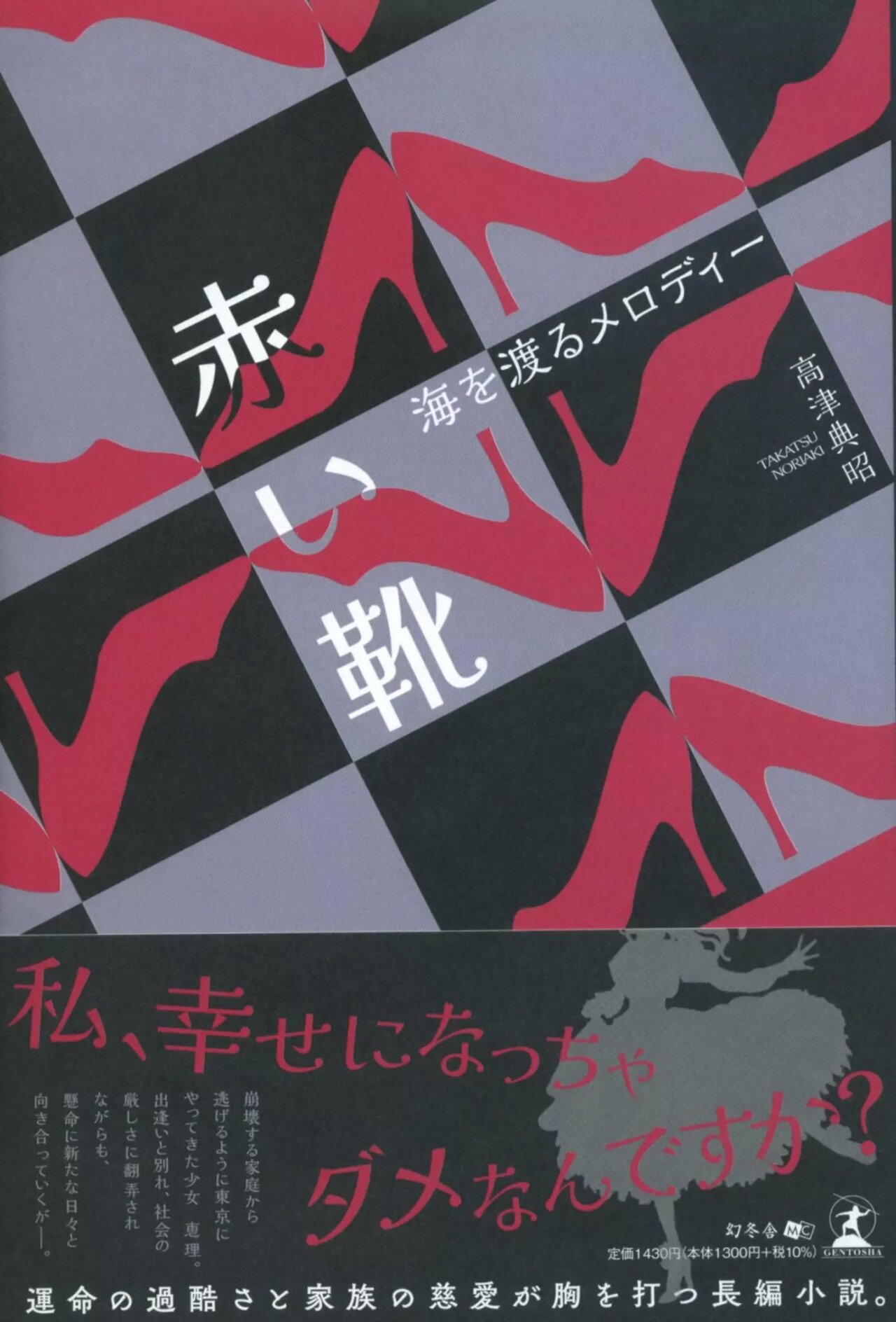第一章 壊れた家族
自分の船は何とか手配できて沖ヶ島まで曳航してもらえるようになったが、我が身をどうやって沖ヶ島の家まで持って行くかが悩みの種であった。
この度の漂流事故の一連の出来事を考えると、アルコール解決策がパニックが起きた時に必ずしも効かないことがあるんじゃないかと疑うことになった。しかし、それ以外の解決策は全く見つからない。
「帰るに帰れないのか?」
どうにかして解決手段をと考えた。すると、ここで名案を思い付いた。
「そうだ、パニックが来てから飲むんじゃなくて、乗り物に乗る前からゆっくり飲んで泥酔してから乗りゃあいいんだ」
なるほど、アルコールのパニックへの即効性は疑ってかかっていたが、最初から泥酔状態を作って乗ればいいんだと。祐一は薄氷を踏むような思いの中、ついに決断した。
羽田空港から八丈島空港への飛行機の出発時間の3時間前からウイスキーを飲み、十分意識を失った間に飛行機の部分をクリアさせる。八丈島から沖ヶ島までは週2回のヘリコプターで行けばいい。そのヘリの出発の日までは肝臓を休ませればいい。時間のかかる船はいつ酔いが醒めるかわからないから使わない。
悪い頭なりに考えた結果、我が身も船も無事沖ヶ島に到着することはできた。しかし、船への恐怖が完全に脳にインプットされてしまった。漁船に乗れなくては漁師は勤まらない。船は諦めて陸から釣るという方法がある。ただし、それでは船釣りに比べると収入面では比べ物にならないほど稼げないし、安定しない。
「陸に上がった漁師」なんて周りからからかわれるのがオチである。それに祐一は無類の見栄っ張りだ。漁師であることに並々ならぬ誇りを持っている。自分の船を手放すなんて考えられない。漁師にとって、命・家族・漁船はどれもいずれ劣らぬ存在であり、優先順位を付けられない程大切なものなのだ。