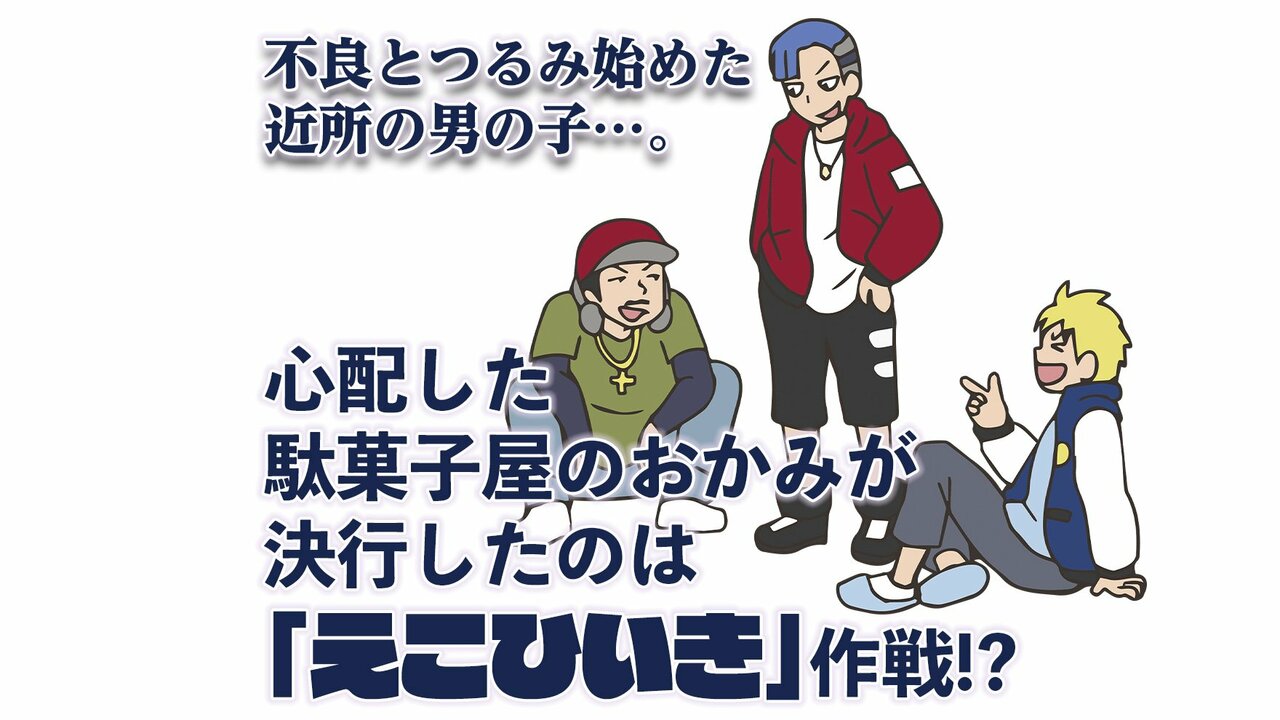「まだ決まっていません」
「そう。なにか困ったことがあったら、その名刺にある番号に電話して。相談にも乗るし、力にもなるよ」
「ありがとうございます。あのー」
「なにか?」
「西純さんは、おいくつですか?」
「三十四だけど。どうかしたの?」
「いえ、わたしの知り合いによく似た人がいるので、おいくつかと思って……」
わたしは嘘をついた。
病室に戻りながら、あれほど子供っぽい顔をした三十四歳なんて、はじめて見たと思った。よほど楽な人生を送ってきたんだろうか。それで、工場で働く女は不幸だと、決めつけているのだろうか。
二
おかしなことに、西純さんは結局、落雷事故のことは聞かなかった。もっとも、わたしも事故の記憶は途切れ途切れになっていて、あまり話せることはなかった。
あの日は朝からパラパラと小雨が降る天気だったが、空は明るかった。それが、あと三十分で昼休み、という頃になると、急に暗くなって雨脚が強くなり、すぐ近くで雷鳴が轟きはじめた。
同僚たちは怯えたようにざわついたが、わたしは気にせずミシンを踏み続け、男物のシャツを縫っていた。しかしすぐにミシンが止まり、電灯が点いたり消えたりしはじめたので、顔を上げた。向かいで作業をしていた楓と目が合った。
その瞬間、彼女の顔は、閃光にかき消されてしまった。わたしは両手で耳を塞いだことは覚えているが、そこからの記憶には、音がない。わたしは転んだり這ったりしながら、なんとか火と煙から逃れ、工場の外に出ることができた。
そこで息が切れて倒れてしまったのだが、守衛の帯田(おびた)さんが駆け寄り、火の粉を払いながら、わたしを助け起こしてくれた。
わたしは残された力をふりしぼって帯田さんの肩にすがりつき、敷地の外まで出たが、そこでまたへたり込み、涙が出るほど咳込んだ。
目の前には水たまりがあって、すでに雨は小降りになっていたことを、妙にはっきりと覚えている。手も白の割烹着も泥だらけになったが、ショックと痛みでそれどころではなかった。