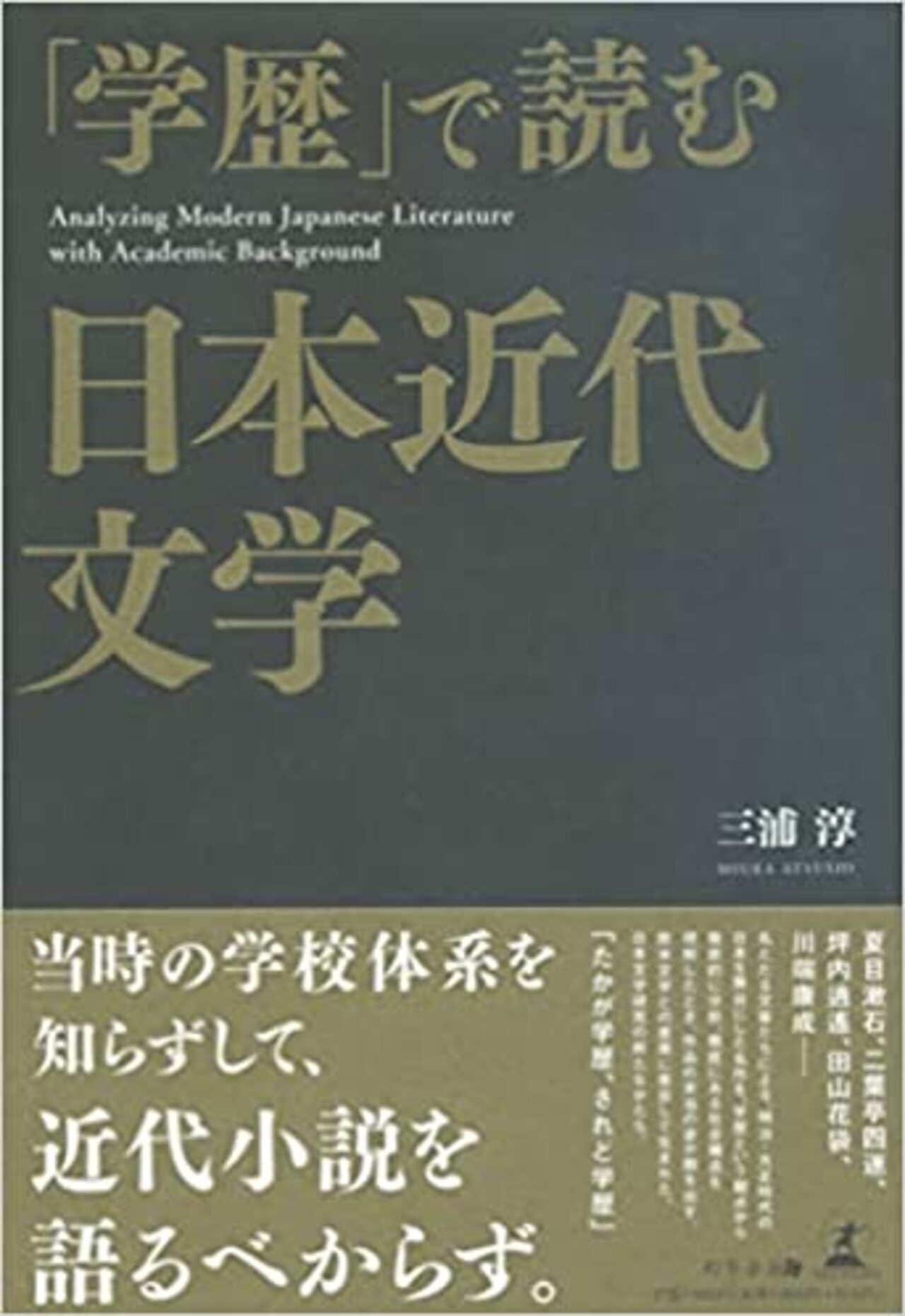大学はどうあるべきかという問題が、この最後近くの第十九回に来て、英国の大学が昔はどうだったかを紹介するという形で取り上げられていることは、『当世書生気質』が明治一八年から一九年にかけて出版された事実からすれば、著者の優れた知識と認識力を示すものに他なりません。
言い換えれば、この小説は明治期日本の高等教育や学生の実態や問題を表現するという点ではきわめて不十分でしたが、英国の高等教育にひそむ欠点を日本人の目を通して明らかにすることには成功していたのです。そしてそうした知識は英国の小説を読むことによって得られたものでした。ですから、逍遙はやはり小説家というよりは、理論と認識の人だったのではないかと思われるのです。
なお、『当世書生気質』の最後の第二十回では、登場した学生たちのその後が簡単に紹介されています。放蕩を悔い改めて勉学に精を出す者、地方の学校の教頭になった者、政党に入りその新聞発行に関わる者、ドイツに留学して哲学研究に没頭する者など、様々です。
しかしいずれにせよ、各人物の行動や特徴はあくまで表層的にしか捉えられておらず、通り一遍という印象が強いことに変わりはありません。
第二節 二葉亭四迷
■二葉亭四迷の受けた教育
次に二葉亭四迷とその作品について検討します。まず、彼の受けた教育について見ておきましょう。二葉亭四迷こと長谷川辰之助は、元治元年(一八六四年)二月の生まれで、逍遙より五歳年下になります。父は尾張藩の下級武士ですから逍遙と同じですが、名古屋ではなく江戸の藩邸に勤務しており、二葉亭も江戸の生まれです。父は明治維新の荒波をうまく乗り越え、当初は名古屋で、その後は島根県や福島県で官吏として勤務するようになります。
幼くして名古屋に移った二葉亭は、まず私塾で漢学を学び、また叔父からも江戸期の伝統的な武士教育、つまり儒教と漢学による教育を受けます。しかしやがて名古屋藩学校に入り、時代の要請に合致した洋学教育を受けるようになるのです。