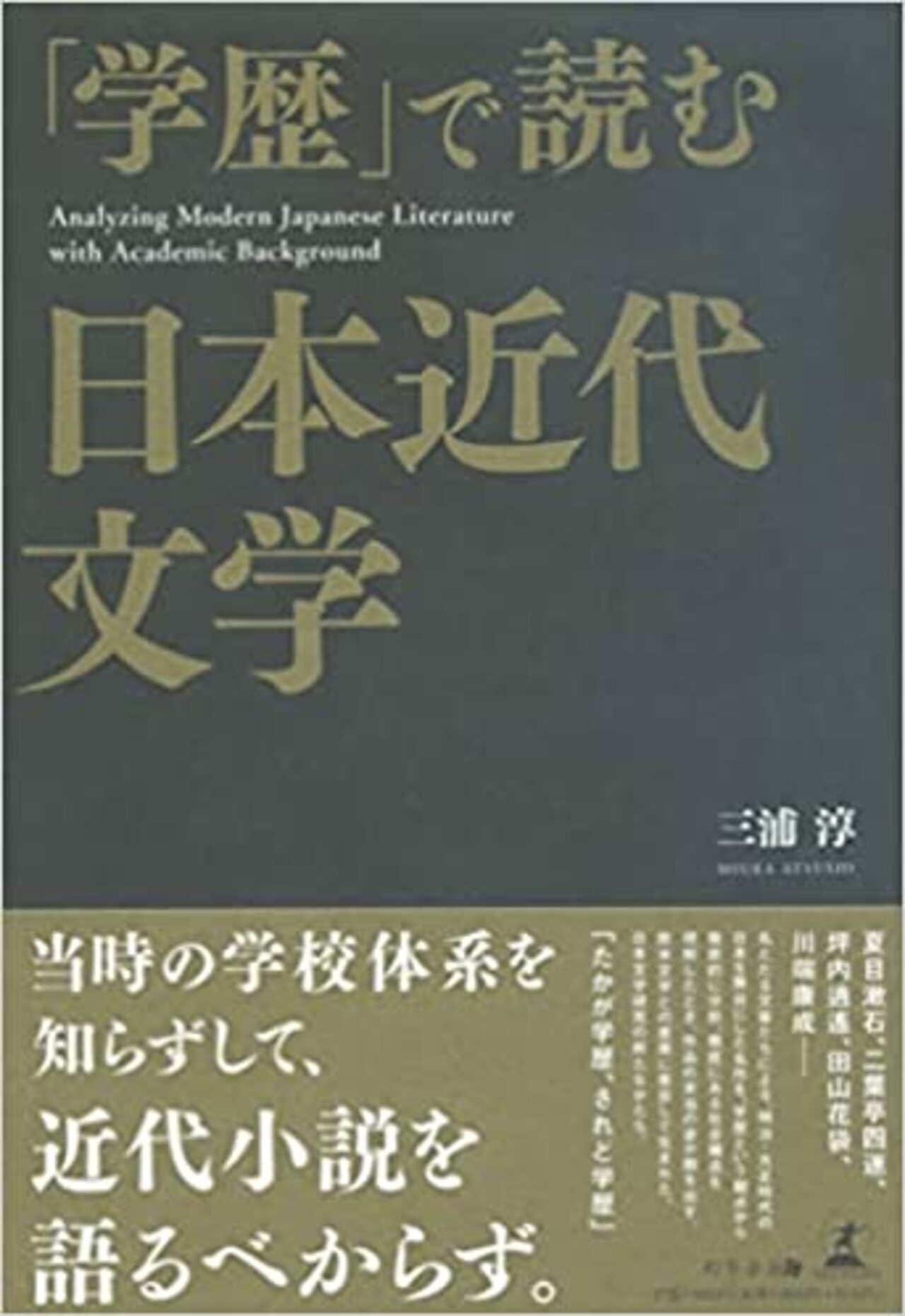【前回の記事を読む】学生の話なのに「学校」を描かない?『当世書生気質』が備えた近代小説の特質とは
第一章 日本近代文学の出発点に存在した学校と学歴――東京大学卒の坪内逍遙と東京外国語学校中退の二葉亭四迷
第一節 坪内逍遙
■『当世書生気質』で今も読むに値する場面
以上の記述を読むと、明治期に生きた坪内逍遙が東京の遊学生だけでなく、先進的とされる英国の大学のマイナス面をもしっかり認識していたことが分かります。階級社会である英国に比して、階級性が薄い日本の大学のほうが学生同士は平等な付き合いができるし、貧富の差に関係なく勉学に励めば立身出世ができるのだ、というアピールを送っているとも読める箇所です。
なおこうした認識の出所ですが、“Tom Brown at Oxford”などいくつかの小説や自伝を読んでみれば明らかだとされ、書名も挙げられています。
小説“Tom Brown at Oxford”は、日本でも邦訳が出ている『トム・ブラウンの学校生活 Tom Brown's School Days』の続編です。“School Days”のほうはトム・ブラウンの高校(パブリックスクールの名門校であるラグビー校)での生活が綴られているのですが、“at Oxford”はそのトム・ブラウンがオックスフォード大学に進学してからの様子を描いています。(残念ながらこちらは邦訳がありません。)
ちなみに、こうした階級と学校との関係は英国だけに見られるものではありません。
「はじめに」で述べたように、フランスでは戦後になっても地方の労働者階級の家庭に育った若者が、自国のエリートコースは大学ではなくグランゼコールと呼ばれる学校であることを知らず、地方の大学に進学して、そのために苦労するという体験をしているのです。
また、第二次世界大戦期の米国大統領として有名なフランクリン・D・ルーズヴェルトは、すでにセオドア・ルーズヴェルトという大統領を親戚から生んだ名門の家庭に育ち、英国パブリックスクールを模した私立男子高校を経てハーヴァード大学に進みましたが、大学では同じ高校出身者が入る寮で暮らし、三食は寮でとり、付き合いも同じ高校の出身者か類似の富裕な学生に限られていたといいます。
一九世紀末から二〇世紀初頭のこととはいえ、一般に自由と平等の国とされる米国の一面がうかがえる話です。
つまり、欧米では階級と学校が密接に結びついている部分があり、明治期に生きた坪内逍遙はすでにそのことに気づいていたのです。また、『当世学生気質』に登場する書生たちはそうした階級性をほとんど感じさせないが故に、逆にこの小説は日本社会の特質を示していると見ることができます。
むろん明治の日本にあっても貧富の格差は厳然として存在し、進学の可能性を左右していました。(この点については本書でも第七章で検討します。)ただ、英国やフランスには単なる貧富の差に還元されない階級性があり、それは米国にも受け継がれているのであって、これに比べれば士族を鼻にかけた明治期の青年などは可愛いものだったと言えるのです。