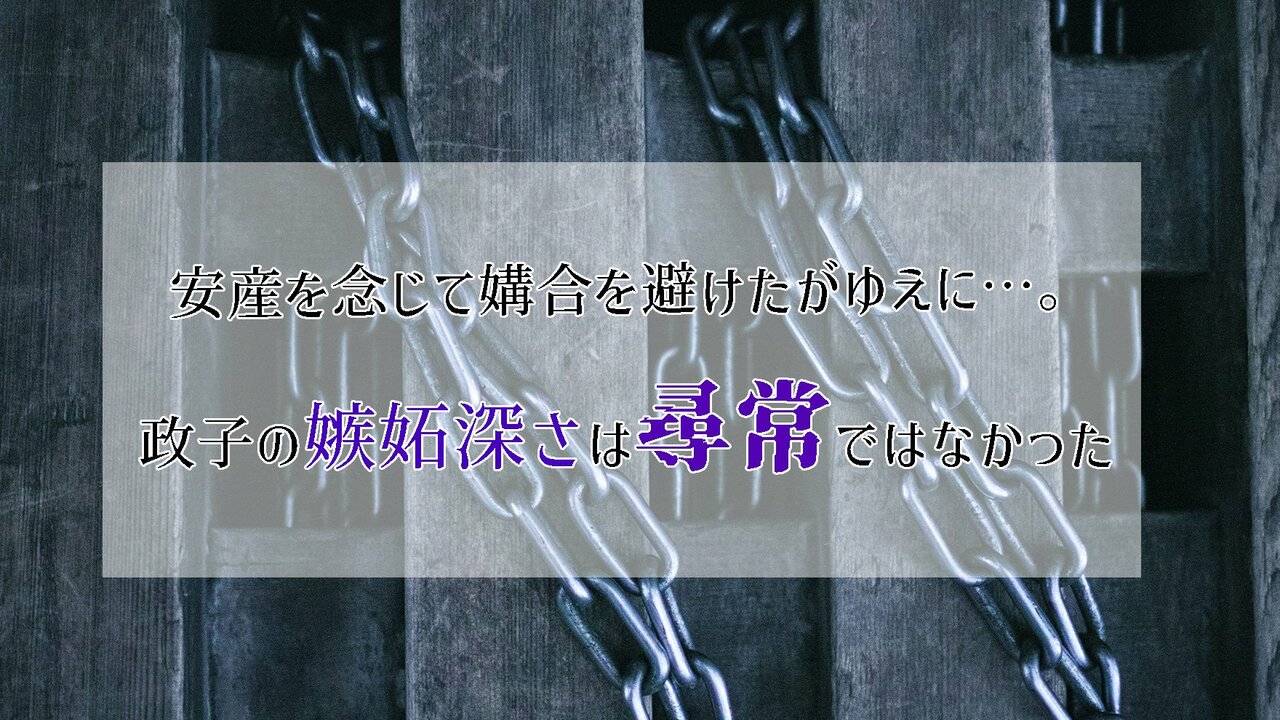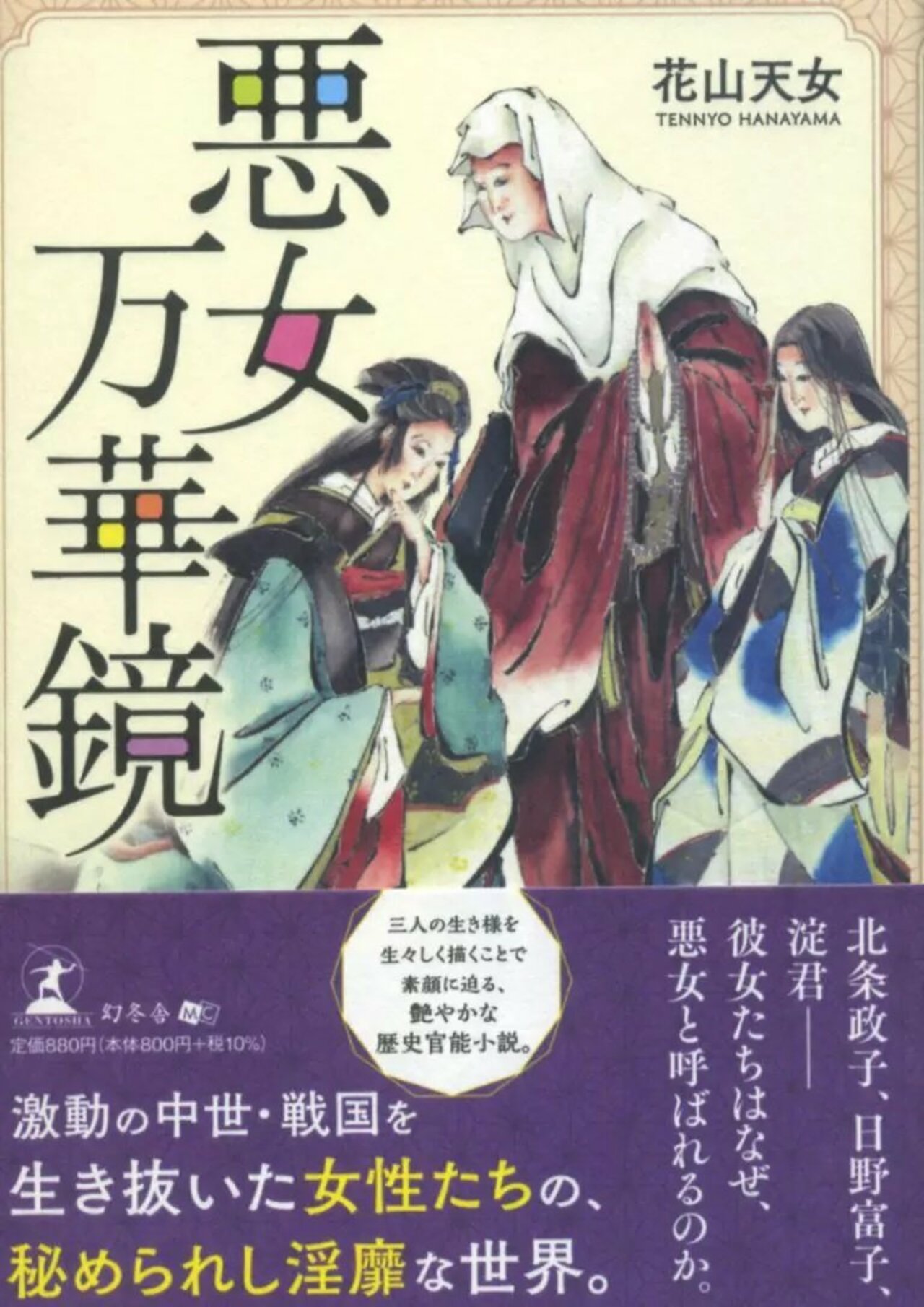第1部 政子狂乱録
三 亀の前の厄難
牢主は桜色に染まった女囚の花門に上気した顔を近づけて、赤褌の脇を僅かに広げてクンクンと香りを嗅ぎ、味わうようにチロチロと舌で触れてみると、これはどうしたことか、その入口からは透明な果汁が、強い香りを発して湧き出てきた。
吊り上げられた片足を揺らしながら、女は恥も外聞も打ち捨てた諦めの表情で、何故か政子に向かって花弁の開門を要求しているようにも見える。
牢主が、花門を飾る二葉の花弁の先をつまみ、左右に開いてみると、溢れるばかりに愛液で潤ったその内部は、幾重もの柔らかな襞(ひだ)がウネウネと騒いでいる。
「ここに佐殿のお道具を誘い込んだのかえ、なんと嫌らしいお部屋をお持ちじゃ!」
牢主は片手の指で、ぬかるんだ壺の内部を擦りまわした。
「ほら、こうしたらどんなにいい気分かえ、後でおまえの大好きなお方の張形で、たんと可愛がってあげるから、その前にその嫌らしいおソソが裂けないように、お道具にはタップリとお薬を塗っておいてあげますよ。
おお、なんて可愛いいお花畑ではないかエ、ついでに後ろの小さな入り口もいい子いい子しておいてやろうね、ほうら気持ちいいだろう、いい声で鳴いておくれ」
牢主は、切なげな吐息を漏らす女囚を抱き寄せ、白いうなじに唇を這わせ喘ぐ唇を舌先でこじ開けた。そして、その舌を吸いながら甘く潤んだ唾液を注ぎこみ、今度は極限まで肥大した花芯の先端に指で、ツツと軽く刺激を与えてみた。
「ヒイッ…… 滅相もございません。お許しくださいませ、そ、そんなことをされたら亀は死んでしまいます、死んで天国に逝ってしまいそうです。ああ、たまらない、おソソどころか躰まで溶けてしまう……」
頼朝とその側近たちが政務を執る大倉御所には、不始末の役人を取り調べたり、時には拷問を行う牢獄が設けられている。政子の懐妊中に、夫の頼朝の浮気に激怒した政子は、この牢獄に相手の亀の前を閉じ込めてしまったのだ。
密通は夫の懲りない漁色行為が原因で、女に責任があるわけではない。それでも嫉妬深さが尋常でない政子は、夫を詰るだけでは気が済まず、その矛先を女にまで向けずには収まりがつかなかった。