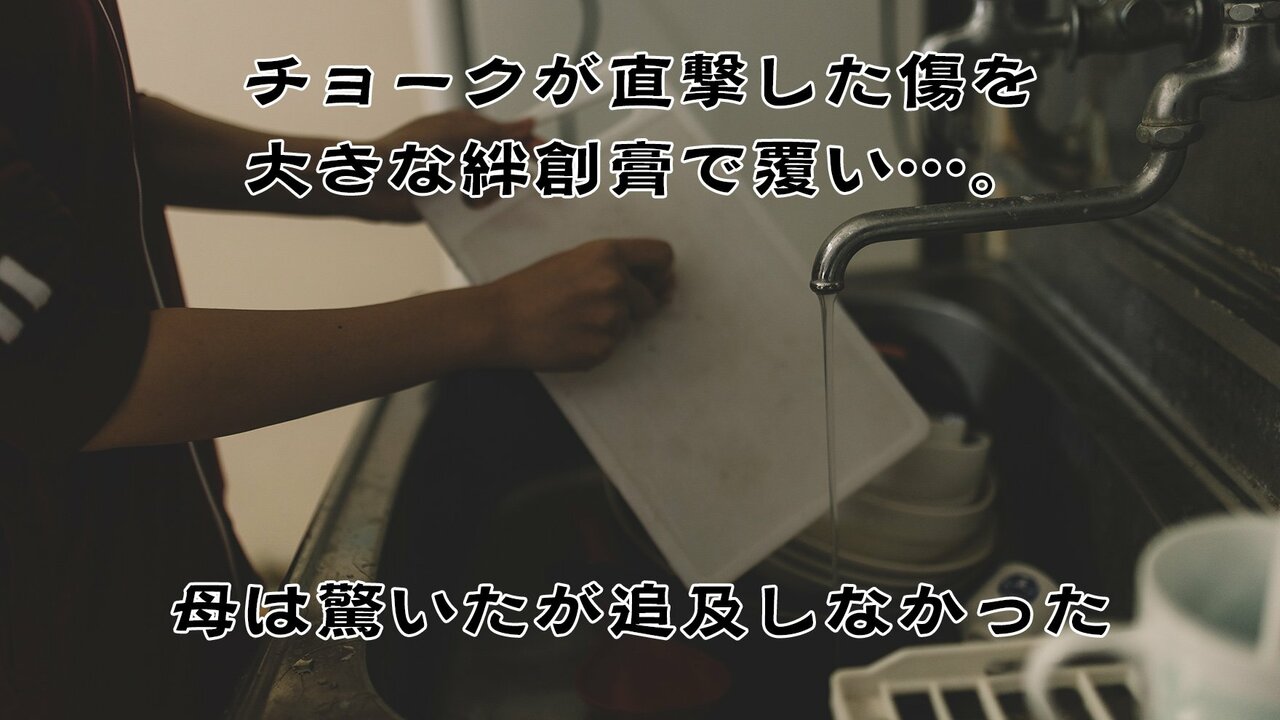校門の北側に自転車置き場がある。自転車通学は学校に申請しなくてはならない。台数は限られていて、学年ごとに綺麗に並んで隙間がない。自転車通学は申請しなくてはならない。その数は決まっているからどこかには入れるはずだが、一人でも斜めに入れたりしたら列は斜めに並んで遅れてきた自転車が一台はみ出す事になる。
そうなると、はみ出した奴は初めから自転車を真っ直ぐに並び直す事になる。そしてやっと自分の自転車を押し込む事ができるのだ。
だが、大抵は乱暴に突っ込んで終わるのだ。純太は自転車置き場の看板の、『真っ直ぐに止めてください』の『……い』あたりが定位置だった。
多少の雨でも自転車通学はやめられない。歩くとなるとゆうに三十分以上はかかる。
バスや電車で通学してくる生徒もいるから、そんな生徒たちに比べたら贅沢な距離だろう。だけど偏差値より何より楽に通学できる高校を純太は選んだのだった。
自転車置き場から自分の自転車を出した。音楽室からかすかに吹奏楽部が演奏する音楽が聞こえてくる。綾乃が所属している吹奏楽部はこの夏のコンクールに向かって休みなしの猛練習中だと聞いていた。
その音色と共に綾乃の顔がチラリと浮かんだ。
校舎を出て家に向かったが、途中、自転車をいつもの曲がり角を曲がらずに駅前のコンビニまで真っ直ぐ走らせた。コンビニの前で自転車を止め、少しあたりを見回した。知っている顔はなかった。
カバンの中から黄色いシミの付いたパンツの入ったビニール袋を引っ張り出すとコンビニの前に置かれているゴミ箱に投げ捨てた。ここまで良く誰にも見つからないで来たものだ。
純太は一刻も早くこの災難の種になるかもしれなかった物とおさらばしたかった。家まで待てなかった。それに、家のゴミ箱に捨てて、万が一母親にでも見つかってまた新たな火種になる事は避けたかった。
純太は学校での出来事のあれやこれやを親に話す事はない。まして、息子が「いじめ」を受けているなんて事を知ったらどんなに傷つくか想像できる。純太は親の悲しみまで受け止められない。
「よう、前田」と声をかけてきた奴がいた。どきっとして振り返ったら同じクラスの荻原健太だった。教室ではあまり目立たない存在の奴だし、話もした事がなかった。そんな荻原が親し気に声をかけてきたので二度驚いた。
「俺、これからバイト」と聞きもしないのにそう言った。
「バイト、学校で禁止されているだろ」
「ああ、でも、見つからなきゃ良いんだよ。他にもやっている奴いるぜ」
荻原はその何人かの名前を挙げた。そして、
「俺はさ、お前に同情するよ」と突然言い出した。
「山田紘一、榊原直人、土屋孝輔、三上アキラ、あいつらやばくね?」
アキラたちの名前を指で数えながらフルで名指しした。