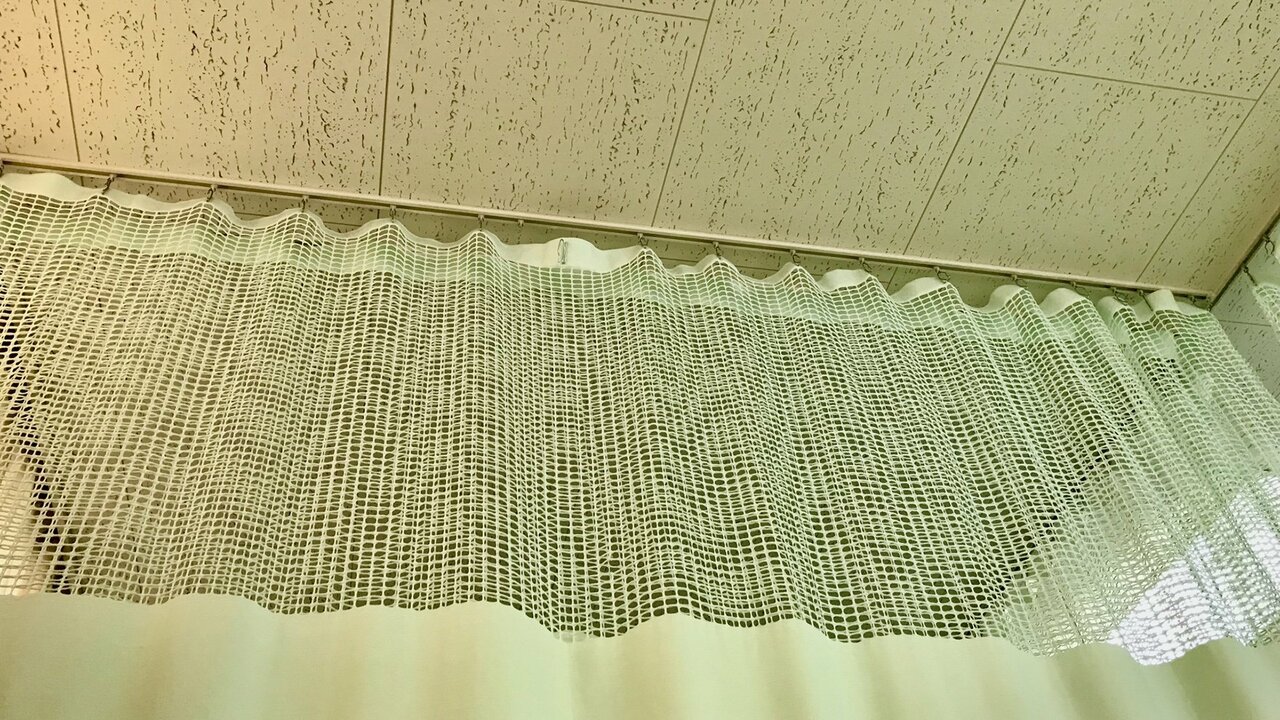八百床ある音原大学附属病院、ふたつの大きな建物で形成されている。
ERには、毎日さまざまな患者がかつぎ込まれてきた。交通事故による内臓破裂、くも膜下出血、急性アルコール中毒、フグなどによる食中毒、飛びおりによる外傷、刃傷沙汰による刺傷、食べ物が喉に詰まったことによる窒息状態、心肺停止、川や海での溺水、リストカット、火傷、衰弱した浮浪者、首吊り、そしてオーバードーズ(薬の大量服用)……そうした患者を三途の川の半途からこちらへつれもどさねばならなかった。
毎日が戦場だった。リハビリ科とは業務内容が異なるせいか、久仁子は仕事を覚えるのに苦労した。ベテランで意地の悪い看護師からは“使えない医師”とばかにされたりもした。
それでも研修医にまじって歯を食いしばって日々自分にやれることをめいっぱいやり、久仁子は救命医としての腕をめきめきと上げていった。頭がぱっくりと割れた患者や心肺停止しているような患者を前にしても、うろたえなくなった。医師としての力量が評価され、三年前から医局長がいないときは現場のチームリーダーを一任されるまでになった。
久仁子の心はふたつの意志に支配されていた。「ここで私がとことん働いて、さとるのような患者を二度とださない」という気持ちと、「患者を救わなければ、さとるは成仏できない」という思いである。ひところは無気力に支配されていた心も、鋼のように強くなった。
何日も徹夜で治療室にこもり、いまが昼か夜かもわからない状態で、何かに憑かれたように、ひっきりないにやってくる患者の治療にあたった。
まわりから働きすぎだと言われても、むりをつらぬいた。全身全霊で患者を助命すること。それだけがこの世を去ったさとるへの贖罪であるように思われた——。
「ふうーっ」
久仁子はパジャマ姿で、ため息をついた。
ピーポー
ピーポー……
遠くでサイレンの音がした。救急車だ。音の大きさから察するに、すでにこの病院の二百メートル手前あたりまで来ているようだ。
ベッドから起き上がった久仁子は窓ぎわのカーテンを横に引いた。
外はすでに暗くなっていた。しかも、ここは建物の三階。病棟の個室のようだ。連日のオーバーワークで倒れたのかもしれない。何も覚えていなかった。
眼下にひろがる光景を、久仁子はながめ渡した。