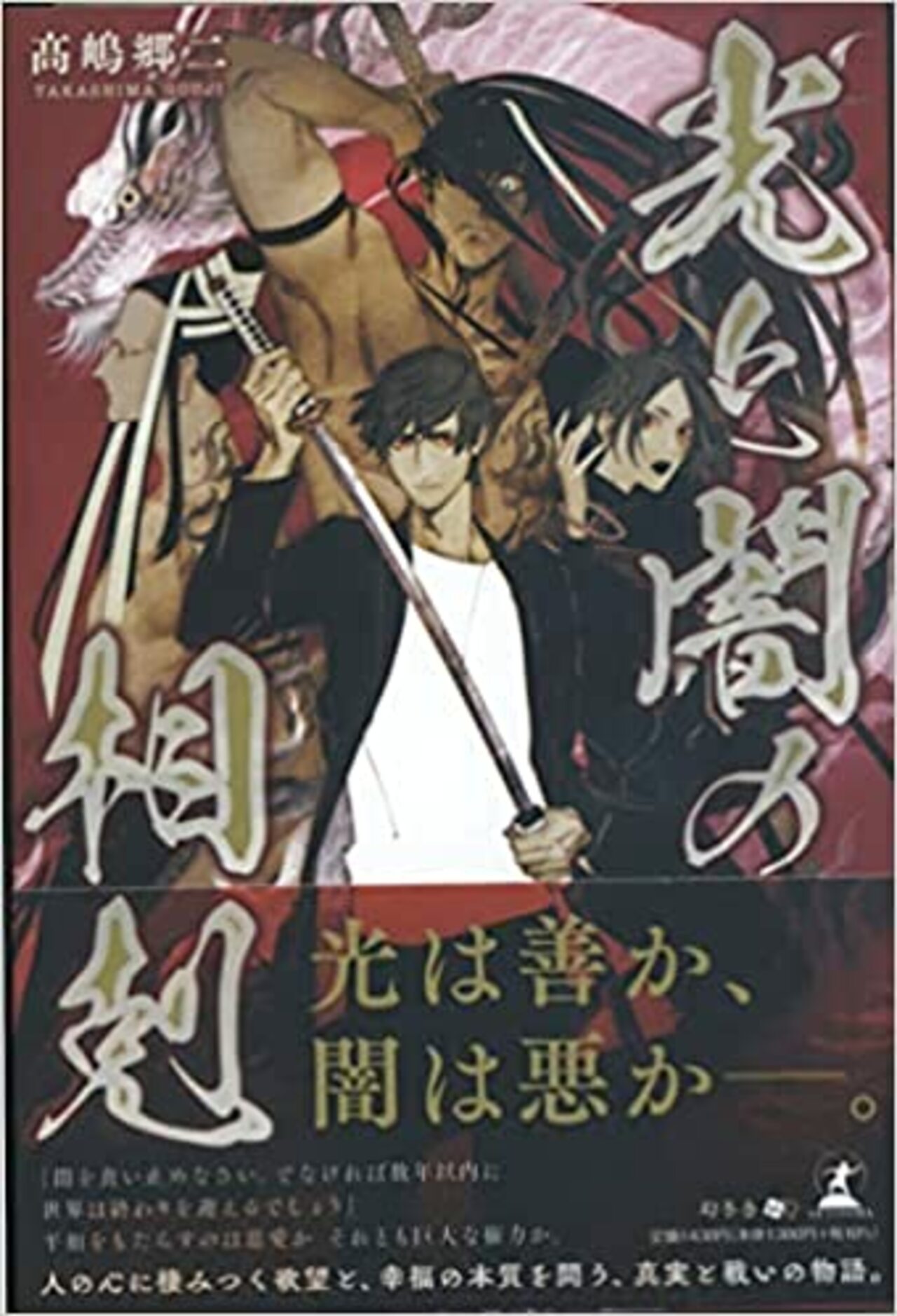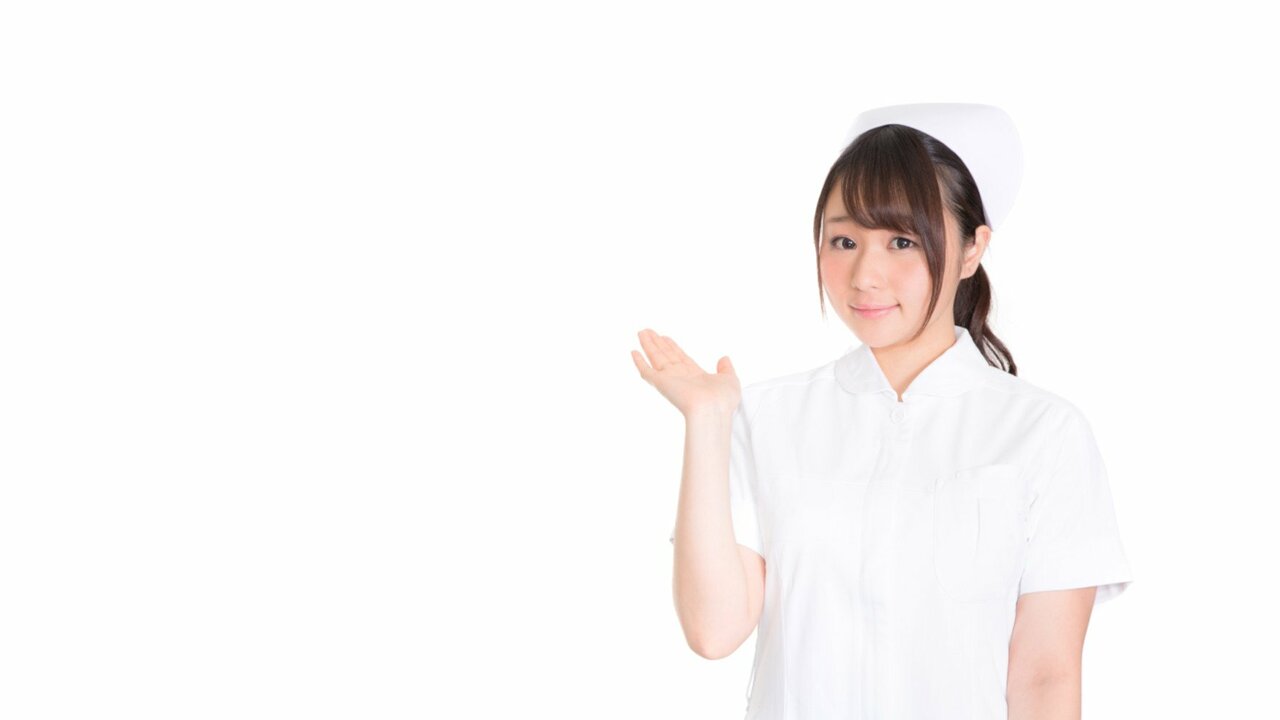長い夢
旭川の春の陽光は柔らかく、頬を伝ってくる風に季節の変わり目を感じる。窓から部屋へ入ってくる風も嚆こう矢し のごとく冬の空気を春へと変えていく。風はその土地の独特な匂いを運んでくる。旭川の街にも独特なものがあり、英良も旭川の匂いを感じた。春の空は碧く、上空から鳥の鳴き声が聞こえてきた。
ピヨピヨ、ピヨピヨピヨピヨ……。
遥か上空を見上げると小鳥が見える。ヒバリだ。英良はその情景を見て銘肝した。必死に生きようとする意志を感じて心打たれながら頑張れ、頑張れ、とひたすらヒバリを鼓舞した。ヒバリも英良の言葉に応えるように懸命に飛んでいる。ピヨピヨピヨピヨ……、英良は吸い込まれるようにヒバリを見ていたが、ヒバリは暫くして遙か遠くへ姿を消した。
英良は玄関のドアを開け、郵便受けに差し込んである朝刊を取りに行った。外からは油圧ショベルカーが動く音が聞こえてくる。現場監督作業員らしい中年男性が大声でショベルカーの運転手に何か指示している。運転手は聞き取れなかったのか、エンジンを止めて、指示内容を改めて聞いていた。お互い大声で話していたが、英良には詳細が聞き取れなかった。
近所の顔見知りで四十代の女性がゴミ袋をさげて歩いていた。彼女は年の割に若く見え、髪はショートカットでハイヒールのサンダル履きで腰はくびれ白いブラウスに黒のタイトスカートを穿いていた。化粧はしていなかったが十分、佳か 人じんといえる。目が合ったため英良の方から「おはよう御座います」と挨拶したら、彼女はにこりと笑い頷いた。
世の中には色々な人達がいて、多種多様の仕事がある。絶対的なものは何一つ存在せず、周りと比べて自分はどうなのかという相対的な事象の集まりのようなもので英良も相対的なものとして対象の存在といえる。普段通りの生活が長い時間軸の中でゆっくりと進んでいく。それは止まることのない普遍的なものだ。
英良はタクシーのドライバーをしていたが、今日は非番だった。朝刊に一通り目を通し、テレビのワイドショーを観ていた。朝食は取らず、コーヒーをいれ牛乳で割りカフェオレを作り飲んだ。
昼も過ぎ、空はだんだん雲が出てきて春の陽光も遮られてきた。部屋の中も少し薄暗くなってきた。英良は眠気を感じベッドに横になるとすぐ深い眠りについた。身体がベッドの下の方へ沈んでいく。睡魔が襲ってきて脳が痺れ、黒い影が目の前を横切っていくのを感じた。