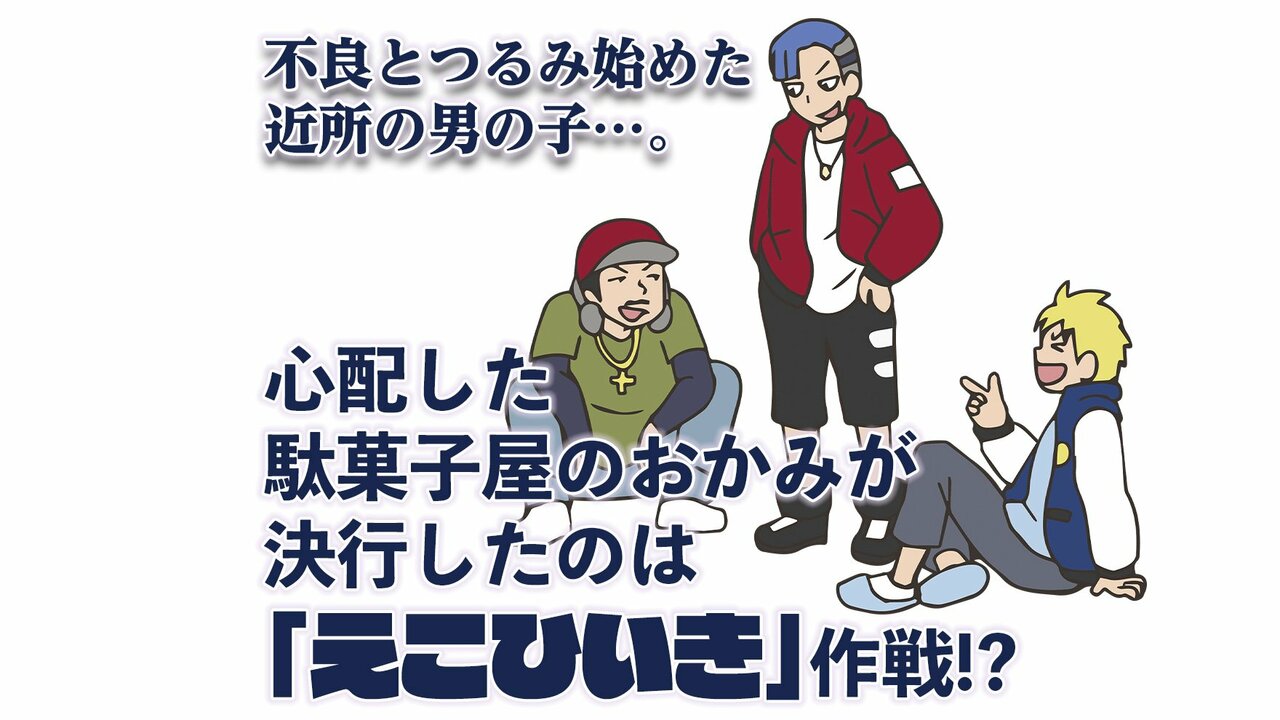第一章
一年一組
咲いていた桜はとうに散って、代わりに並木道にはみずみずしい緑が占めていく。僕が高校に入学してから一か月が経った。今日は友人たちと下関市の市街地を歩いていた。開催されていた祭りで街中がいつもよりにぎわっている。
「どうですか、翼さん、数年ぶりのこのフェスの雰囲気は」
大手を広げるお調子者の友人に笑い返す。
「はいはい。楽しませていただきました。ありがとうございました。ですが、危ないので、前を見て歩いてくださいませんかね」
祭りの中心地から離れたとはいえ、人通りが多い。
「貴様、礼がなっとらん。今日、このセッティングはお前のために用意したと言っても過言ではないのだぞ」
僕の忠告は守りつつも腕を組み、大仰に頷いている友人につい笑みがこぼれる。
「いや、申し訳ない」
僕は軽い調子で頭を下げた。
「そうだ。それでよいのじゃ。お前さんが下関を発ってから、はや、あれ。何年たったっけ?」
芝居を解いてくるっと振り返ってくる。その背中を押して、正面を向かせる。
「八年くらいかな。小学校一年の途中で転校したからね」
「そうだよ。ほんと意味分かんないよな。まだ一年生だったんだぜ。制服さ、一年も着てないんだよ」
下関市の小学校は市立でも制服がある。東京に転校することになって、テレビで憧れた私服の学校生活に喜んだ。けれど、すぐに面倒になって制服で過ごした一年にも足らない生活を懐かしんだ。
「いや、それにしてもいじらしいですな」
「何が」
僕には友人が何を言いたいのか分かりきっていた。とぼけたふりをして、街を見やる。僕のいない間、街は変わっていた。友人も成長していた。僕も、あの子も。
「翼さんが、その長い間、片思いをずっと引きずってらっしゃるなんて」
平常心を保とうと横でニヤニヤ笑う友人に気付かれないよう、深呼吸した。
「いいんですか。だんまりなんか決め込んで。今日宮園さんを呼んだのは他でもない、この俺ですよ」
あの子の名前を出されてドキッとする。この友人秋吉は僕の想いを知っていて、今日宮園を誘ってくれていたのだ。
「はい。秋吉様。ありがとうございます。一生ついていきます」
「分かればよいのじゃ。分かれば」