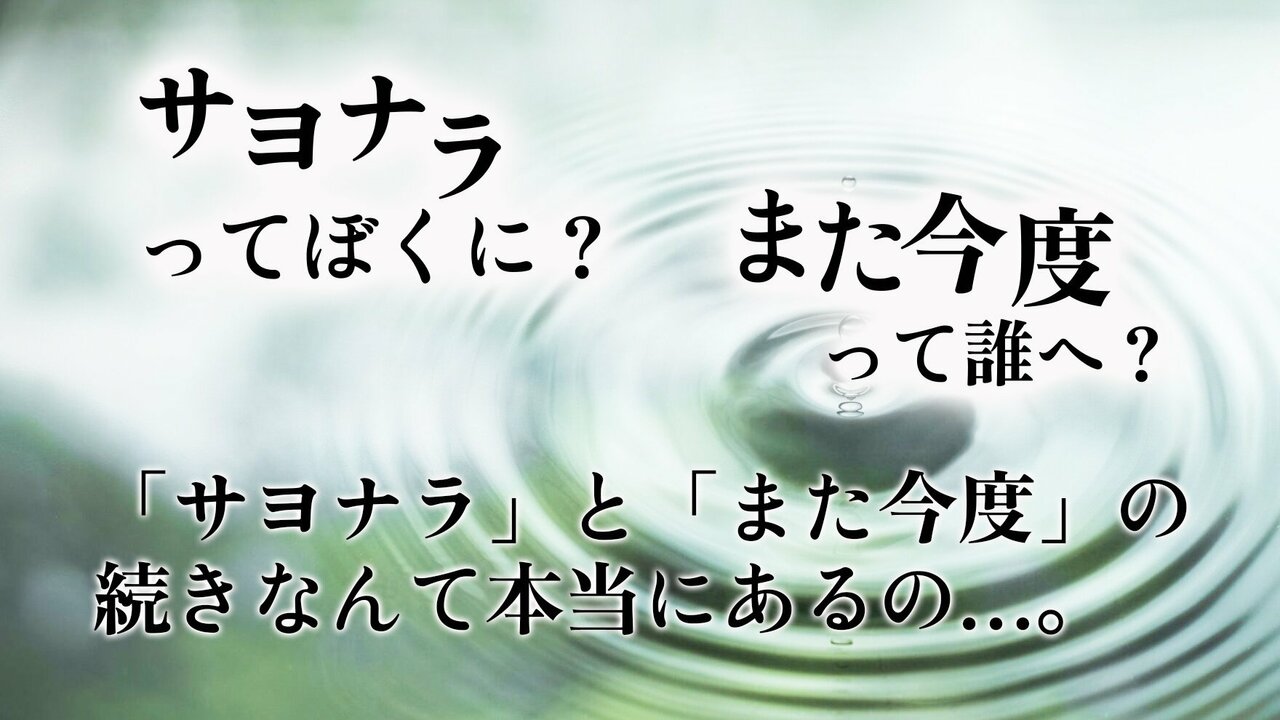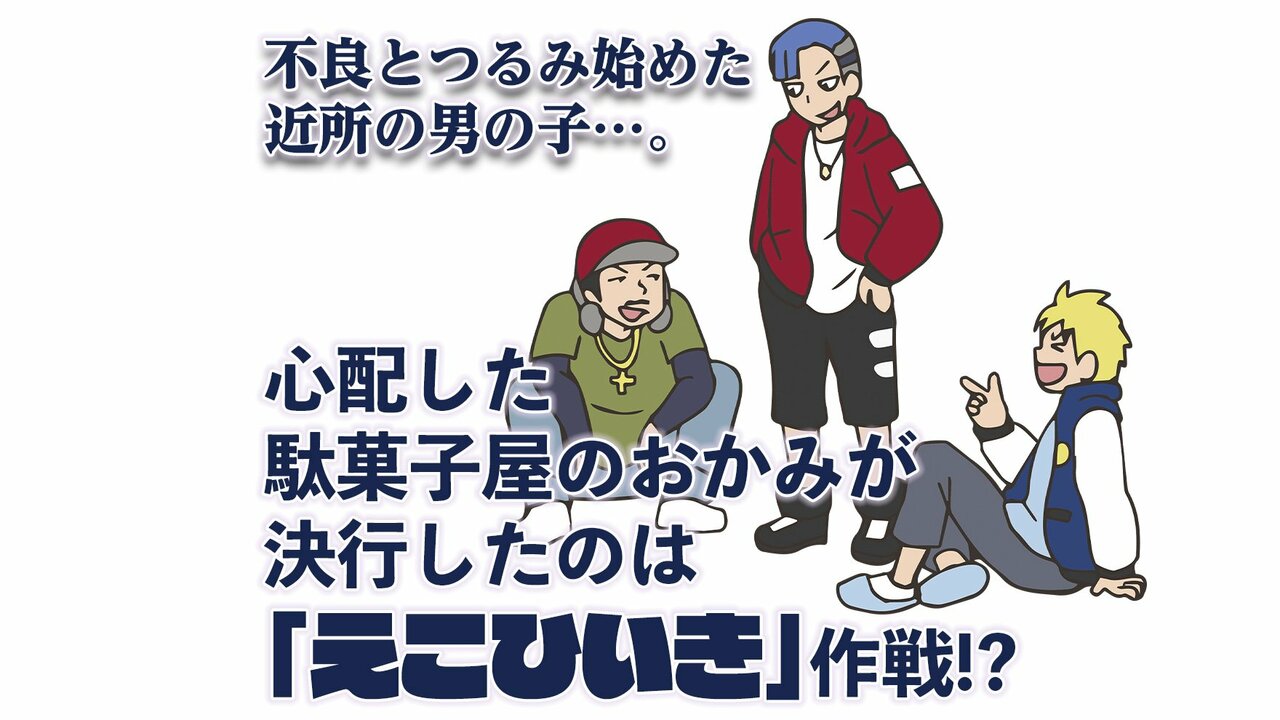ひとしずくは、兄弟たちのからだを透かして、もやもやとした視界の彼方から、橙色の光が優しくこちらを見つめていると感じることがありました。この橙色の光の正体、これは私たちにとっての太陽に違いないのですが、何も知らないひとしずくにはまだ秘密にしておきましょう。
とにかくそういうときは、兄弟たちはみんなにこにことして心から嬉しそうでしたので、つられてひとしずくもとても温かな気持ちになりました。
一度だけ、雪の結晶の兄弟たちのからだが、太陽の光を透かしてきらきらと虹色に輝いていることがありました。その姿を不思議そうに見つめるひとしずくといったら! 何て美しいんだろう。幼気なひとしずくは、ただうっとりと見とれていました。
光の束が過ぎ去って、雪の結晶の兄弟たちが真っ白い元の姿に戻ってからも、ひとしずくの心はあの虹色の光に夢中でいました。ぼくもいつかあんな風になれるのかしら。そう思ったら、小さなからだがはち切れそうなほど期待が大きく膨らんで、あちこちくすぐったくなりました。
ひとしずくには、これから先に待ち受けているすべてのことは、何もかもが楽しげで優しいものに感じられました。このような予感を誰かれに話して、一緒に歌いだせたらどんなに楽しいことでしょう。
いえ、本当は私たちには聞こえなかっただけで、空気の振動よりずっと小さな声で、彼らは絶えずおしゃべりしていたのです。といってもそれは、「嬉しいね」とか、「楽しいね」「暖かいね」といったことばをそれぞれつぶやいて頷き合うような、緑児のように他愛ない会話でありました。
しばらくのあいだ、ひとしずくたちはぽかぽかと温かな、夢のような時間にいました。けれどほどなくして、ほろほろと聞き慣れぬ音が聞こえてきました。かすかにゆられてもいるようです。それは、クマザサの葉の上に降り積もっていた雪が、春の陽の熱によって、少しずつ溶かされる音であり、雫となってぽたぽたとこぼれるときの振動が彼らに伝っているのでした。根雪であったひとしずくと兄弟たちがいるあたりには、太陽の決定的な熱はまだ届いていませんでした。
それでもこの変化の予兆に気が付かぬこはいませんでした。なぜなら、彼らもまた、からだの内からフツフツと熱が沸き上がってくるのを感じていたからです。