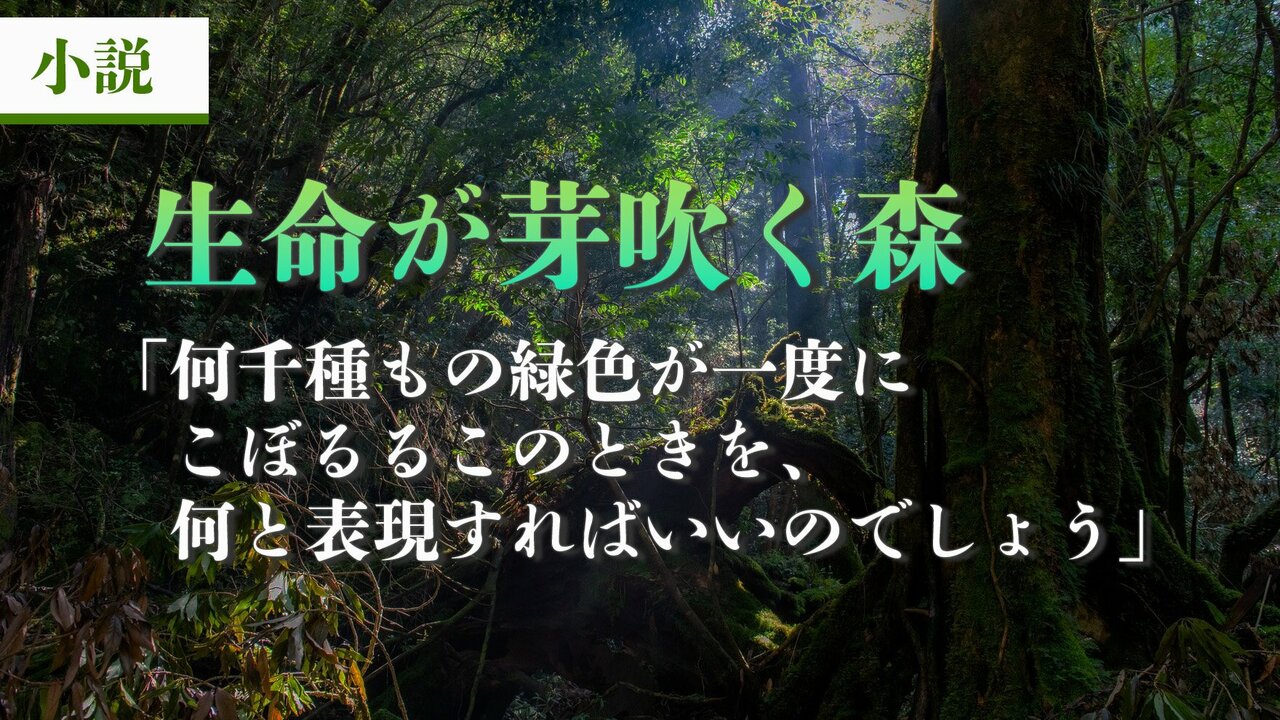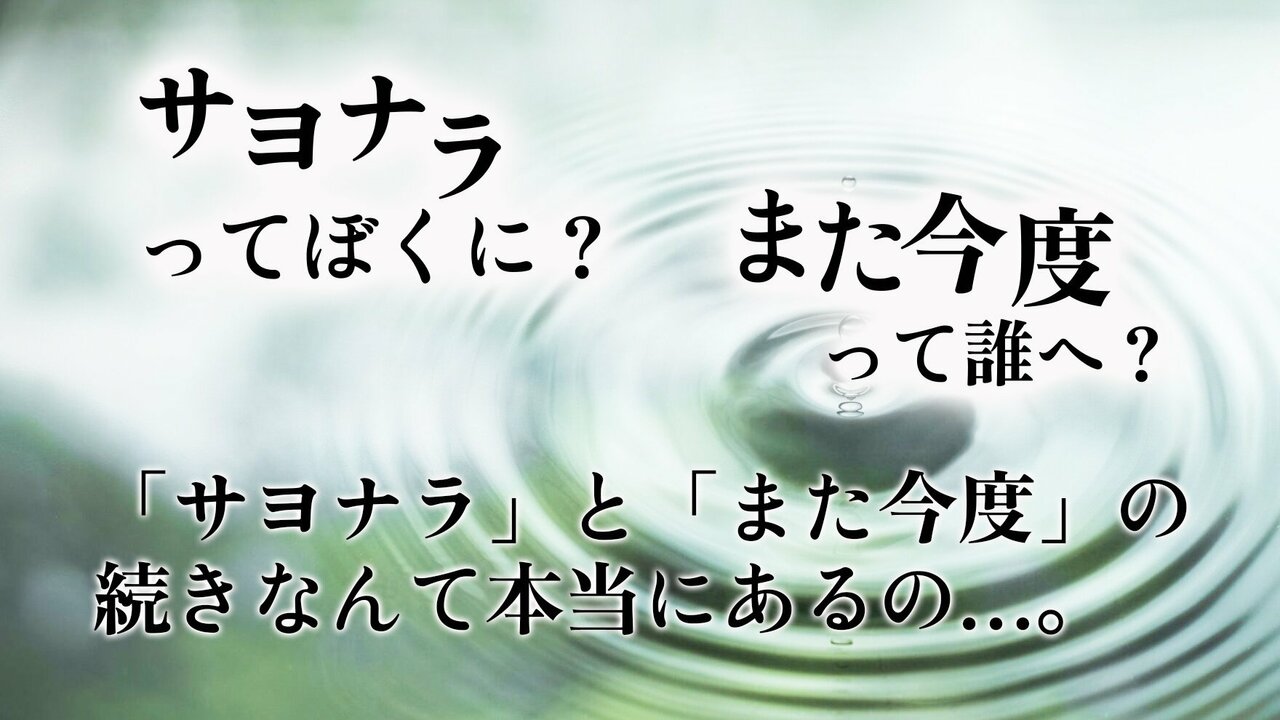ひとしずく
長らく巨大な陰の下で過ごしてきた若い草木や種たちは、太陽の光をひねもす一身に浴びることができる興奮ともたらされた幸運で心がいっぱいになり、ほてったからだを森林の澄んだ空気で冷まします。ところがその空気までもが彼らの悦びにふれて鴇色に染まってゆくのです。
草木や種は呼吸を強かに、根の先から天へ、からだのすみずみまで命の水を巡らせます。そうしてあるとき、風が凪ぐ穏やかな日和を待って、いっせいに生命を放ち、芽吹くのです。
何千種もの緑色が一度にこぼるるこのときを、何と表現すればいいのでしょう。それは、ただただ圧倒的に、生命の色彩という他ありません。これでもまだ、ことばが足りぬくらいです。
ところが森たちは、こうした美しい悠久のすべてを人間には決して見せ尽くしてはくれません。自然だけが秘匿できるこの時空間こそ、今では彼らの矜持だからです。こういうとき、あの美しい瞬間を目の当たりにできる生物たち、鹿やモグラ、キツツキやゾウムシ、ヤスデなどがどれほど羨ましいか知れません。

この物語の主人公、ひとしずくの話に戻りましょう。このひとしずくも、七色の陽光と何千種もの新緑色と潤んだ湿気がおどり戯れる美しい時間のさなかに生まれたこでした。
早春のある朝。遠く、山の彼方に太陽がのぼり始めます。藍色の森に曙色の光の束がさっとひと刷け射しこんで、鈍色の朝霧に溶けあい混ざりあい、紅、黄金、瑠璃群青、そのどれともいわれぬ色のあわいが揺蕩う朝。誰の目にも留まらずとも永遠にくり返されてきた美しい朝です。
「いつもであればまだまだ薄暗い肌寒さが続くはずなのに。どうしてだか、今日の冬はもうぽかぽかと暖かい」
春の朝陽は森の奥へと進むにつれ、少しずつ先細ってゆき、ただひとすじの光となって、一本のクマザサにそそいでいます。眩い曙色の光線は森の奥深くのひんやりと澄んだ空気にふれ、まもなくうす紫色になり、やがてやわらかな銀色の光に変わっていました。ここらの生物たちに、春の訪れを告げるには大変好ましい、聡明で優しい朝の光です。