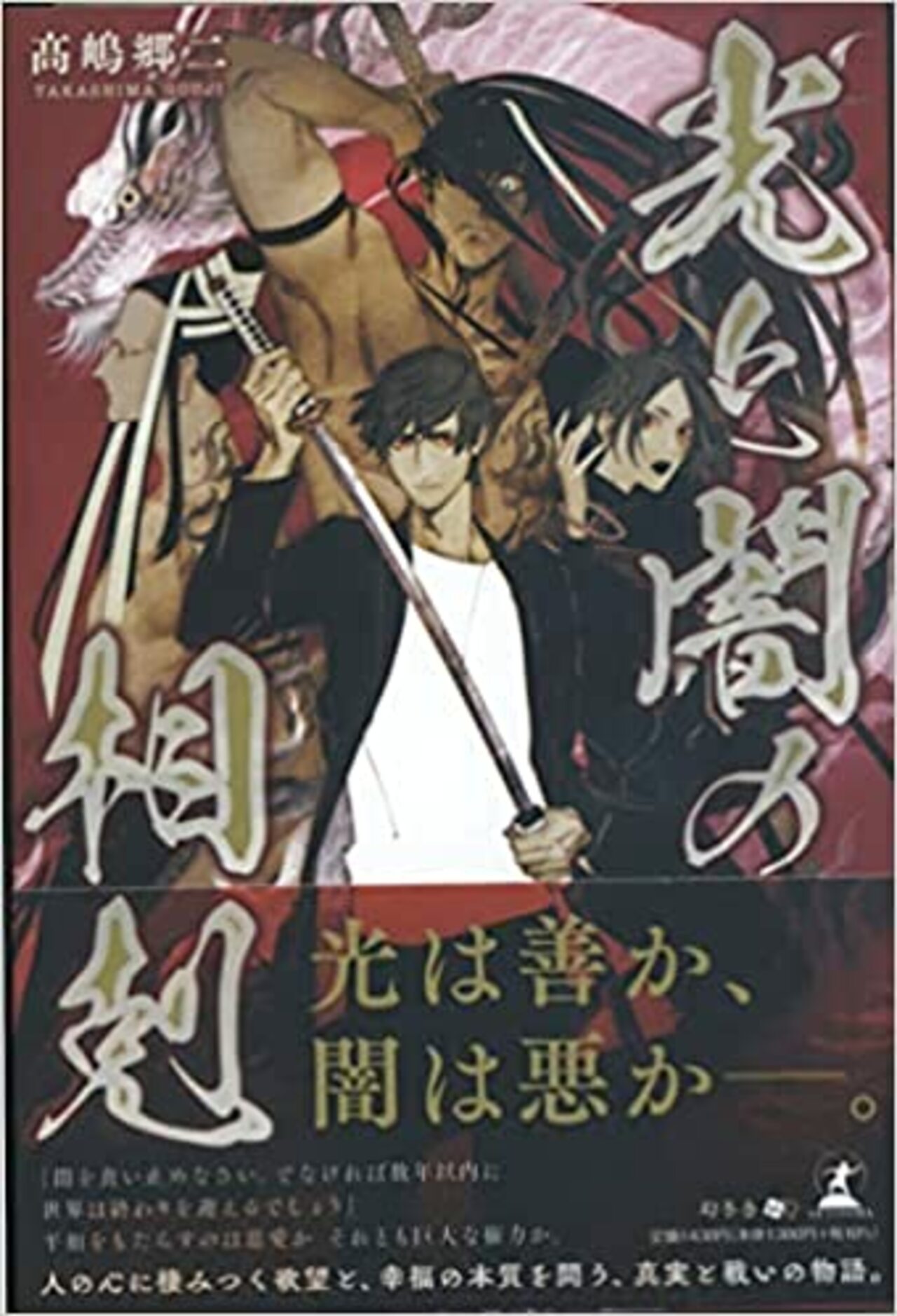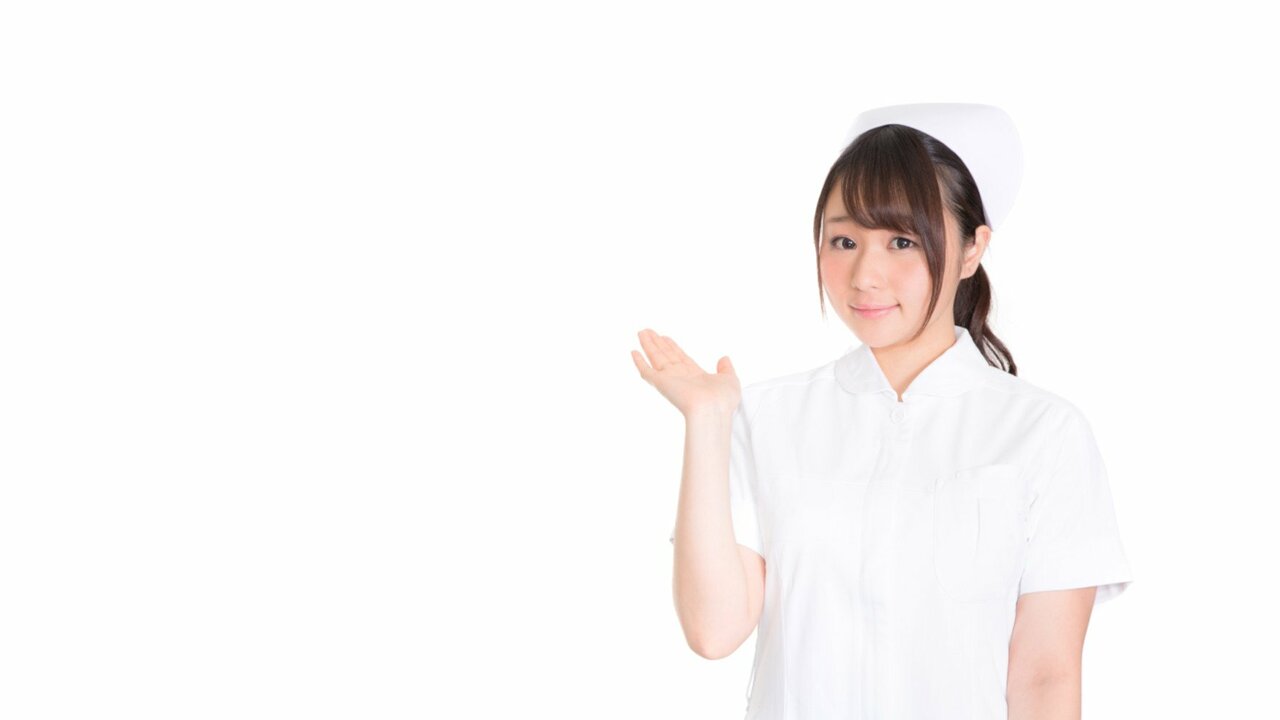序章
英良は幼い頃、両親と夕食を取るために繁華街を歩いていた。狭い小路を抜けると正面に「銀座一丁目」と赤い看板に黒い文字の入ったアーチが見える。それは英良達を見据える大きな鳥居のように見えた。途中の電気店からは運動会の時に使う拡声器のようなものから『ローハイド』の曲が流れていた。
会社帰りの中年の男性は電器店の店頭にあるテレビ画面に映る映像にずっと見入っていた。周囲の人は同じような仕事帰りの背広姿の人や学生……忙しそうにしている人や……家族の笑顔がある。所々にゴミを入れる大きなプラスチックのバケツがあり、まだ薄暮の中、カラスが一羽周りを小さく飛び跳ねている。英良が側を通ってもカラスは逃げようとせず少し移動した。
歩道のある部分には大きなシミがついている。ファーストフードの包み紙やドリンクの空きコップも散乱している。五十代の男性と二十代の若い女性が腕を組んで歩き、女性は至福の様相で男性の肩に左頬をつけ何かささやいている。まだ幼い英良の目にはその光景が日常を逸脱した光景に感じられた。
英良と両親は中華料理屋に入った。テーブル席が六カ所と小上がりに四人掛けのテーブルのある昔風のひなびた食堂だった。室内の奥には二十型のカラーテレビが台座に載せられて天井近くに置かれている。テレビの下には白い菫の花がオレンジ色の洋なし型の花瓶に不釣り合いなまでに生けられている。
五十代の女性の従業員がグラス三つに水を入れて持ってテーブルの上に置く。父と母は味噌ラーメンと餃子一皿を注文し英良はチャーハンを注文した。英良のテーブルの左斜め向かいの四人の客(作業服を着た仕事帰りの客)はビールを飲んで談笑し、時折甲高い奇声をあげて今日の出来事や家族のことを話している。
隣のテーブル席にはどこかの大学のロゴが入ったスタジャンを着た四人組がホルモンを焼いている。彼らは何もしゃべらず焼けた肉とビールをひたすら口へ運んでいく。店内は厨房からの湯気と油が混在した空気で充満していた。外からはバイクの排気音と遠くから聞こえる車のクラクション、それに数人の大学生達の大声が聞こえてきた。
テレビではニュース番組が始まり、中東の反政府軍の抗戦と破壊された市街地が映されている。英良達が入った後にも数組が会計を済ませて退店し、店内は四割近くが空席となった。今も地球のどこかでは戦争が続き日本では平和な日々が続く。人間は不思議な不公平感のもと、どちらかに属し、英良はまさに平和なところに属している。
英良は両親と三人でテーブル席に座ったが、向かい側の壁に掛けてあった「般若」の面が幼い英良の目に入ってきた。それは今生には存在しない顔であり、その顔からは憤懣やるかたなさ、恨み、妬み、悲しみ、苦しみ、他者を陥れる雰囲気を感じ、英良は両手で顔を隠した。
それは争いごとに巻き込まれた人々が放つ負の感情の連鎖の波動のようで英良は「般若」が作り出す空間に意志、想念、負の力とは真逆の自分の力全てを吸い取られていきそうな気がした。