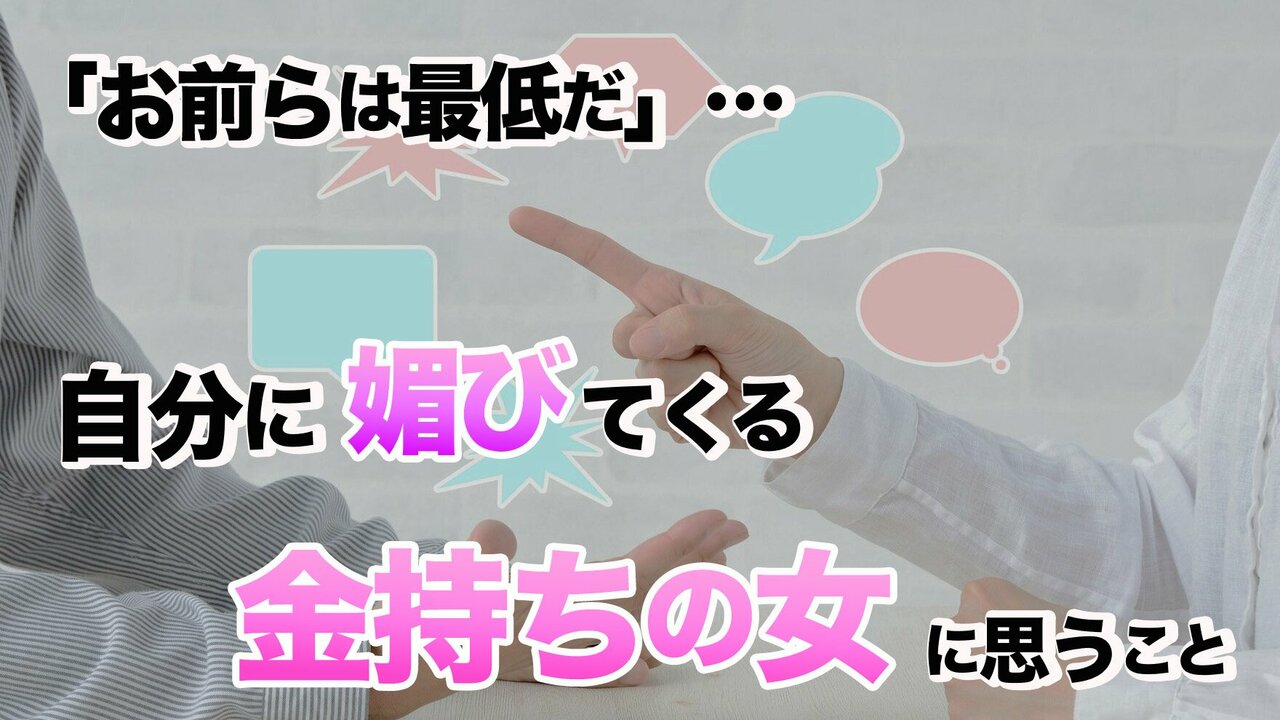りょうの絵本
海水が重い。何かブレーキをかけられたみたいに上手く進めない。これは歳のせいでも身体のせいでもない。あいつの、渡辺のせいだ。のしかかってきそうに重たい雲が空を覆っている。その空を映した薄黒い波がゆっくりと大きく盛り上がり、押し寄せてきた。波に乗ると崩れるように揺れた。今日は波が荒い。気をつけないと沖へ流されそうで、あたふたと岸を目指す。
ばかばかしい。気持ちが凪いでいる時は死んでもいいと思うくせに、気持ちが荒れる時は死にたくないと思う。反対だろ。新村の言う通り、俺はマゾか。生き方下手にもほどがあると、自分に腹が立つ。
いつものように水から身体を引き剥がす気分で陸に上がり、いつものように砂浜を歩く。なんちゃあないの老婆はいなかった。
ふいに、あの老婆は本当にいたのか不安になる。景色が、現実が、入り込めない絵のように思えて自分の居場所が掴めない。外への違和感が始まった。いわゆる神経症というやつですね。父の言葉がよぎって、溜め息が出た。
松林が切羽詰まった蝉の声を集め、夏の日を遮って続いている。まだ夏だ。あそこにも夏があった。あれからたくさんの夏が生まれ消え、これからも繰り返し夏が来る。
総て繰り返して終わらない。それに腹が立つ。
松林の中に廃屋のような家がある。あそこに海辺で会った老婆が住んでいる気がするのは、あの家が老婆のうずくまった姿に似ているからで何の根拠もない。
近づいてみると、潮の匂いに混じって家から微かに朽ちていく匂いがした。ふいに記憶の中の大陸が蘇ってきて、軽い吐き気がした。中を覗くと、それでも畳らしき形があり、崩れかけた机があり、奥は台所だったんだろう、ガラスのない窓枠があった。
台所の台にはぽつんと一つ鍋がある。煮炊きし、ここで生きた人間がいた。この家を捨てたのか、この家で死んだのか。死にたいと願う友人は年賀状に「死ねました」という文字を書けない。喪中のはがきでしか、あいつの死は分からない。あいつは望んでいた死を語れない。
死ねませんは使えても、死ねましたという言葉をあいつは永遠に使えない。それがとても理不尽な気がして、また、腹が立った。
開けた木戸が、今日は耳障りな音を立てる。広がる庭に目をやり、横の風呂場でいつものようにシャワーを浴びる。昨日と同じように、萎びた皮膚の上を水がこぼれ落ちていく。身体は廃屋みたいに朽ちていくのに怒りは朽ちないらしい。
今、書いている脱獄犯の主人公のように本能だけで生きれば、楽なんだろうか。楽も手に取れば退屈に変わるか。あの主人公は最後に捕まった時、「もういいかと思った」と言った。
自由になりたくて外に出たが、外にも自由はなかった。自由を諦めて、ようやく自由になったということだ。
彼の人生に勝手な解釈をつけ、自分は嘘っぱちの脚本を書く。自分の人生にも、自分なりの解釈でストーリーを作り、それを真実と思って、生きている。真実なんて解釈次第。人の数だけあるのだ。思い切り強くシャワーを浴び、思い切り強く身体を拭いた。
りょうは仕事をしているらしく、部屋から出て来ない。丹精込めてりょうが磨いた、塵一つない廊下を歩く。ここは人の気配まで掃いて捨てたような廊下だとまたイライラする。
りょうのお気に入りの自然木の欄間がある。波の形に似ている。盛り上がろうとする一瞬の波か、崩れようとする一瞬か。今日は崩れる直前の断末魔の波に見える。