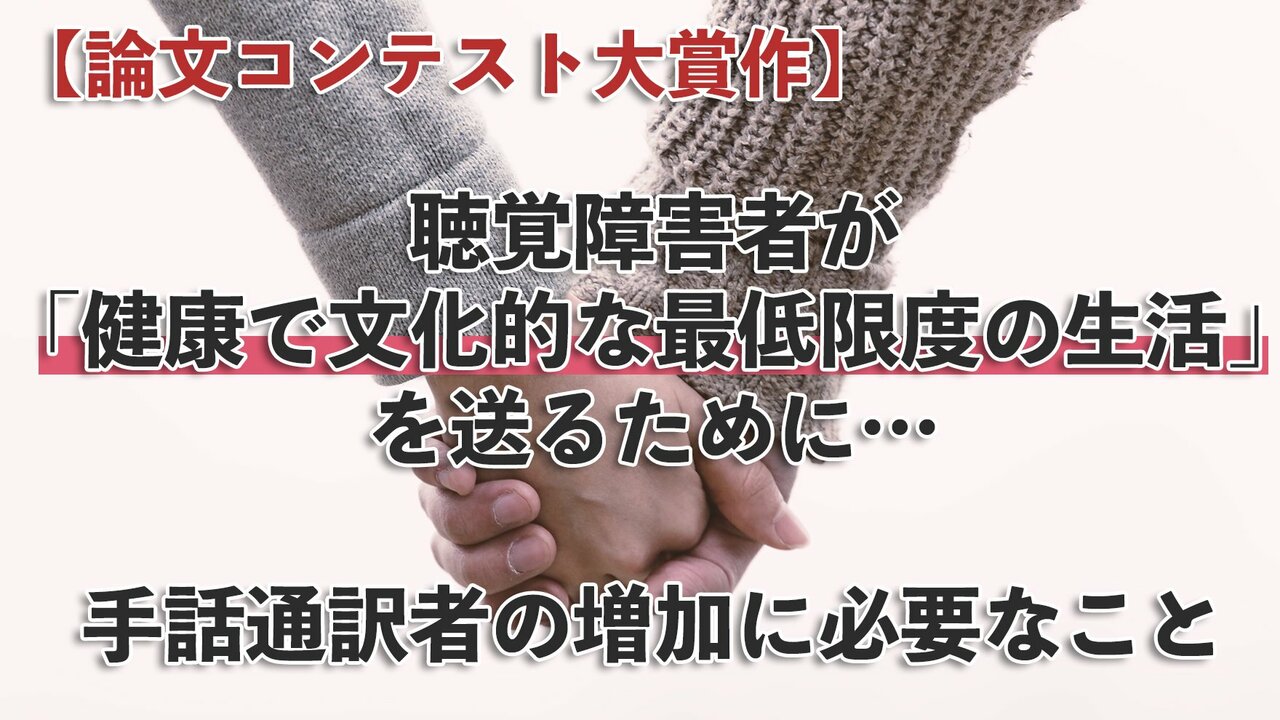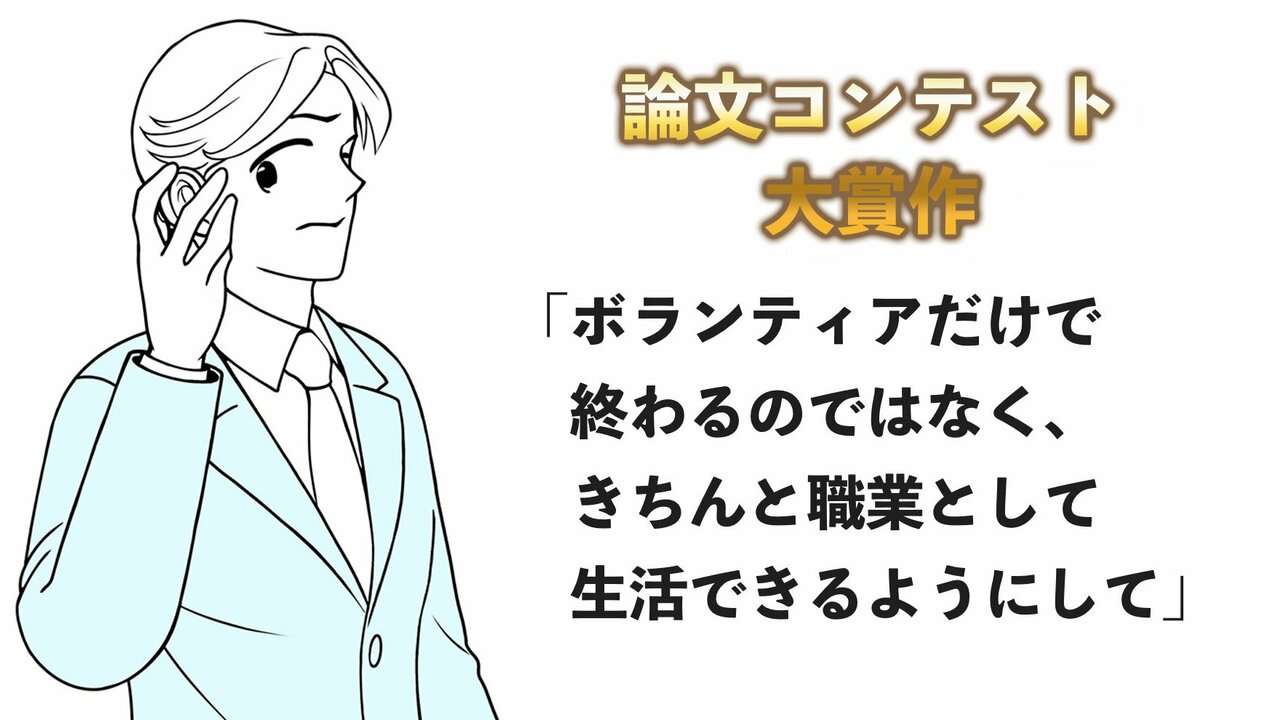1.序論
1-1 研究目的
1970(昭和45)年の手話奉仕員養成事業開始を機に、日本の手話通訳制度は整備されてきたが、専門性は認められても、専門職として認められない部分がまだ多い。
例えば、「手話通訳士」は全国的な資格でも国家資格ではない。
全日本ろうあ連盟、全国手話通訳問題研究会(略称:全通研)、日本手話通訳士協会等の運動で進んだ部分もあるが、運動だけで解決できない部分も残っている。
私は千葉県登録手話通訳者だったが、専門職を選んだつもりでも、経験を重ねるにつれ、「手話通訳者を真の専門職と位置づけるには、何か不足ではないか?」と思うようになった。
例えば、現場で困った時、相談できるスーパーバイザーがいなかったり、設置通訳者が非正規職員で肝心な時に職責を果たせなかったり、新人は入っても若くなかったり、表ではプロ意識を求められても、裏ではボランティア精神を求められていた結果、聴覚障害者の権利には敏感でも、手話通訳者自身が労働者としての自分自身の権利に鈍感だったりという状況である。
また、手話通訳者は女性が多いせいか、社会的評価が低く、待遇が悪い。
対象者から直接、苦情を訴えられるだけなら、その対象者が手話通訳制度の利用を止めるだけだが、手話通訳者が仕事を辞めれば、その手話通訳者の稼働件数分が、そのまま社会的損害となりかねない。
手話通訳者は、対象者やその家族だけでなく、一般市民から苦情を訴えられることもある。それは長年、ボランティアと誤解され、他の専門職より低く見られてきたからではないかと推測される。
障害当事者の思いに耳を傾ける行政職員や政治家はいても、その障害当事者を支援する立場の者が自分の思いを表現すると、本人の仕事に対する不満やわがままととらえられがちで、社会問題とはとらえられないのが一般的だと感じられる。
しかし、手話通訳者の待遇が保障されていないことは、聴覚障害者のコミュニケーションが保障されていないことと同義である。障害当事者の経済的負担を軽減する施策は必要だが、その障害当事者を支援する人材の待遇が悪ければ、障害当事者の生存権を守れないことになり、本末転倒である。
これでは、日本国憲法第25条第1項に掲げられている、「健康で文化的な最低限度の生活」には程遠い。