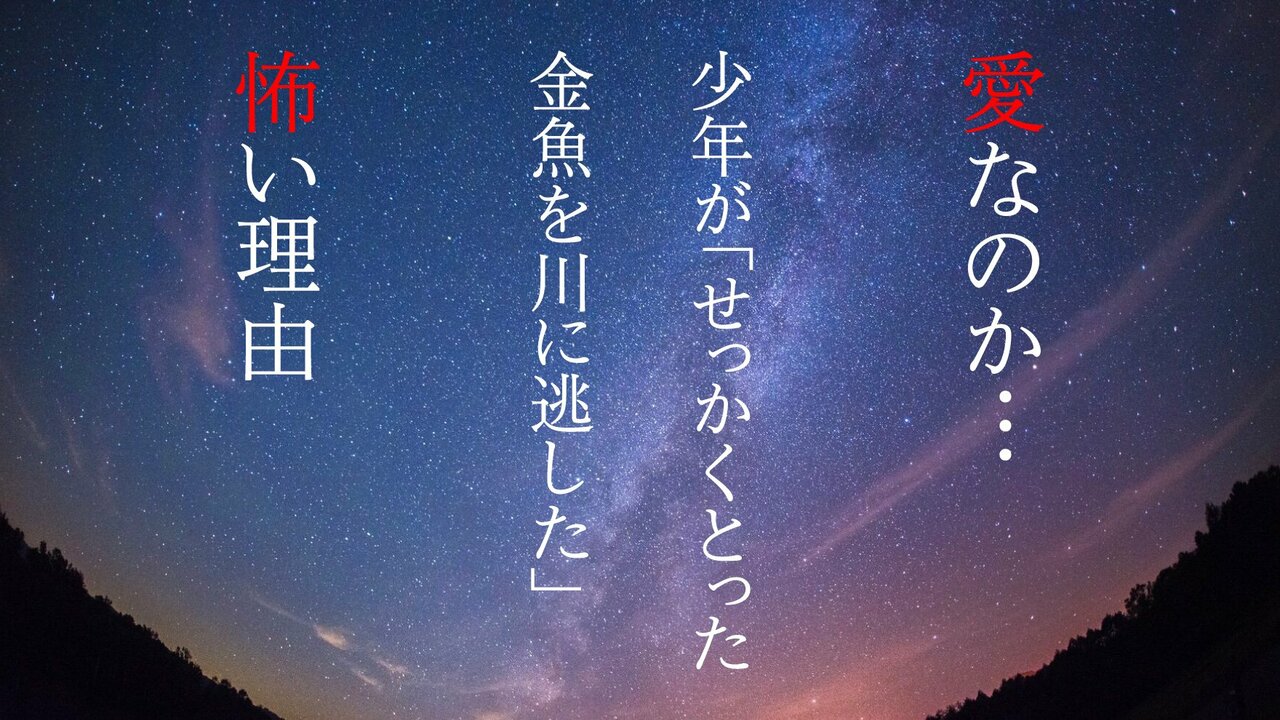圭太は、咲希と五年生になった時に初めて同じクラスになった。いつもうつむいて歩いていて、口数の少ない目立たないやつだから、それまでは咲希のことを知らなかった。
咲希は、圭太にとって、理解できないやつだった。咲希は、一言で言ってしまえば暗い。圭太だって、いつも明るく振る舞いたいわけではなかった。けれど、クラスのみんなが、明るくて頼れる圭太であることをいつも求めてくるのだ。圭太は、そういう他人の気持ちを敏感にキャッチしてしまうところがあった。
求められるのなら仕方がない。圭太はいつもその場その場で求められる役割を演じてしまうクセがあった。そのクセを圭太は幼少期からすでに持っていた。
圭太の父親は大学病院で医師をしている。母は専業主婦だ。父は忙しくてなかなか家に帰って来られないため、母の日々の関心のほとんどは、一人っ子である圭太に向けられていた。子どもを立派に育てようと思う気持ちは、どんな母親でも持つものだ。しかし、圭太の母は、その思いが少し強すぎた。それ以外に情熱を注げるものがないから、本人も気付かないうちに過剰になってしまっていたのだった。
母の「圭太を立派な人間に育てたい」という思いや圭太への期待は、圭太に「あなたは立派な人でなければいけない」というプレッシャーになって、小さい頃から伝わっていた。
圭太の振る舞いによって、落胆したり、喜んだり、イライラしたり、大げさにほめたり、一喜一憂する母を見て、圭太は母が自分に求めているものを敏感に感じとるようになった。そして、いつも母の顔色をうかがい、母が笑ってくれる姿ばかりを見せようとするようになってしまった。そうしなければ、母に嫌われると思っていたからだ。なぜなら、母はどんな圭太でも喜ぶわけではなく、自分の望む姿を見せる圭太だけを求めていたからだ。
五年生になった圭太は、そういう気持ちは「親のエゴ」だと気づくようになった。気づいてからは、少しばかり母に怒りを感じないでもなかった。しかし、この頃になると、家に不在がちである父の分まで家のことを背負い、育児に奮闘してきた母の大変さに気づくこともできていた。なので母を憎むことはできなかった。
今は、以前より母との間に距離を置き、自分の時間を作ることで、過干渉な母をうまくやり過ごしていた。