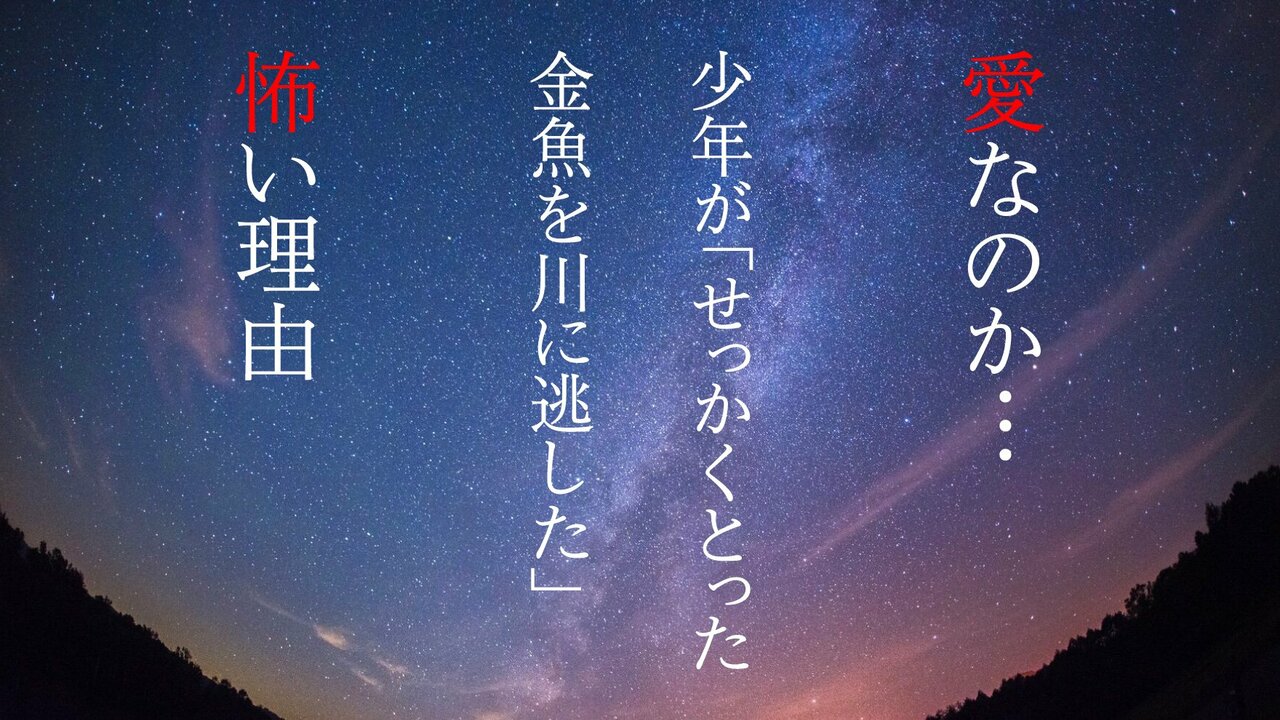一学期の終業式があった日、夕方五時頃から小学校の運動場で保護者会主催の夏祭りが行われていた。運動場の真ん中には、簡易ステージが作られ、生徒や教員、父母達の飛び込み参加によるカラオケ大会が開かれていた。そのステージの周りには、保護者会役員が出店する屋台がぐるりと円を描いて立ち並んでいる。
浴衣を着た子ども達のはしゃぎ声や、ほろ酔い気分で歌う生徒の父親の声、子ども達を見守りながらあちこちで立ち話をする親や教員達の声や、屋台の下から売り子の役員が子ども達に話しかける声、いろんな声が熱気とともに運動場に満ち満ちて、祭りらしい雰囲気を作り出していた。
小学五年生の伊藤圭太は、クラスで一番背の高い体に涼しそうな甚平をまとって、友人数人と屋台を見て回っていた。たこ焼きや焼きとうもろこし、綿菓子やりんご飴、あちこちの屋台を冷やかしながら歩いていた時、圭太はふと運動場の上にある空を見た。
圭太は夏の夕方が好きだ。冬ならばとうに暗くなる時間でも、まだ空はうっすらと明るい。夕食を軽く済ませてから塾に向かう道中、辺りが真っ暗だとそれだけで気が滅入ってしまうけれど、夏だと気分は全く違う。夏の夕日は、ゆっくりと沈んでいく。夜はなかなか訪れない。圭太はそんな空を見上げていると、親に内緒で塾の鞄を放り出し、これからどこか遠くへ出かけて行こうかという気分になる。
道の向こうに続く街にも、空にもまだまだ夜の気配はない。このまま、どんどん遠くへ歩いて行けそうな気持ちがする。街には昼間の熱気が残っている。胸の中にも、熱に浮かされたようなうきうきとした気持ちを感じる。夏が来ると、毎年のように、今年は今までに出会ったことのない何かに巡り合ってみたいと思うのだった。
「圭太、射的しようぜ」
「誰が一番うまいか競おう」
「一番のやつに、ビリのやつが何かおごるってのはどう?」
圭太は友人達に、いいね、と答えた。負けないよ、と楽しそうに。