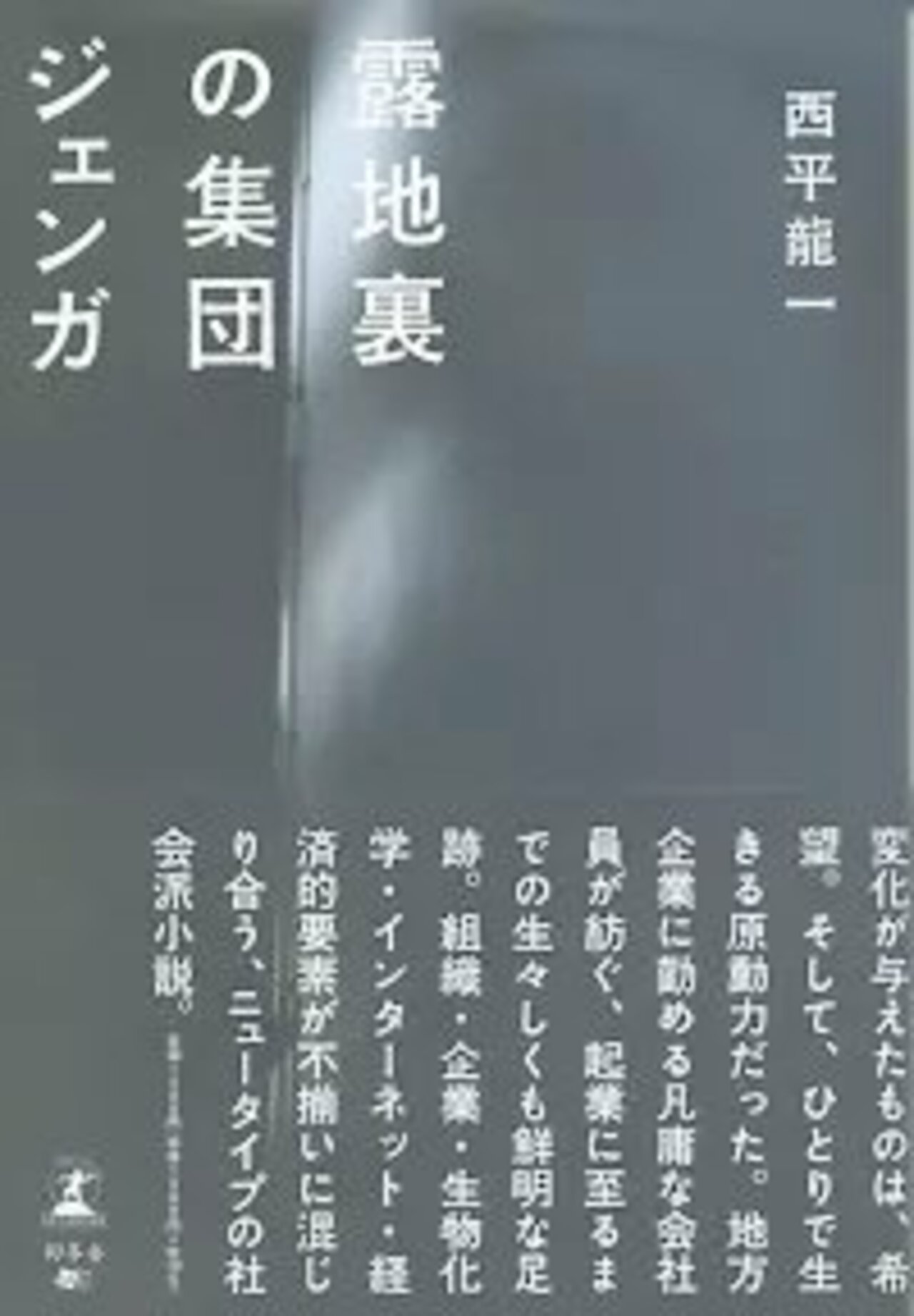第一章 洞穴の燈火
成果は少しずつ顔を出した。販売商品情報を除いた提供物に熱心になってから、時間は幾分か過ぎていた。実店舗に合わせたニッチなマーケティングレポートを、頼まれてもいないのに持参した。
年間の事業計画も、𠮟咤を恐れながら口を出した。いくつかの顧客から、お節介だから辞めてくれと苦情になった。しかしいくつかの顧客から、これまでにない相談や、謝礼の言葉が生まれることもあった。僅かであるが、僕の成績は膨らみだした。
ある日支持ある担当顧客から、心の込もった手紙と菓子が届いて、それはオープンしてから滞っていた集客が、広告の文言で一変したという嬉しい報告だった。掲載する広告には費用が大きく伴うため、その企画は重要だった。例えばメニューの構成や、その表現も顧客と共同作業で考えた。手紙の中には、謝礼の手厚い言葉が詰まっていた。
僕はすぐに川島に内線電話で報告すると、ドタドタドタッと役員室から降りてきた。そして両手を挙げてハイタッチをし、喜びに打たれるように二人で騒いだ。
「ちょっと。静かにしてもらえませんかね」
チッと舌を大きく打ったのは、部長補佐の森だった。森は上松の懐刀で、上松はいつも森を、
「如才ない」
と、甚く褒めちぎっていた。そして逸早く抜擢した。森は僕に出世競争で勝利した。しかし仇敵であるかのように、いつも冷ややかな笑いを浮かべて、何より頻繁に舌を打っていた。