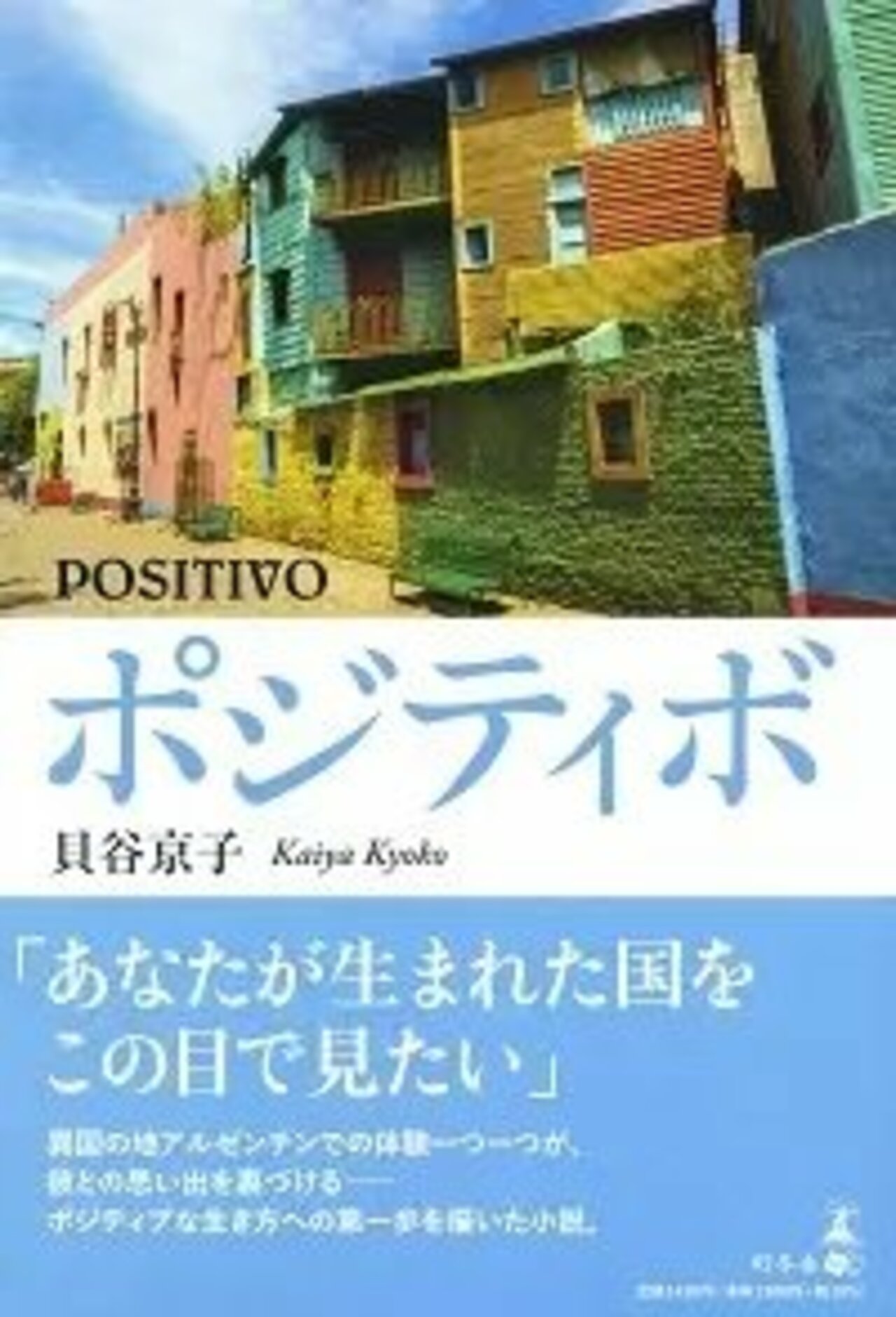「この人たち、私たちの言ってること、わかってるのかしら」
日本語が口をついて出る。
「それって、私のカスティジャーノが彼らに通じていないってことを暗に示しているわけ?」
トモコさんの目が私を射る。こっちに来てから数カ月。語学学校にも通っているからカスティジャーノも多少は理解できるようになったと思っていた。日本にいるときだって、少しでもスペイン語を身につけたいとNHKのラジオ講座を毎日聞いていたのだから、多少はわかったつもりでいた。でも、こんなシーンはテキストには出てこない。そして、私がラジオ講座で聞いていたスペイン語はスペインのスペイン語で、アルゼンチンのスペイン語、カスティジャーノは全く別物だった。だから、余計に頭が混乱する。
「ノ、ノ。彼女たちが、言葉そのものをわかっていないんじゃないかって疑ってるわけ。ひょっとしたら、アルファベットを勉強していないんじゃないのかしら」
さすがに同じことを何度も尋ねられれば、私にもひとつひとつの単語が聞き取れるようになる。それで、三度目に同じことを聞かれたときには、私は自分で「私の名前はショウコ、SHOKO」と綴りもちゃんとスペイン語の発音で答える。職業は日本語教師。
三人目の女性がようやく報告書をプリントアウトして、どうだと言わんばかりに差し出した。印刷された文面は、A4用紙の半分にも満たない。すぐに致命的な間違いに気づいた。名前がTOMOKO ISHIZAKI になっている。
他の部分に間違いがあるかどうかはわからないけれど、名前の間違いはカスティジャーノが理解できなくてもわかる。何度も繰り返し口にし、求めに応じて綴りまで伝えたというのに、彼女たちは身分を証明するのにトモコさんが渡したIDカードのほうを信用したというわけだ。私はパスポートを持ち歩くのが怖くて、部屋に置いてきたのだった。
トモコさんは、「これは私の身分証であり、彼女のではない。彼女の名前は……」とまくしたて、カードをもぎ取るようにして自分の手に収めた。
私は、目の前にあった反古紙に先の丸まった鉛筆で、まさに小学校一年生が初めて字を書きましたというような丁寧さで自分の名前を書いて、印刷されたA4用紙の氏名欄にはアンダーラインを引きまくった。それからおもむろに二枚の紙をそろえて、窓口の向こうの担当者に両手で差し出した。白衣を着た金髪女性は、最初からそう言いなさいよというような一瞥をこちらに向けて、ブラウン管をにらみつけ、キーボードを叩く。