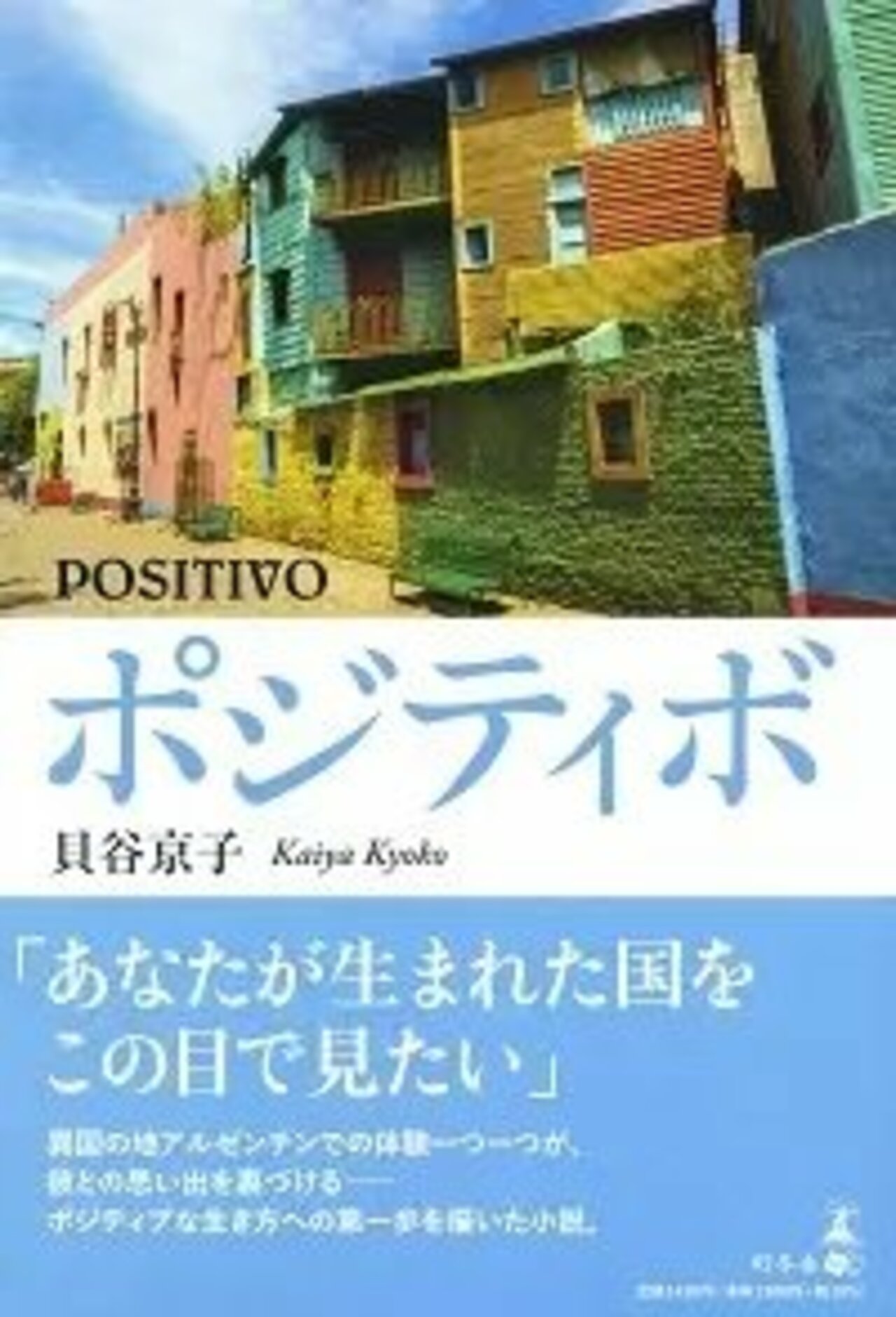1
目の前で起こったことでいっぱいいっぱいだったのが、何度も同じ質問を繰り返されているうちに、うちの近くでひったくりに遭ったときのことを思い出した。記憶の外に追いやっているけれど、とんでもないことが起こると必ず思い出すやつだ。
大晦日の夜だった。年末のバーゲンで買ったばかりの蛍光色のショルダーバッグを左肩にかけてゆったり歩いていた。二人乗りのミニバイクが目の前を走り去っていき、気づいたら左肩にかけていたショルダーバッグがなくなっていた。
すぐに近くのビジネスホテルに飛び込んで、電話を借りて警察を呼んだ。十分ほどして、二人の男が来た。一人は警察官の制服を着、もう一人は私服だった。警察であることを証明するものを見せて、電話を借りたホテルのロビーで私に事情を聞き始めた。
私は、電話をした時点で、警察が来たらすぐにその周辺をパトカーとかでいっしょに犯人捜しをするのではないかと思い込んでいたが、全くそんな気配を見せることはなかった。
二人のうちの一人が、状況を聞く。何をひったくられたのかを聞く。バッグの中に何が入っていたのかを聞く。私は聞かれたままを答える。もう一人は、携帯電話を取りだして、離れたところで電話の相手と話し始める。
あらかた話が終わったところで、電話をしていたほうの男が、私の前に座って、同じようなことを聞く。同じことを答える。後から、また一人、コートを着た男がホテルのフロントに頭を下げてこちらに来る。そしてまた、彼も同じことを聞いてきた。
「さっきも言いましたよ。どうして同じことばかり聞くんですか」
「すみませんね。これが仕事なんで。大事なことなんです」
私は、先の男が言った言葉を思い返す。
「鞄はたすき掛けにしてなかったんですね」
「ひったくられたものは、まず、戻ってきませんよ、残念ですが」
「あいつらが欲しいのは、現金。ここ、川が近いから、現金抜いたらあとは全部、川に投げ捨てですわ」
彼らは、犯人を捕まえようとする姿勢を私には微塵も見せず、盗られたものが戻ってくることはないと断言し、被害者である私に同じことを繰り返し聞いた。このあと私は、警察官にひったくられた現場を案内することになり、そこで写真を撮られたのだった。
私の手元には何も残らなかった。写真まで撮られ、書類に拇印も押したけれど、話した内容を書いた調書は、複写もされず、私にくれることもなかった。