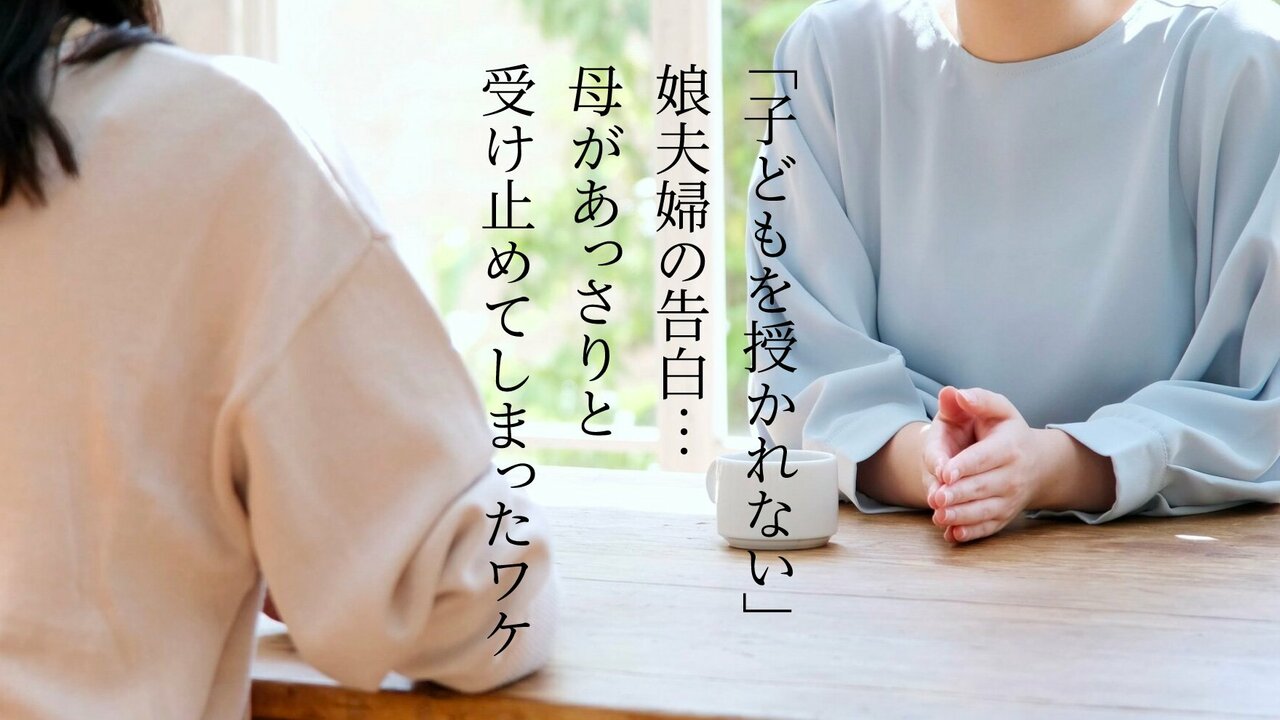一ノ四 行方不明からの最後の知らせ
私は高校を卒業し、社会人になりました。私は、新しい交流も増え、それと反比例するように、家族と一緒に過ごす時間は、徐々に少なくなっていきました。少し落ち着いていた時期もあったのですが、また父は入退院を繰り返すようになりました。
父の入院には、これまでも何度も一時帰宅(外泊)というものがありました。そして、ある寒い日。父は入院中の外泊で、一、二日間、家に帰っていたところでした。そして病院へ戻るはずの日でした。私が仕事から帰宅すると、母が私に言います。
「今日一緒に病院へ戻るはずだったけども出かける支度をしている一瞬のうちに、いなくなった。病院と警察には連絡している。叔父にも伝えている」とのことでした。
症状が落ち着いているからこその一時外泊が、まさか、こんなことになるとは。私も聞いて驚き、自転車で方々を捜し回りました。
以前、父が立ち寄ったであろう労働者の集まる場所にも行ってみました。日が経ち、私の仕事が休みの日は、さらに遠くまで行き、ガード下やホームレスの人を覗いてみたり、いくつもの公園、そしておかしいけども、子どもの遊具の山の上に上り、見渡したこともありました。他人に相談することなく一人で捜すのは、その程度が限界でした。近くを警察官が自転車で通りかかるのを見て、呼びかけようかと思いましたが、連絡はしているので、どうしようもないか、と見送りました。
心あたりは、いろいろ捜しました。もうどうしていいかわかりません。もし、どこかで元気に住んでいるなら、それでもいい、と、そう思うようにもなってきました。父が姿を消して、一週間経ちました。仕事から帰宅した私に、母が、「今日、お父ちゃんが港で遺体で見つかった、会社の人が確認してくれた。きれいだった」と、気丈に話してくれました。
あー、そうかー。私は体の力が抜け、ぼんやりしていました。父の生き様を切なく考えていました。私は職場に忌引きで休むことを伝えました。参列やお花は、お断りしました。死因は、適当な病名を言ってごまかしておきました。やはり、自殺とは言えません。
死体検案書を受け取りにも行きました。数か所の擦り傷があったことなど、父の体の最後の様子を知ることもできました。溺水の文字が、あったようにも思います。
しかし、なぜ病院に戻ることをせず港へ向かったのでしょうか。少し前に自分で訪れていたイベント会場の方に関心があったのか、遠く離れた故郷の海を思って、ただ海を見に行っただけ、そして、自分で誤って足を滑らせてしまったか、と、そんなことも、もしかしたらあるのかもしれない、と母は言うのです。誰も見ていないので、それは、わかりません。
父の入院していた病院へも、母と挨拶に伺いました。病院の先生は、「少し症状が良くなってきている冷静なときにそういう行動に出ることもあるんですよ」と、そのようなことを優しく穏やかに説明されました。納得する一方で、では先に言っておいてよと、私は思いました。でももしかすると母は、そういう注意を聞いていたのかもしれません。もちろん、こちらに落ち度があるのは当然なところです。
母も父がいなくなった当初、「しまったー」と思ったそうです。父を発見してくれた漁船は、父の故郷に近い地域の船でした。母は、これも何かの縁なのか、と言っていました。
また各地域とは別に、水上警察署というのがあることも知りました。水上警察署にも母と挨拶に伺いました。それぞれの事情により、遺体の発見は新聞報道にも出していない、とのことでした。
父の遺体は特別なので、家に連れて帰ることはできません。遺体は、斎場に運ばれ、そこでの簡単な葬儀になりました。
その後、花束を用意し、それを手向けに、港へ向かいました。岸壁に立ち母と叔父が号泣しています。私は、静かに傍らに立っていました。
父は、自分の思い描いた将来につながらなかったのか、郷里と都会との差に、とまどいながら、なじめずにいたのか。勝手なことは言えませんし病気の大変な辛さは本人にしかわかりません。思春期ごろの私は特に、やはり父とは、距離をおいていました。私も、もっと、「お父ちゃん、お父ちゃん」と、くっついていけば、もしかすると違う結果になっていたのかもしれません。
自殺という言葉は、あまり使いたくありません。今では、自死という言い方もあります。また、現代は自殺を“悪”とだけにとらえないで、その人の生涯、寿命と見る見方になってきている部分もあります。辛い病気からも解放されたのかな、と母は言います。しかし、これらのことを全ての人にあてはめてはいけないことも、私たちはわかっています。
また、当時、健在であった祖母よりも先に自ら逝ってしまったこと、これは人にとっては最大の悲しい出来事です。母は、般若心経を覚え、毎日、仏壇を前にし唱えてきました。父は、残された私たち家族が、しっかり強く生きていくようにと、はるか空の上から私たちを見守ってくれていると、それだけは、真実だと感じています。