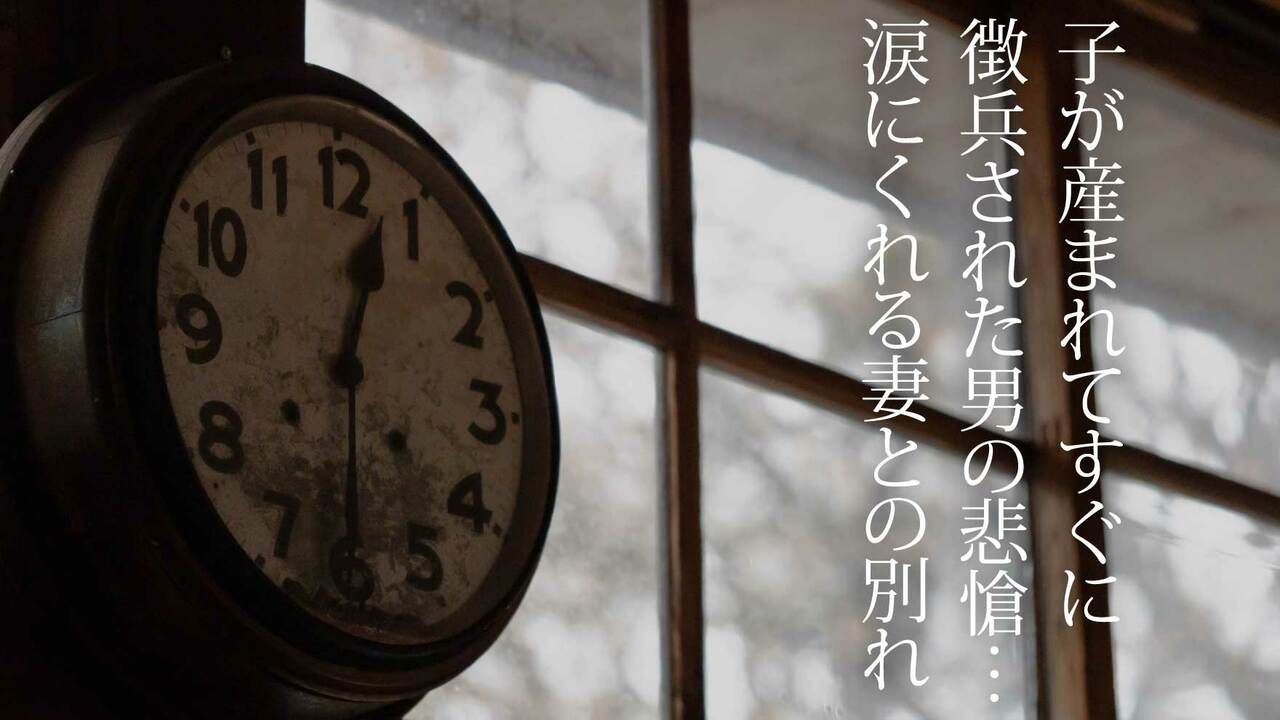【前回の記事を読む】「父危篤」の電報が入り帰ってみると父がピンピンしていたワケ
母ミヤコ
姉が嫁いだ翌昭和一四年二〇歳、ミヤコは親戚の紹介で隣県のK町のN洋装店へ花嫁修業も兼ね住み込むこととなった。
ミヤコは、とうきびの取入れの忙しい最中に姑に無理を言い野良仕事を抜け出してきた姉の嬉しそうに話すおのろけを聞きながら駅に着いた。
線路に沿って流れる吉野川を眺めていると、二年前の秋、姉や父に見送られ真っ黒な煙と蒸気を勢いよく吐き出す汽車に、一人乗り込んだことを思い出した。やっと一八歳になったばかり、自ら希望したお手伝いの仕事とはいえ、新調した一張羅のお気に入りの着物にも浮かれた気持ちにはなれず手を振る姉にちょっと手をあげ一、二度うなずいただけだった。
ところがその日のミヤコは、雲一点無い抜けるような青空や両岸にそそり立つ山間の杉林の深緑に染まるゆったりとした流れと急流のしぶきが織りなす大歩危の景観、川にせり出す真っ赤に色づいたハゼや黄褐色のモミジ、カエデの紅葉は目にも鮮やかで、いつも見慣れた風景に見とれてしまった。
姉はと見ると、駅の柵の片隅で控えめに手を振りながら、新妻らしい幸せそうなほほ笑みを浮かべている。藍色の布地に紅と白色のかすり模様のモンペ姿。真っ白な布の姉さんかぶりが初々しさを添えていた。
ミヤコは待ち時間の間、実家の屋根裏部屋の夥しいお蚕さんや急坂のミツマタの栽培、誰かは必ずぐずっていた弟妹の子守り、夜明けから日暮れまでの野良仕事、男しや女子しの野良着姿を思い浮かべつつ、車窓から少し身を乗り出し笑顔いっぱい両手で姉に大きく応えながらこれからの生活に思いをはせた。
K町の目抜き通りにあるN洋装店は、想像していた以上の店構え。男女一〇数名の職人を抱える大店だった。職人たちは町や村の着物姿を見るにつけ機能性に富む洋服に将来の夢を託し野心的だった。ミヤコはそのような男たちを見るのは初めて、何かしら頼もしく、明るい気持ちになった。