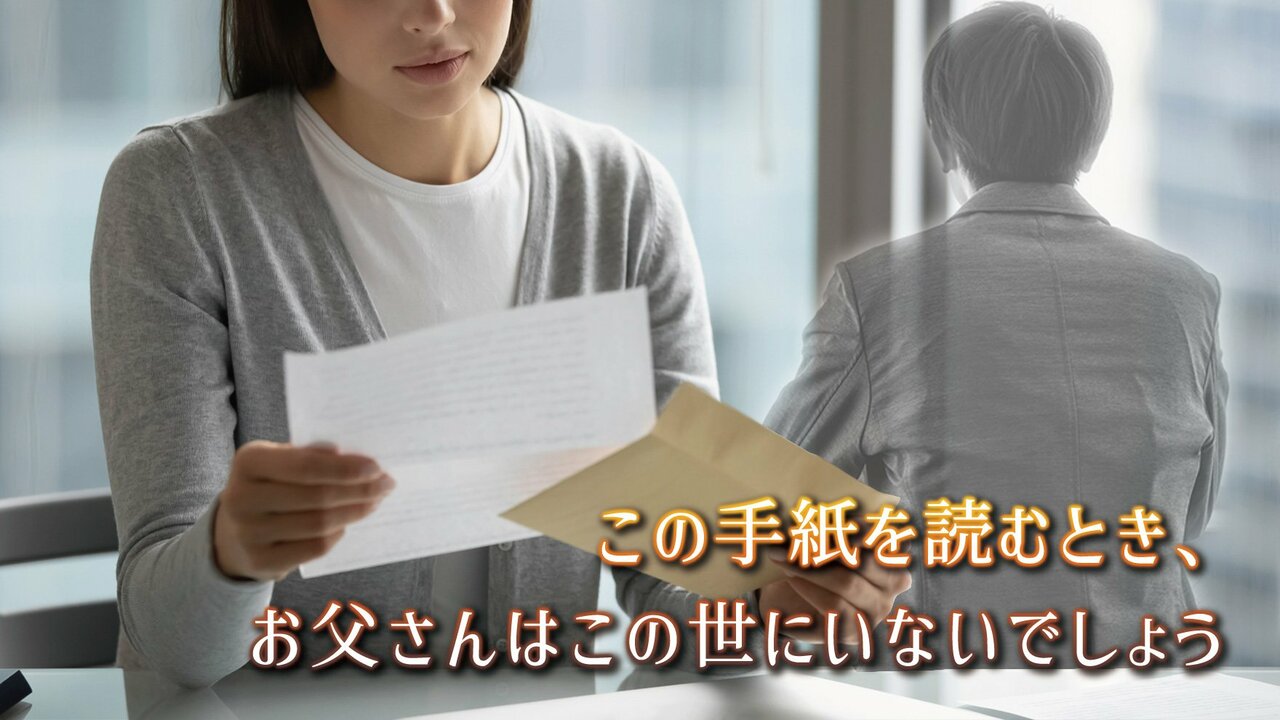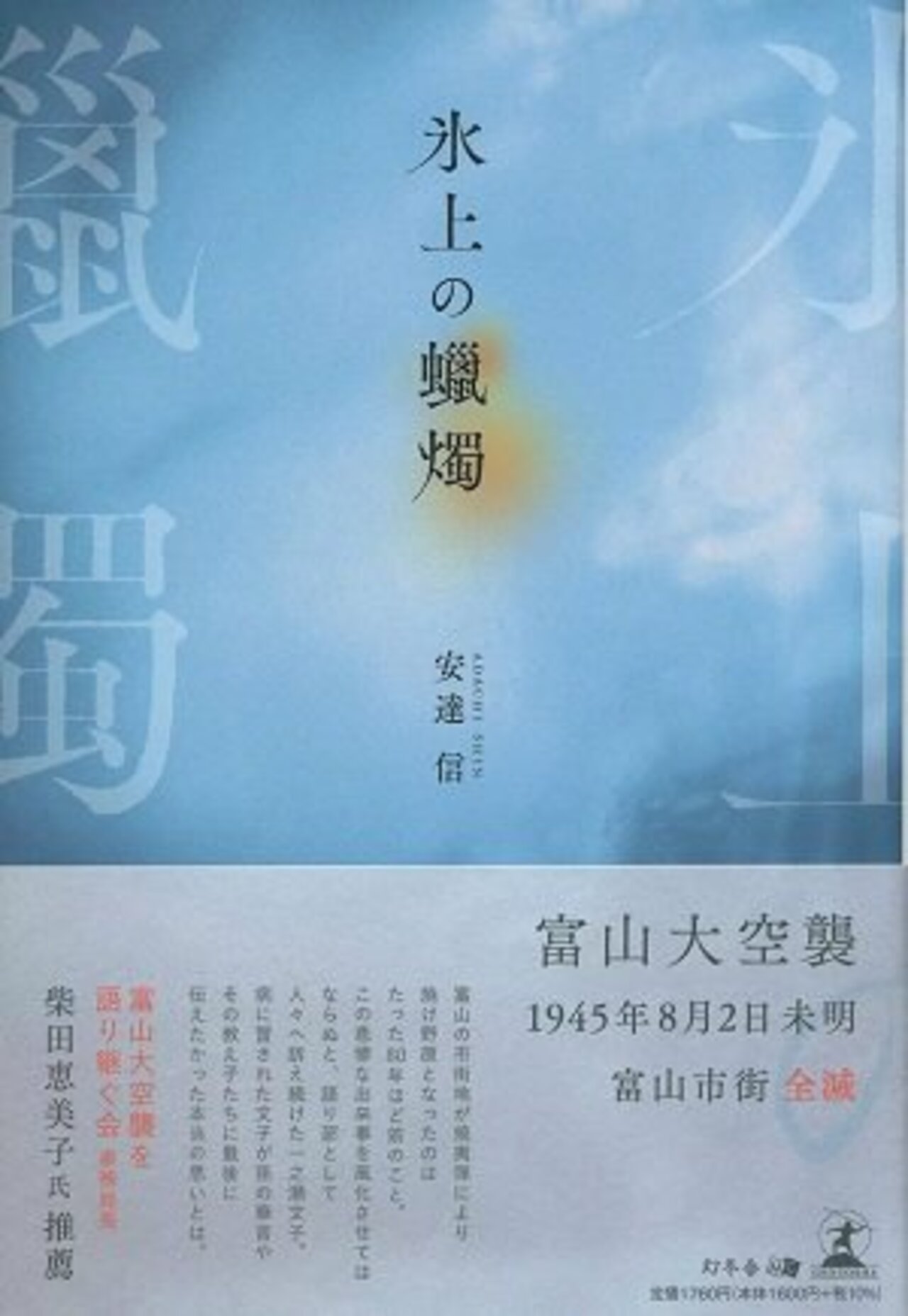一闡提の輩
我に返った直之は、
「瑠衣。瑠衣。お父さん、取り返しのつかないことしてしまった」と目に涙を浮かべながら娘を、すまなさそうに見つめていた。
「お父さん。お父さんは何も悪くない。悪いのは私なの。お父さん、本当にありがとう」と瑠衣は手を目にやって溢れる涙をぬぐった。
直之は、バスタオルの端をつまみながら瑠衣の頬を優しく丁寧に拭き、
「ごめん。ごめんね。ごめんなさい」と、音にもならないかすれ声でうなだれた。しばらくの間、二人の目はうつろだった。
直之は寝間着を着直し、うなだれたまま瑠衣の部屋を出て行った。
瑠衣は父の汗がついたバスタオルで、ゆっくりと愛おしそうに、丹念に自分の身体全身を拭き胸の周りに巻き付けた。
瑠衣は押し入れから自分の敷布団を出し、カバーも敷かずに父の匂いの付いたバスタオルを巻いたまま横になった。
バスタオルは、幼いころよく嗅いだ父の懐かしい香りがした。
「忘れていなかったんだ……」
その夜、瑠衣はなかなか寝られなかったが、安心している自分がいた。
お父さん子だった瑠衣は、父にいつも見守られながら育った。
ウトウトしながら、父との昔の思い出を夢見心地にたどった。
よちよち歩きできるようになったころ、母に編んでもらった花籠を持って父の手をしっかりと握りしめながら道端に咲く小さな花を摘み、
「おかあさん。おかあさんに……。プレゼント。プレゼント……」と手を振りながら自宅に帰ってきては、佳奈を困らせたことが何回もあった。
何よりも父のそばにいるだけで、瑠衣は幸せだった。
お通夜のあと瑠衣は、一人で父の顔が見たくなり、仏間に足を運んで遺体の横に正座し手を合わせた。お仏壇の前に座り直しろうそくに火をともし、真ん中にある阿弥陀如来の絵像に向かって合掌し念仏を称えた。
礼拝を終え何気なく見上げると、絵像が少し横に傾いていることに気づいた。直そうとして立ち上がり絵像に手を触れたとき、白い封筒がこぼれて落ちてきた。封筒の表には見なれた字で、「瑠衣へ」とだけ書かれていた。おもむろに封筒を開け、中にある手紙を取り出した。
『父の遺書』だと直感した。