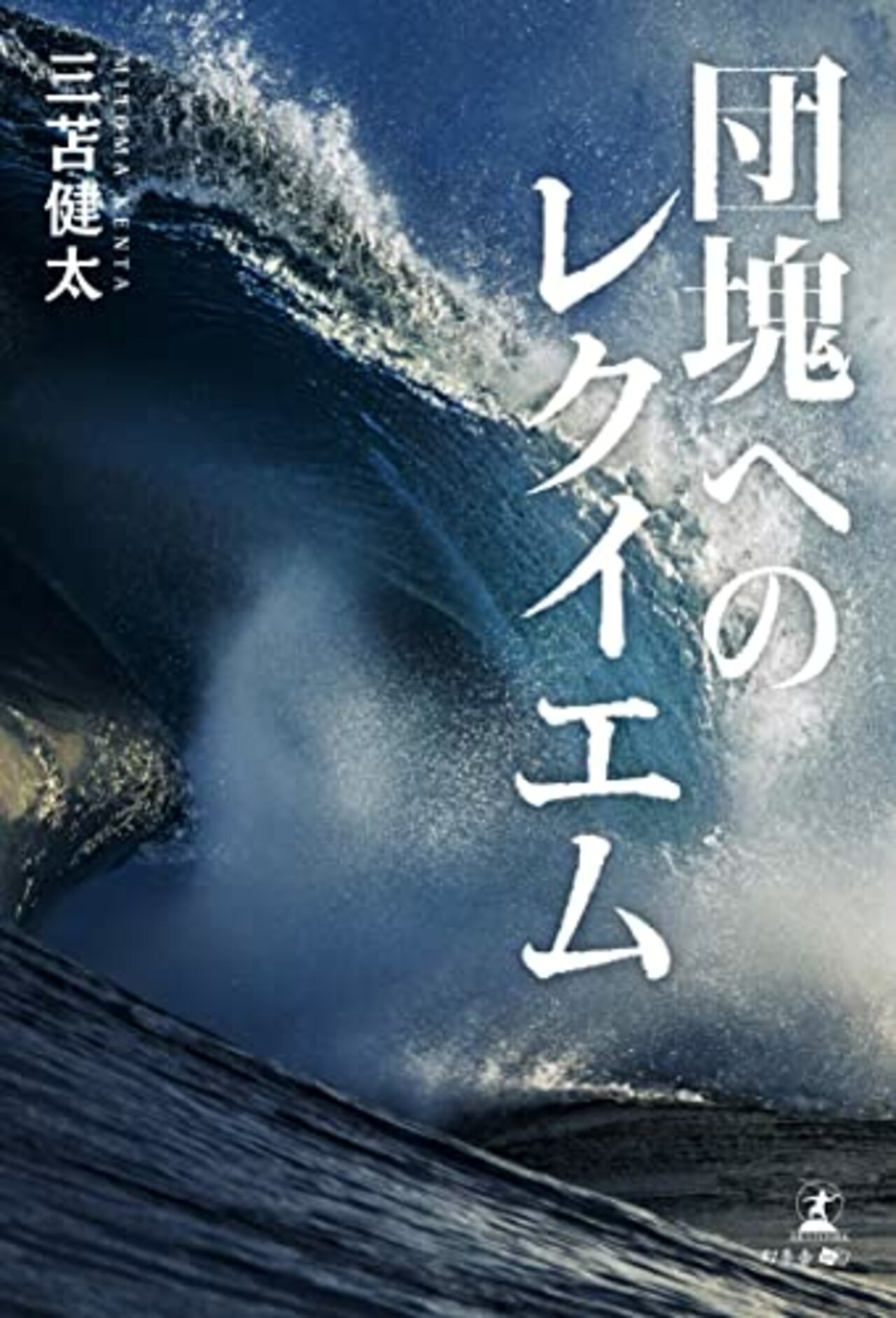左沢はスマホを待ち受け画面に戻しながらつぶやいた。試作プログラムの仕上がり具合から、周平は遅くても九月末には福島行きを決めていたと考えてよさそうだ。周平と最後に会ったのはアラスカ出発前日の十月二日だった。新宿のシティホテル一階のカフェラウンジで、この試作プログラムの打ち合わせをしているとき、周平はすでに福島行きを計画していたに違いない。
そして、福島行きに合わせ、このプログラムの完成を急いだのだ。プログラムの出来栄えから、徹夜の作業も一度や二度はあっただろう。しかし、福島行きが事前に計画されたものだったとしても、その目的が心中であったとはとても思えない。それに、二十日完成で良しとしていた試作プログラムを、なぜ、福島行の前日までに完成させようと急いだのかも不可解だ。
左沢は、周平に最後に会った十月二日に記憶の糸を手繰る。あの日は、アラスカ紀行を企画した出版社との打ち合わせのあと、都庁前のMZビルのロビーで周平と落ち合い、一緒に昼食をとりながら、「ケアタイマ試作プログラム」設計書の細部の確認の他、左沢の留守中の発注元への対応などについて打ち合わせる予定だった。
しかし、出版社との打ち合わせが長引いてしまい、結局は午後二時に、左沢がいつも利用するシティホテル一階のカフェラウンジで落ち合うことになった。左沢が先に着いて待っていると、周平は約束した時刻の五分前に現れた。いつものように綿パンにTシャツだが、急に冷え込んだあの日は、その上に濃紺のジャケットを羽織っていた。こだわりか無頓着か、周平の綿パンにTシャツは年間を通して変わることがない。
左沢の設計書の細部や要点の説明に、周平はただうなずくだけで特別な質問はしなかった。前の週に送信しておいた設計書には赤ペンで何やらいろいろ書き込んでいるところから、試作プログラムについて事前に検討していることを窺わせた。
「日本に帰る二十日までに作ってくれればいいよ」、と言うと、周平はほんの少しばかり間を置いて「はい、できるだけ早く作るようにします」、と答えた。今から思えば、あの少しばかり空いた間は、福島行までに試作プログラムを完成させる算段を心のなかでしたものだろう。
間といえば、会話のなかでもうひとつ気になることがあった。それは、話が介護サービス一覧表の設定になったときだった。食事介助や入浴介助などのすべての介護作業をセットするところだが、介護管理者は利用者ごとに一覧表に設定された各作業の要否と、実施時刻を決めて計画ファイルに書き出し、介護士は担当する利用者の計画ファイルを自分のスマホにダウンロードし、計画に従って作業を進めていくことになるため、一覧表の設定は「ケアタイマ」の重要ポイントのひとつになっている。だが、あの時点では、まだその介護サービスは完全には洗い出されていなかった。
「今わかっているものだけの仮設定でいこう」、と左沢が言うと、周平はしばらく間を置いて、「なんとかしてみましょう」、と言い、自信すら見せた。あのとき周平は誰かに相談しようと見当でもつけていたのだろうか。なんでもない間だったが、今思い返すと、誰か心当たりがあったのだろうかと考えさせられる。
「福島に行ってみるか」
左沢は頬杖をついたままパソコンの画面を睨んだ。